

前回(#2)教わった読書の悪口ゲームで、読書に対するネガティブな感情を払拭できたら、他の“読書ゲーム”もはじめてみましょう。
作家で書評家の印南敦史(いんなみ・あつし)さんの著書『読書する家族のつくりかた 親子で本好きになる25のゲームメソッド』(星海社)では、さまざまな読書ゲーム25種類が提案されています。
そのゲームメソッドのうち、今回は未就学児~小学校低学年でもできそうなもの5点を抜粋してご紹介いただきます。
※全4回の3回目(#1、#2を読む)
①目が覚めた直後 朝の10分間読書
親子で読書を習慣づけるために、まずは朝の10分読書をはじめてみましょう。
「たとえば朝食前後、そのまま家族がそろっているテーブルで、10分だけ本を読む時間をつくりましょう。
ポイントは、タイマーをしっかりかけること。10分間、家族で顔を突き合わせ、本を読む時間を共有するんです」(印南敦史さん)
1冊読み終えるごとにポイントがつくようにし、たくさん読んだ人にポイントを付与したりすると、さらにゲーム性が高まり、モチベーションも上がります。
「忙しい朝ですが、工夫次第で《10分間》を捻出(ねんしゅつ)することはできるはずです。朝から本を読むことで、頭がさえてすっきりしますよ」(印南さん)
朝の10分読書の最重要点は、おもしろくなってきても「10分で止めること」。
「10分読んだらおもしろくなってくるのは当然の話ですが、あえてそこで止めてしまえば、それが『早く続きを読みたい!』という気持ちにつながり、“次の読書”への意欲が高まります。
すると、学校から帰ってきたらゲームをやるような子も、『あの続きを読みたい!』と思って本に手を伸ばすかもしれない。つまり、目覚め10分読書は、そんな“次の可能性”を高めてくれるわけです」(印南さん)
②ほしい本リクエスト箱を作る
「《おもちゃはダメでも、本なら買ってもらえる》という環境が家庭内にあれば、必然的に読書は身近なものになります。僕自身がそういった環境で育ったので、本を身近に感じることができました」(印南さん)
リビングでも玄関でもトイレでも、家のなかのどこでもいいので「ほしい本リクエスト箱」を置いておき、「ほしい!」と思った本の書名や著者名を書いて投書できるようにするのです。
「月に1度とか2度、家族みんなで集まってその箱を開きます。ほしい本リクエスト箱を開いたら、親はリクエストされている本を、スマホやパソコンですぐに“ポチり”ます」(印南さん)
いまの時代は「スピード感を活用できる」というメリットがあります。ほしい本リクエスト箱を開いたら、親はリクエストされている本を、スマホですぐに購入してあげましょう。
「それだけで、子どもはワクワクするのではないでしょうか。そしてそれは、届いた本への好奇心を高めてもくれるはず。
自分がリクエストした本という愛着、ほしいものが手に入るという満足感、『しっかり読もう』という気持ちなどが、読書習慣の定着につながっていくことになるでしょう」(印南さん)
③家族で図書館へ 借りてきた本公開タイム
夏休みを目前にして、読書感想文などの課題をするために地域の図書館へ足を運ぶ機会が増える時期です。
しかし、ただたんに子どもを図書館へ連れていき、本を選ばせておしまいではなく、ここにもイベント性を持たせてほしいと印南さんは言います。
「図書館を利用したひとつの家族のイベントというか、これもゲームにしてしまうわけです。図書館に着いたら30分など時間を決めて別行動をし、おのおの好きな本を選んで集合します」(印南さん)
帰宅したら家族でテーブルに集まり、借りてきた本を家族にアピールします。
「どうしてこの本を読みたいと思ったのか、を家族の前で発表します。ゲームと呼ぶのがはばかられるほどシンプルですが、定期的なイベントにするだけで、本がグッと近い存在になり、家族でのコミュニケーションも増えるのではないでしょうか」(印南さん)
図書館には、「予想外の本と出会える可能性がある」と印南さん。館内を気まぐれに歩いているだけで、普段なら興味を持たないようなタイプの本に出会えるかもしれません。
「地域にもよりますが、いまの図書館は広くて清潔でおしゃれで、ずっといたくなるような仕掛けがなされているところが多い。全世代を対象としているので、夏休みに家族で読書ゲームをするのに最適な空間ですよ」(印南さん)
④気に入った本を飾るスペースを作る
いいなぁと思った本を家族に紹介するときに、押し付けがましくない、とっておきの方法があります。
「表紙が魅力的な本は少なくありません。そこで、おすすめの本を面出し(表紙が見えるよう平面に並べる)することによって、『この本、いいと思わない?』というメッセージを家族に送るわけです」(印南さん)
いつもの本棚に面出ししたり、リビングなどの家族が集まりやすいスペースに飾っておくのも効果あり。飾ってある本を見た家族が、こんな本あるんだなと気づけたり、家族のお気に入り本に興味を持つきっかけになります。
「僕にも経験があるのですが、家族の誰かがその面だしに惹かれて本を持っていったとしたら、『してやったり!』といった気分になれます(笑)」(印南さん)











![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)





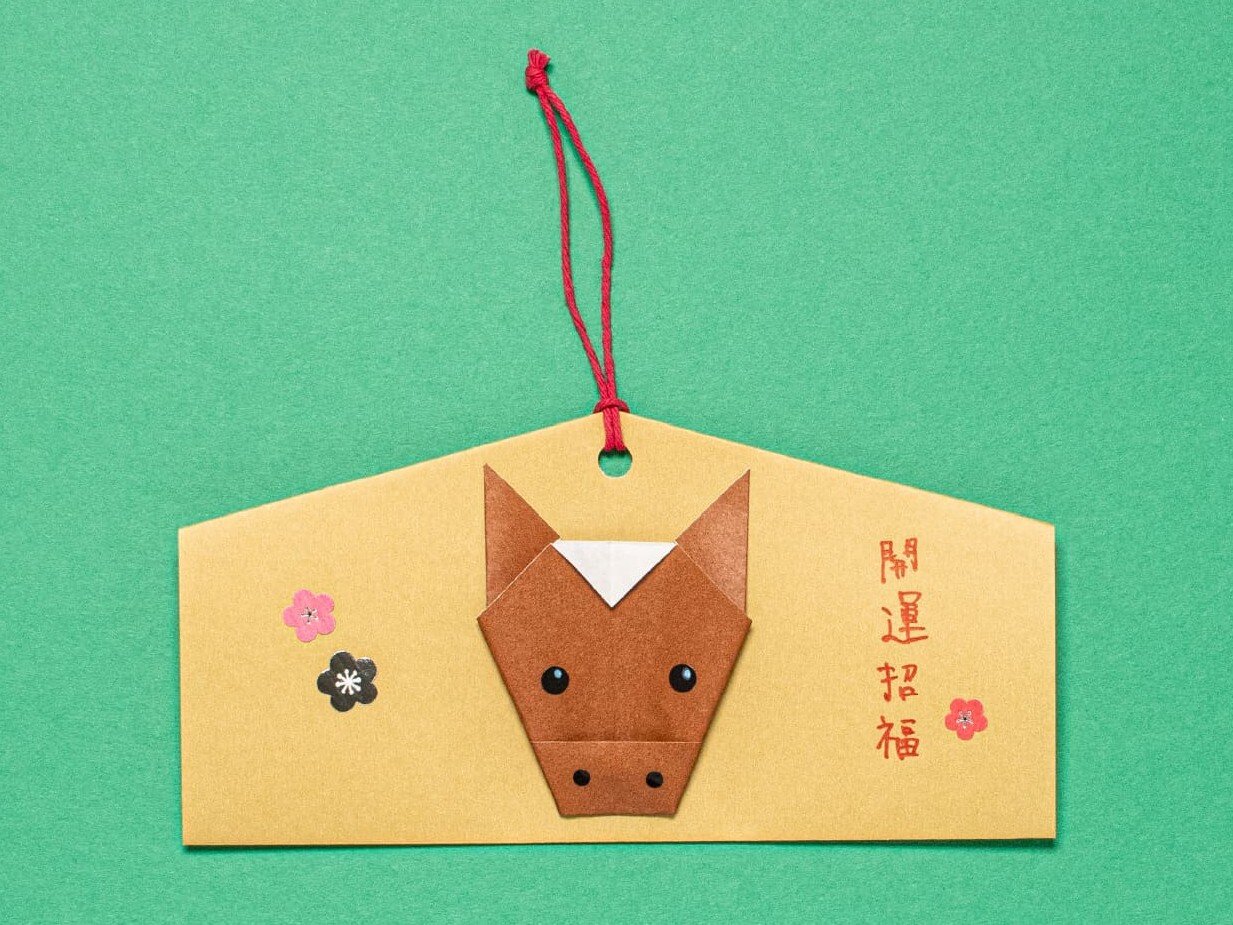



![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)





















































































