

「不登校の子」と親の気持ちがラクになる小説・マンガ5選
【飯田一史のこの本オススメ! 第3回】学校に行けない子どもに寄り添う本を紹介 (2/2) 1ページ目に戻る
2025.07.04
ライター:飯田 一史
不登校・発達障害当事者によるエッセイマンガ
学校に行けない・行かない状態になる理由として、教師や学校の人間関係が悪化する、または嫌いになることはめずらしくないですが、周囲とうまくやれない理由に発達障害が関係することもしばしばあります。
うちの子は小1から「学校行きたくない」と言っていますが、児童精神科で検査したところ、ADHDであり、若干ASD傾向もあるとのことでした。
注意力が散漫または過集中のどちらかで、話しかけても聞こえていないことがよくあります。気が散りやすいので物事を進めるスピードにムラがあり、かといって急かされるとパニックを起こします。
自分に興味がないことを何十分も座って聞いているのがそもそもムリです。
それならたしかに学校という制度自体に不適応になるよな、と納得しました。
こういうタイプの不登校も現実にはめずらしくないのですが、こちらは「物語」では比較的フォーカスされにくいように思います。
というのも、人間関係や心のわだかまりが理由で学校に行けないのであれば、「こじれていた原因を解消した結果、行けるようになった」といった展開をつくりやすいのですが、生まれ持った特性は変えられないからです。
ですからこちらのタイプの不登校は実体験をベースにしたエッセイマンガなどのほうがよく描かれています。
私の家には不登校や発達障害をテーマにしたエッセイマンガがそれなりにあるのですが、私の子どもに聞いたら何度も読んでいるのは、下記の3冊とのことでした。
『学校へ行けない僕と9人の先生』

著/棚園正一 双葉社
『学校へ行けない僕と9人の先生』では発達障害という言葉は出てこないのですが、少なくとも発達障害と定型発達のグレーゾーンなのかなと思われる描写がいくつかあります。
『発達障害と一緒に大人になった私たち』

著/モンズースー 竹書房
『発達障害 僕にはイラつく理由がある!』

著/かなしろにゃんこ。、監修・解説/前川あさ美 講談社
これらのエッセイマンガでは、親や第三者の視点からではなく、不登校や発達障害の当事者から見える世界、日々感じていることが描かれているから、共感が深いのかなと解釈しています(かなしろさんの本は基本的には親視点ですが、当人にも話を聞いて描かれています)。
不登校当事者が書いた本やマンガをいくつか読んでいくとわかってくるのは、現実生活では「何か原因があって不登校になっているのだから、それを取り除けば登校できる」という考え方、登校をゴールに設定したうえでの「行けない理由探し」自体が不毛で的外れな犯人捜しになることが多く、採用しないほうがよさそうだ、ということです。
むしろ多くの不登校エッセイマンガなどで描かれているのは、親・大人側が「なんで行けないの?」と問うて問題視して原因探しをしたり、「こうなってほしい」「こうするべき」という自分の理想や願望を子どもに押しつける、コントロールしようとするのをやめて、たんに「行けないんだな」と、「そういうもの」としてまるっと受けいれることをきっかけにして親子関係が改善に向かっていく姿です。
不登校当事者ではない大人たちは、「これが原因じゃないか?」と思ったものをどかしてみたり、そこから離れたりすればいいと考えがちです。それでうまくいく場合もありますが、それらをやってみたところで学校に行けるようになるとは限りません。
物語とは違って「行けない」理由をあれこれ探して解決しようとしても、現実ではすっきりしないことはよくあります。
物語は物語で、現実ではぐちゃぐちゃで解決不可能に思える困難な事象であっても解決に向かうプロセスを描くことで、読者を安心、満足させるといった価値があります。物語を否定しているわけではありません。
寄り添うことが解決の近道
親が考え、望む方向に誘導しようというスタンスでは、摩擦は解消できない。
そうではなくて、行けない・行かない子に寄り添うこと、行けない・行かないことを前提にコミュニケーションを取ることからしか、お互いにとって意味のあるやりとりは始まらないのではないかと、私は個人的には思っています。
ここで紹介した本やマンガは、大人がまず読んだあとで、お子さんの目に付くところに置いておくなり、手渡してみるといいかもしれません。親が先に読むことで子どもの心情を想像する助けとなり、子どもが読むことで「自分だけじゃない」と感じるきっかけになるでしょう。読書を通じて親が子どもを理解し、子どもの気持ちがラクになることにつながってくれたらと願っています。











![“高い絆創膏” 不適切な使い方をすると化膿!? 「正しい使い方」とは[医師監修]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/050/large/72bf4190-f850-4e30-99f1-d97fcf8571f2.jpg?1765410326)


![子どもに“高い絆創膏”と“安い絆創膏”どう使う? 「重ね貼りOK?」「やけどに貼っていい?」などの疑問に皮膚科医が回答[医師監修]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/053/large/59717e7c-3955-4664-a71c-e2a2e8b45c97.jpg?1765256342)





![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)













































































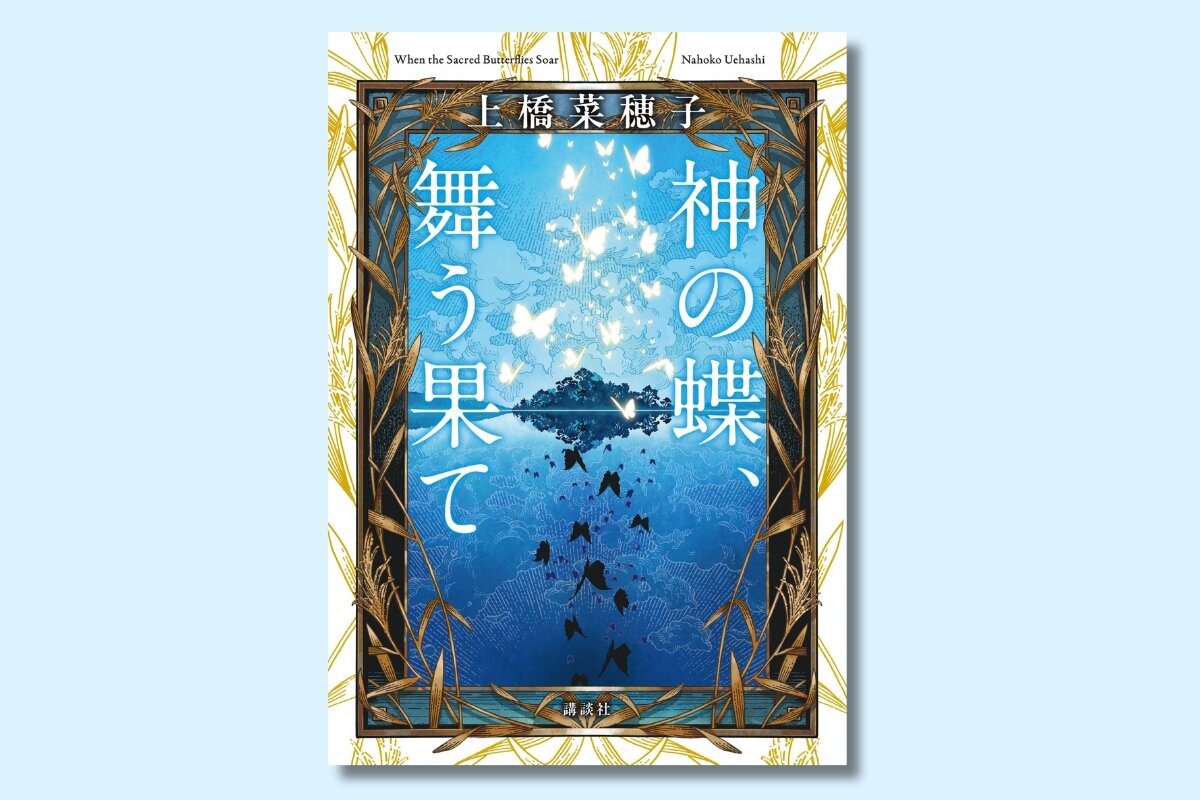





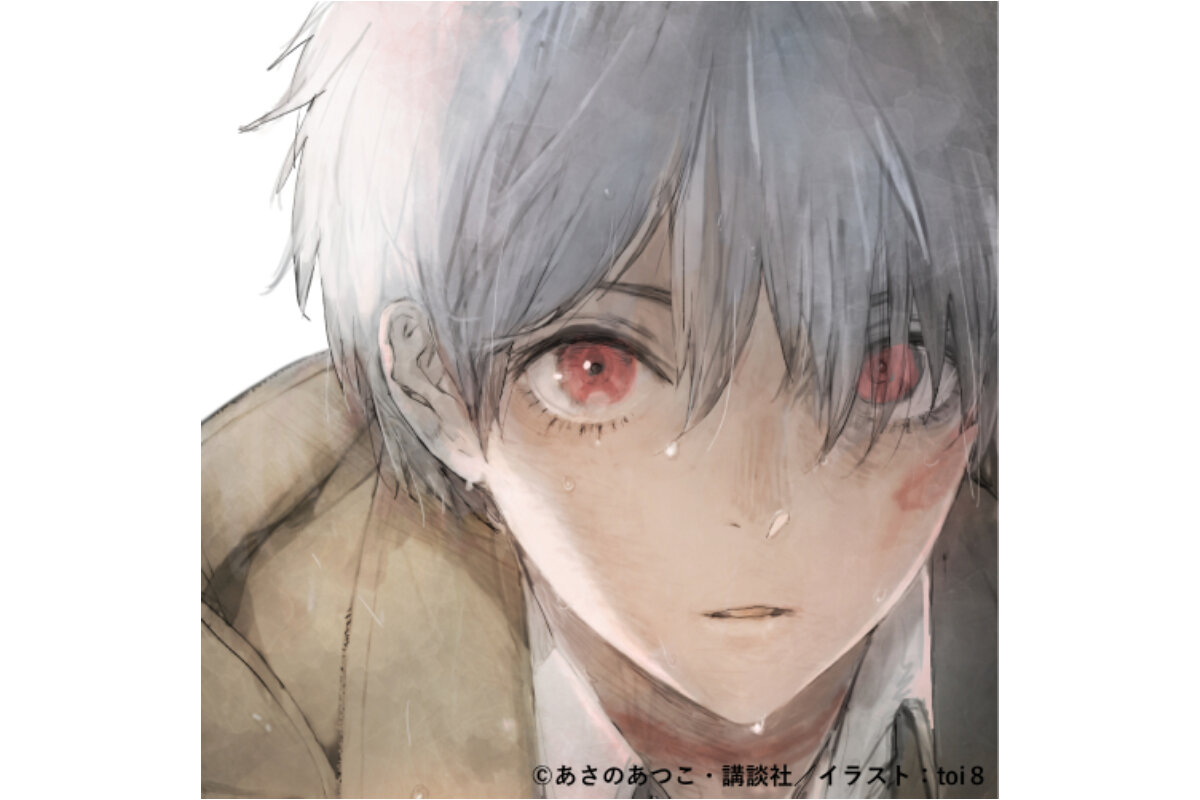
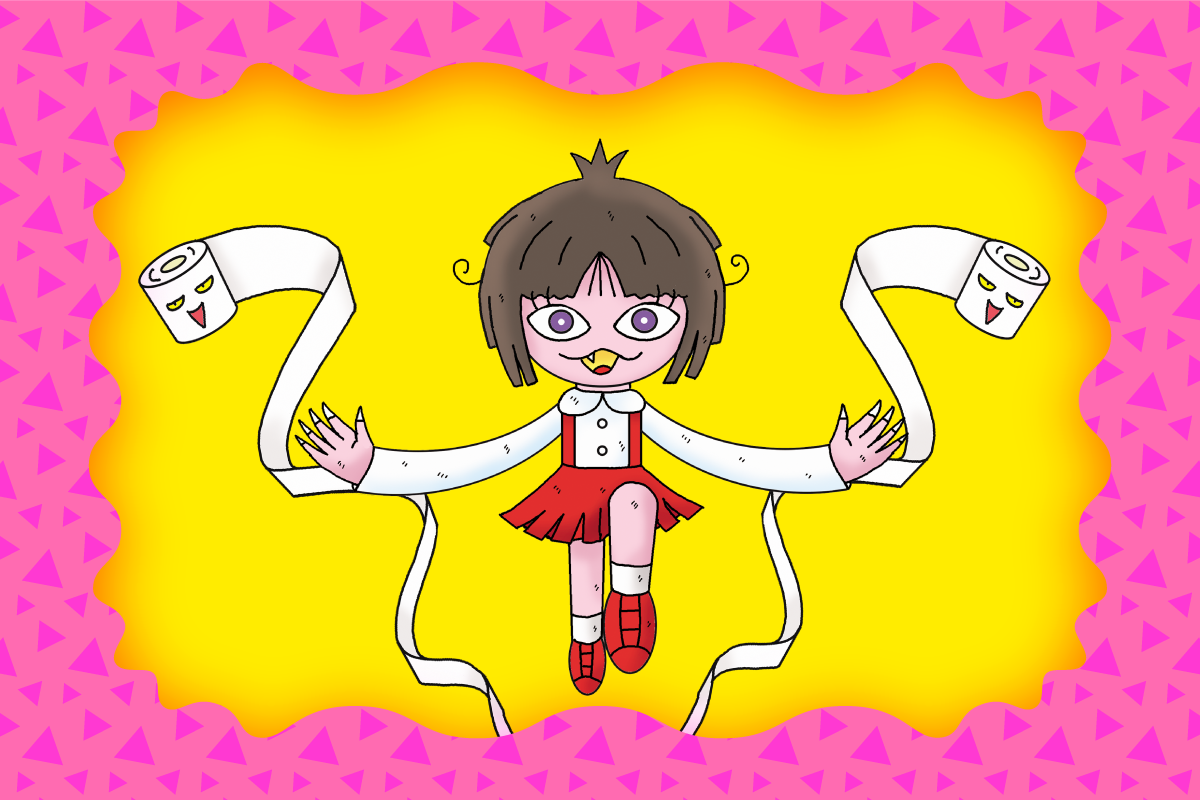

飯田 一史
青森県むつ市生まれ。中央大学法学部法律学科卒。グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了(MBA)。 出版社にてカルチャー誌や小説の編集に携わったのち、独立。国内外の出版産業、読書、子どもの本、マンガ、ウェブカルチャー等について取材、調査、執筆している。 JPIC読書アドバイザー養成講座講師。 電子出版制作・流通協議会 「電流協アワード」選考委員。インプレス総研『電子書籍ビジネス調査報告書』共著者。 主な著書に 『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』 『「若者の読書離れ」というウソ』 (平凡社)『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの?』(星海社)『ウェブ小説30年史』(講談社)ほか。 ichiiida.theletter.jp
青森県むつ市生まれ。中央大学法学部法律学科卒。グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了(MBA)。 出版社にてカルチャー誌や小説の編集に携わったのち、独立。国内外の出版産業、読書、子どもの本、マンガ、ウェブカルチャー等について取材、調査、執筆している。 JPIC読書アドバイザー養成講座講師。 電子出版制作・流通協議会 「電流協アワード」選考委員。インプレス総研『電子書籍ビジネス調査報告書』共著者。 主な著書に 『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』 『「若者の読書離れ」というウソ』 (平凡社)『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの?』(星海社)『ウェブ小説30年史』(講談社)ほか。 ichiiida.theletter.jp