

生みの親と暮らせない子どもは約4万2000人 「養子縁組」の現在地 〔養子・里親の実態と仕組み〕
養子縁組の現在地 第1回~養子・里親の実態と仕組み~ (4/4) 1ページ目に戻る
2025.04.02
日本財団 公益事業部 子ども事業本部長:高橋 恵里子
2017年には厚生労働省が、おおむね5年以内に3歳未満の里親委託率75%以上、特別養子縁組を1000件以上成立させる目標を掲げました(※)。
しかし、残念ながら特別養子縁組の数はここ数年で減少しているという厳しい現実もあると高橋さんは言います。
「2017年に児童福祉法が改正されてから2021年までは特別養子縁組の成立件数は上昇傾向でした。2014年は成立件数が513件だったのが、2019年は最高件数の711件に、2020年は693件、2021年も683件と700件に迫る勢いです。
しかし、2022年には580件と急速に落ち込んでしまいます(※)。原因の特定はできていませんが、コロナ禍で養子縁組の説明会や研修が見合わせになったり、子どもと養親希望者のマッチングや面会が進まなかったり等の理由はあるかもしれません。
また、2020年の民法改正で特別養子縁組ができる子どもの年齢が6歳未満から15歳未満までに引き上げられました。そのことで、養子縁組は急がなくてもいいという考えになり、特別養子縁組の成立を先送りされる方が増えた可能性もあります。
一方で、現在も乳児院で親との面会がない子どもは600人以上います。子どもには愛してくれる家族が必要という考えのもと、特に実親に復帰する見込みのない幼い子どもについては、児童相談所や家庭裁判所がしっかりと特別養子縁組を進めることが重要です」

※社会的養育の推進に向けて/こども家庭庁支援局家庭福祉課(P100)令和7年1月
─・─・─・─・
先進国の中では遅れていると言われてきた日本の養子縁組制度への取り組みですが、国が推進する制度で、法改正をきっかけに少しずつ改善されつつあることがわかりました。次回は、実際に養親となることを考えたときに、知っておきたいことについてお話を伺います。
取材・文/関口千鶴
●高橋恵里子PROFILE
2013年、日本財団にて「ハッピーゆりかごプロジェクト」(現:日本財団子どもたちに家庭をプロジェクト)を立ち上げる。生みの親と生活することが難しい子どもが、あたたかい家庭で暮らすことのできる特別養子縁組や里親制度を啓発するべく活動を行っている。
【関連リンク】
●子どもたちに家庭をプロジェクト/日本財団
●養子縁組について 子どもたちに家庭をプロジェクト/日本財団
●里親制度について 子どもたちに家庭をプロジェクト/日本財団

関口 千鶴
大学卒業後、出版社にて編集者として数多くの雑誌・書籍を手掛ける。その後、親子カフェ経営を経て、独学で保育士免許を取得。現在は、幼児教育・子育て支援・絵本などを中心としたフリーランスの編集者・ライターとして活動中。 ●Instagram chise_kanon
大学卒業後、出版社にて編集者として数多くの雑誌・書籍を手掛ける。その後、親子カフェ経営を経て、独学で保育士免許を取得。現在は、幼児教育・子育て支援・絵本などを中心としたフリーランスの編集者・ライターとして活動中。 ●Instagram chise_kanon






























































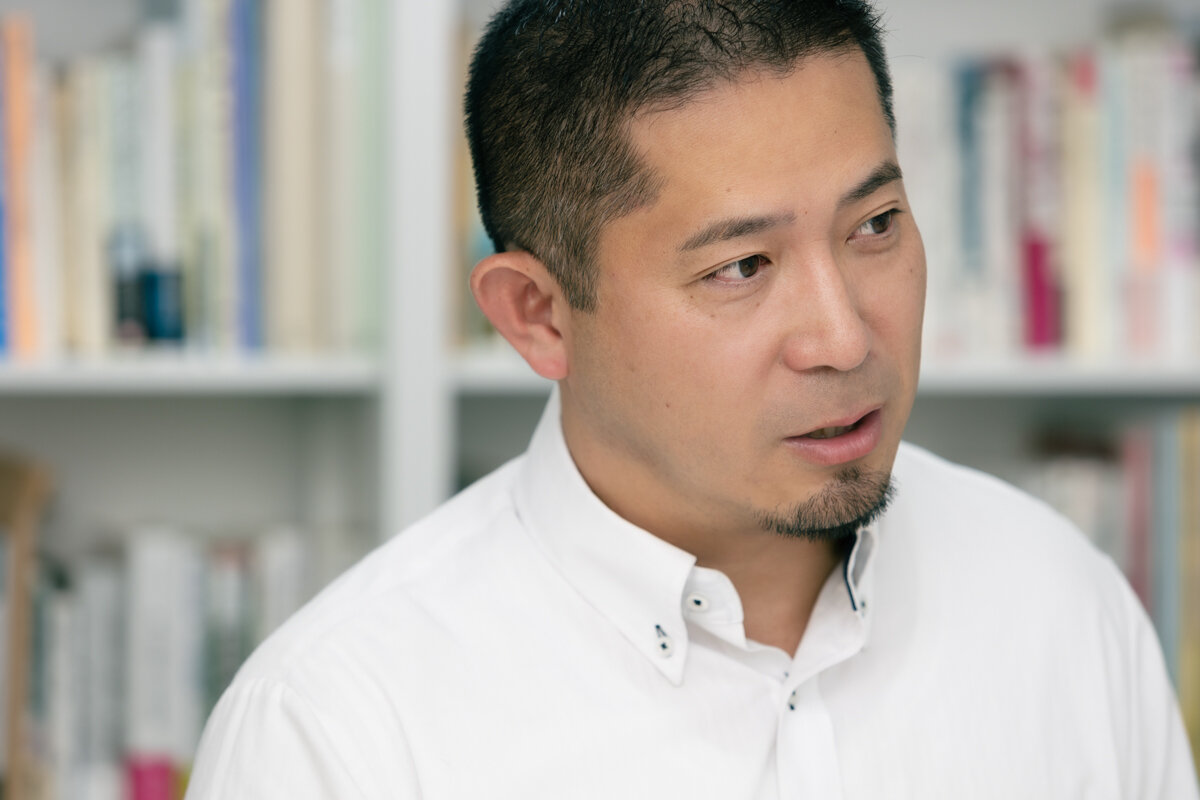








































高橋 恵里子
上智大学卒、ニューヨーク州立大学修士課程修了。1997年より日本財団で海外の障害者支援や国内助成事業に携わる。 2013年、日本財団にて「ハッピーゆりかごプロジェクト」(現:日本財団子どもたちに家庭をプロジェクト)を立ち上げる。生みの親と生活することが難しい子どもが、あたたかい家庭で暮らすことのできる特別養子縁組や里親制度を啓発するべく活動を行っている。 ●子どもたちに家庭をプロジェクト/日本財団 ●養子縁組について 子どもたちに家庭をプロジェクト/日本財団 ●里親制度について 子どもたちに家庭をプロジェクト/日本財団
上智大学卒、ニューヨーク州立大学修士課程修了。1997年より日本財団で海外の障害者支援や国内助成事業に携わる。 2013年、日本財団にて「ハッピーゆりかごプロジェクト」(現:日本財団子どもたちに家庭をプロジェクト)を立ち上げる。生みの親と生活することが難しい子どもが、あたたかい家庭で暮らすことのできる特別養子縁組や里親制度を啓発するべく活動を行っている。 ●子どもたちに家庭をプロジェクト/日本財団 ●養子縁組について 子どもたちに家庭をプロジェクト/日本財団 ●里親制度について 子どもたちに家庭をプロジェクト/日本財団