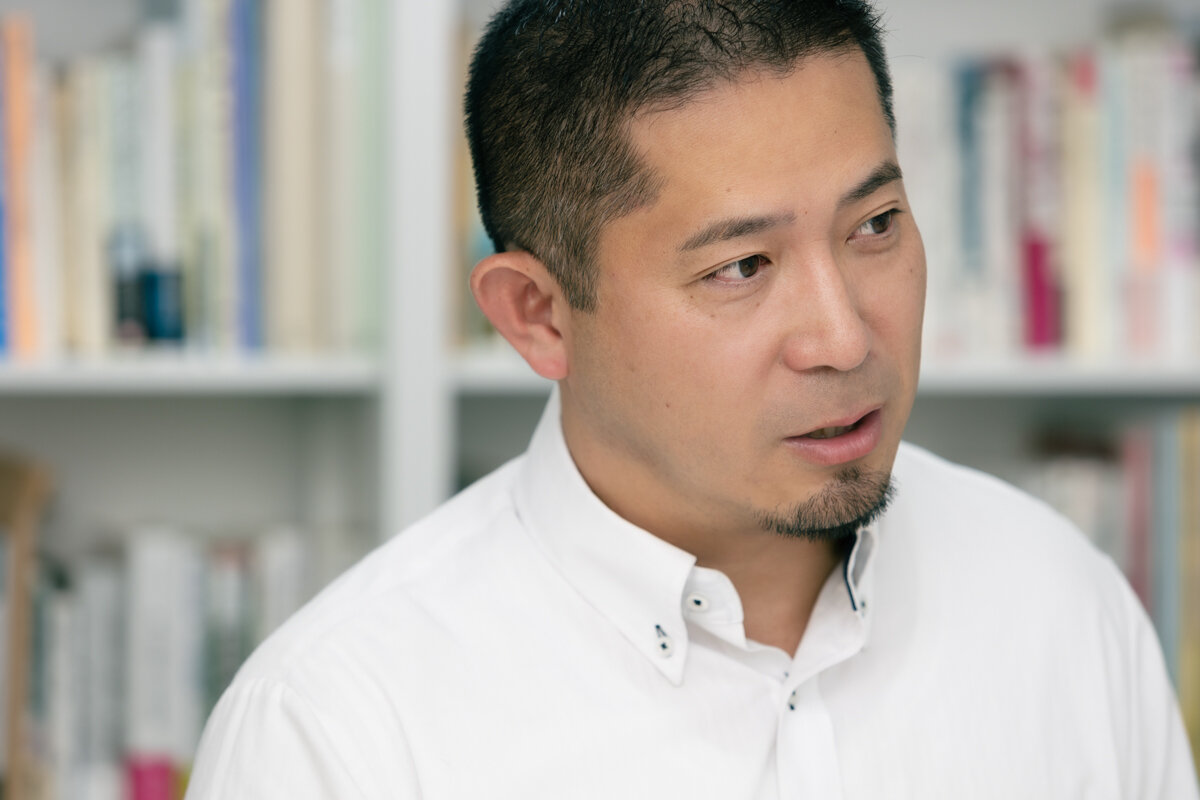長期休み明けに「子どもの行き渋り」発生! 〔精神科医〕が教える親の寄り添い方とは? 「質問攻め」が絶対にNGな理由
精神科医さわ先生に聞く、「ちょうどいい親子の距離感」 #1 (3/4) 1ページ目に戻る
2025.08.30
「学校に行きたくない」にも段階がある
では、子どもが実際に「学校に行きたくない」と言ったとき、どう対応すればいいのでしょうか?
私がクリニックの診察でよく伝えているのは、大前提として「命をかけて学校に行く必要はない」ということです。そのうえで、親が判断の参考にできるのは子どもの反応です。
朝は「行きたくない」と言っていたけれど、帰ってきたときに「行ってよかった!」と笑顔を見せるようなら、その日は背中を押して正解だったと言えるでしょう。
一方で、「やっぱり行かなきゃよかった……」「しんどかった」「なんで、学校に行けって言ったの?」といった反応や、朝よりも顔色が悪くなっていた場合は、その日は無理をさせるタイミングではなかったということです。
さらに、「学校に行きたくない」という気持ちにも段階があります。たとえば、登校しようとすると手が震えてしまうような場合には、無理に背中を押すのは避けてください。
長期休暇から学校生活に切り替えるまでの時間は、子どもによってさまざまです。1週間で日常生活に戻る子もいれば、1ヵ月かけて少しずつ慣れていく子もいます。
「みんなと一緒にスタートできるはず」と親が期待してしまう気持ちはわかりますが、大事なのは無理をさせすぎないことです。

「行くか」「行かない」かで決めない
また、子どもに行き渋りがあるとき、親はつい「行くか」「行かない」かと白黒はっきりさせたくなってしまいます。でも、選択肢はそれだけではありません。
・少し遅刻していく
・午後からだけ行く
・給食だけ食べにいく
「今日は校門まで行ってみようか」という提案でもいいんです。子どもができそうなことの幅を持たせてあげられるかどうか。このように選択肢を持たせることで、子どもは一歩を踏み出しやすくなります。
















![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)