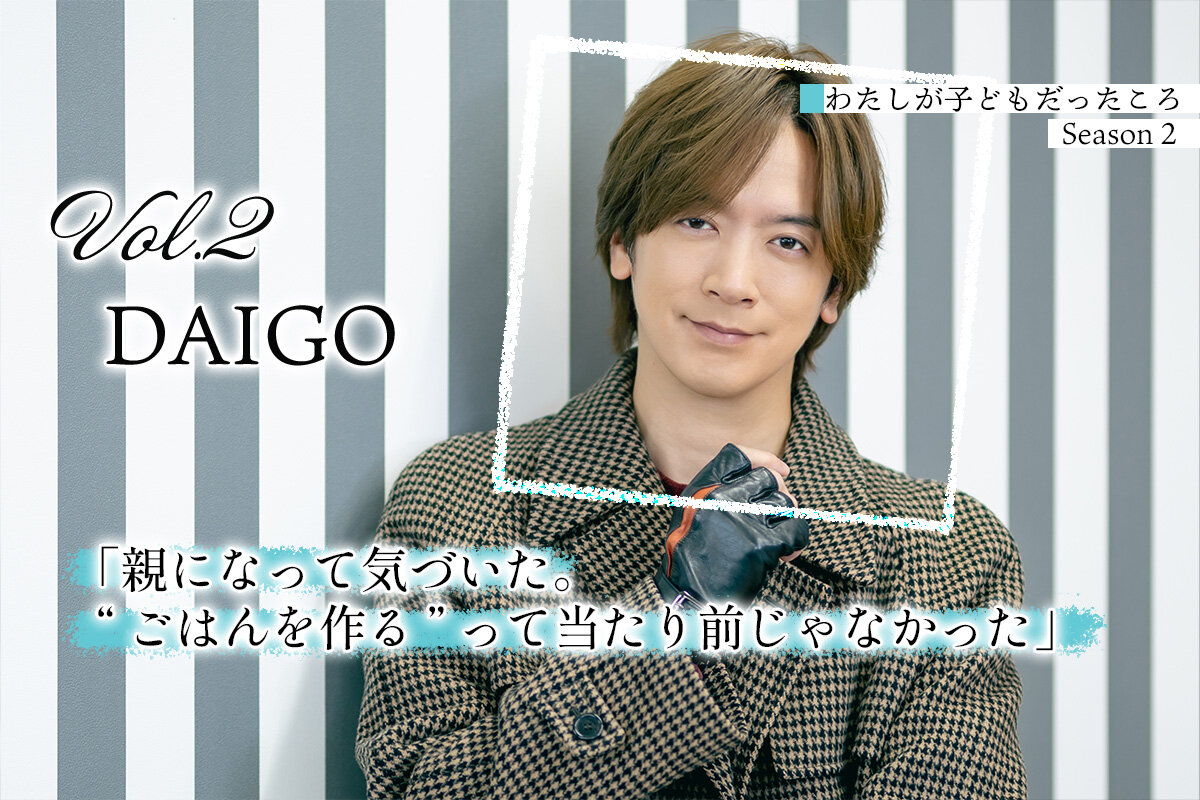学童野球・少年野球の「保護者の負担」 現役ママがリアルに告白
後編 「学童野球はめんどくさい」? 親子で楽しむママが伝える「めんどくささ」のリアル
2024.06.17

10歳の男の子と4歳の女の子の2人きょうだいを育てている、エニママライターのえみです。
本記事のテーマは前回に引き続き、学童野球のリアルについてです。今回は「小学生の野球チームはめんどくさい」というイメージについて、実際に長男が学童野球チームに入部して1年になる私の経験や考えをお話しします。
※AnyMaMa(エニママ):ママのはたらき方や選択肢を広げるための支援サービス

「少年野球(※)」と検索すると、関連語として「めんどくさい」「ストレス」といったネガティブなキーワードが表示されることがあります(なかには「家庭崩壊」なんてキーワードも……一体なにがあったのでしょうか……)。子どもに野球をやらせることに不安を感じているパパ・ママが多いことの表れかもしれません。
今回はこの、世のパパ・ママたちの「小学生の野球はめんどくさい/ストレスになる」という不安について、息子が学童野球を続けて1年経った私が感じることをお話ししたいと思います。
※前編でお伝えしたとおり、小学生の軟式野球の正式名称は「学童野球」ですが、検索する際には「少年野球」として検索する方が多く、ここではこの表現を使っています。
小学生の野球がめんどくさいかどうかにはチーム選びが大きく影響する
「少年野球はめんどくさい」「保護者の負担が重い」と言われる理由の主なものとして、「お当番制」「保護者間の人間関係」があるようです。
私が複数の学童野球を比較してチーム選びをした経験から、お当番制の有無や負担感、保護者間の人間関係は、チームによって大きく異なると言えます。前回の記事で「小学生の野球を楽しめるかどうかは、所属するチーム次第」だという私の意見について述べましたが、めんどくさくなる/ストレスになるかどうかにも、チーム選びが大いに関係すると思います。
【前回記事】子どもが「学童野球」に入部したママの「正しいチーム選び」リアル体験談





















![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)