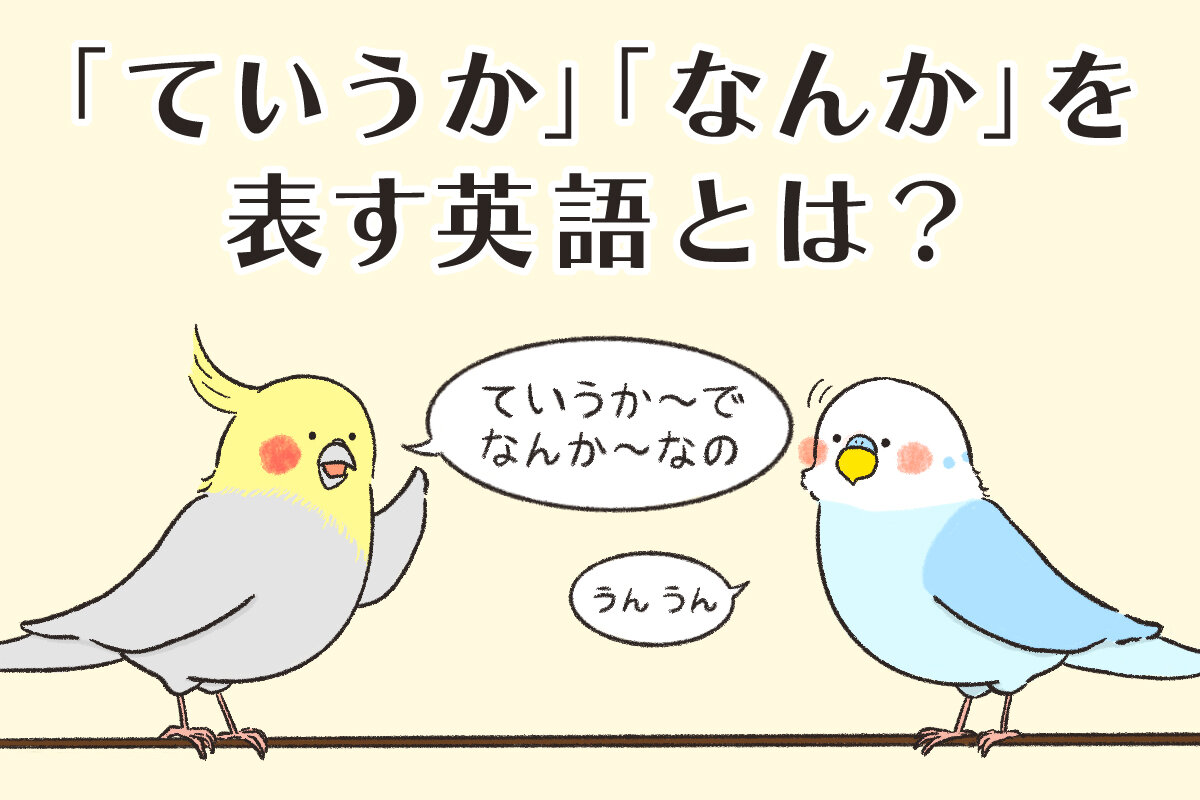

【中学受験が過熱している。受験者数は過去最多で、首都圏では5人に1人、クラスの半数以上が「中受」という地域も。受験市場の拡大・学歴別の生涯賃金・就職氷河期世代の保護者たちなど、中学受験が過熱する現状と背景について解説した第1回に続き、第2回では教員たちのリアルな声を、「年収443万円」の著者でジャーナリストの小林美希氏が取材する】
「本当に”中受”しなくて良かったのか」割り切れない思い
「息子も一時は受験すると意気込んでいました。4年生の途中から受験塾に入ったのですが、既に塾の子たちは5年生の勉強もしていて目が点という状態。ついていくのは大変。先取りして難しい勉強をする意味も見いだせず、結局やめました」
都内に住む大野真紀さん(仮名、40代)は中学受験をしないと決めたが、子どもが小学6年生の3学期をむかえ、周囲の受験色が強まるこの時期、「本当に“中受”しなくて良かったのか」という割り切れない思いが残る。
卒業式に向けた準備のため、子どもが既に卒業している先輩ママ友に連絡をとると中学受験の話題になる。「うちは、受験しないともう決めたから」と言うと「ええー!信じられない。大丈夫?今からでもどこか受けなよ。高校受験なんて大変だよ。大学受験も大変だよ」とまくしたてられてしまった。
息子の通う小学校では約半数が“中受組”となり、新学期が始まる1月は入試対策のラストスパートをかけるため登校しない児童が増える。がらんとした教室のなかでは、受験せずいつもどおり登校する児童らにとって、多少なりとも“取り残されている感”が漂う。
6年生3学期に頭を悩ませる教員

入試が始まる1~2月は、教員の心境も複雑だ。
都内の公立小学校で図工の教員をしていた佐藤恵子さん(仮名、20代)は、中学受験のための内申点をつけるのに神経を使った。
小学校の通知表は3段階評価だが、生徒が受験する中学校によっては、提出用に成績を5段階に付け直さなければならないケースもある。再評価した成績が、その子の人生を決めてしまうかもしれないというプレッシャーがかかった。
1~2月は登校せずに、受験に挑む児童が少なくない。6年生の3学期の成績をつけることも苦心する。
受験せず登校している児童と、受験で休んでいる児童とでは授業で制作する作品数に違いが出てしまう。恵子さんは、3学期の提出物がないことで減点はせず、それまでの授業態度や制作物を考慮したうえで平均点を出し、成績をつけるようにしていた。
しかし、卒業前に6年生の集大成として制作する作品も、長期間休む児童は完成できないため、寂しさが残る。
「教員の立場で考えれば『受験で登校しないなんて嫌だ』とは思います。しかし、荒れている学校で学級崩壊していたため、ガヤガヤして常に落ち着かない状況でした。ですから、そこから離れてストレスなく受験したい、将来のために頑張りたいという、保護者や児童の気持ちは理解できますし、受験することは止められません」
「学校の宿題を出さないで」受験勉強に追われる児童たち
都内の公立小学校の教員の谷口加奈さん(仮名、30代)も、6年生を担任すると中学受験する児童への対応でジレンマを抱えた。
「小学校高学年では、5年生ごろから心が大人に近づいてきて、活動が男女で分かれることが増えていくものの、6年生の終わりごろにはまた、性別で分け隔てなく仲良くなるという流れがあるものです。しかし、卒業に向けてクラスがまとまってくるそのとき、1月は受験勉強の追い込み、2月は受験本番でクラスに仲間がいなくなるのです」
受験生が学校に登校せずに塾で入試のために追い込みをかけている1月、給食が大量に余ってしまうため、給食を止めるかどうか確認していくのも担任の仕事だ。そのうえ、受験しない児童からは「なんで来ないの」と不満の声も。その子どもたちのケアもしなければならない。

前述の恵子さんと同様に、3学期の成績をつけるのは一苦労。
受験のために登校せず、提出物を出せない児童もいる。学校に来て一生懸命にやった子と同じにはできない。通知表はテストの点数だけではつけられず、授業態度やノートのとり方なども考慮される。受験のために登校しない児童の保護者には、あらかじめ成績のつけ方を説明するようにしている。
荒れていることで有名な地域の小学校だが、約1割が中学受験をする。公立中学も荒れている、という噂を聞きつけた保護者が、6年生の後半に慌てて受験を決めるケースもある。
加奈さんの知る限り、多くの子は「受験してみたいとは思ったけど、こんなに勉強しなければならないとは思わなかった」という様子。電車で20分もかけて塾に通う子もいた。
受験する児童は週4~5日塾に通っている。塾の宿題が多すぎて、学校の宿題をする余裕がない。そのため、親から学校の宿題を出さないでという要望が来ることもある。
毎朝、眠そうに登校する子が多く、受験する子にとって学校は「息抜き」や「ストレス発散」の場となる。ストレスから喧嘩になってしまったり、友達の物を隠したり、スマホをもつ児童らが「LINEで悪口を書かれた」と、もめることが絶えず起こる。
義務教育課程の小学5~6年生を受験勉強に費やす子どもたちを見ていると、「この時期は二度とこないのに」と思う場面は少なくない。
運動会や学習発表会で使うための制作物を見て、加奈さんは「親がやっているな」と思うことがある。
夏休みの読書感想文もそうだ。調べると、学校の宿題の模範例がメルカリで売られていて、それを買って書き写したというケースまであった。加奈さんは、「塾で忙しいからといって大人がやってしまったら意味がない」と肩を落とす。
受験する・しないに関わらず「メンタルのケア」が重要
通塾や宿題で23~0時ごろまで勉強するため、睡眠時間が6時間程度の子もいる。成長期なのにと心配になる。寝不足で食欲をなくす子もいる。
「もう頑張らなくていいよ、受験しなくていいよ」と言ってあげたいが、そうはいかない。
塾は先取りして勉強を終わらせるうえ難易度の高い問題で訓練するため、学校の教員にとっては授業がやりにくくなる。もともと算数は学力別にグループ分けした少人数制にして教えているが、塾で成績がトップクラスだと物足りなくなってしまうため、授業中に手持ち無沙汰にならないように難しい応用問題を多く用意しておく。
6年生の後半、受験しない児童は「中学でどんな部活に入ろうか」と楽しそうだが、受験する児童は何ヵ月も前から「落ちたらどうしよう」「失敗したらどうしよう」という不安とプレッシャーに押しつぶされそうになっており、メンタルが弱っている児童も多い。「これほど塾にお金がかかっている」と、親から大きな期待とプレッシャーを受けているケースもある。
子どもたちが「家では自分の気持ちを出さず、学校で不安定になっている」と見ている加奈さんは、受験直前には必ずこう言うようにしている。
「受験で合格しても不合格でも、頑張った過程は無駄にはならない。人生終わったと思うな!」
不合格だったと、わんわん泣く子もいる。落ちた後は数日間、学校に来ることができない子もいる。
一方で、途中で受験をやめた児童も何人かいる。「あんなに荒れていたのに穏やかになって、すっごく明るくなるんです」。「緊張する気持ちを家で言えたら。親が『受験勉強が辛いならやめていい』と言ってくれる環境ならいいのに」と切実に思う。
「家でリラックスできるから、学校で頑張ることができると思うのです。家で愚痴や弱音を言えないと、子どもは息が詰まる。公立か私立かというより、進学先がどこであっても、『嫌なこと・辛いこと』があったら子どもが親に話せるよう、家庭は構えていてほしい」
加奈さんが指摘するように、子どもたちにとっては勉強だけでなく、メンタル面におけるケアも重要だ。
受験をするしないに関わらず、どのような進路であっても、子どもたちが精神的により良く成長できるよう支えることが、保護者や教師に求められている。続く第3回では、学校関係者に中学高校の現状や子どもたちのメンタルの変化について取材、真のエリート教育とは何かを考察する。
【『中学受験する・しない? 親の悩み・子どもの進路を考える』連載は全4回。第1回では「中学受験ブームとその背景」を解説。第2・3回では「中学受験と学校の現状」を教師・学校関係者に取材、第4回では、「中学受験とそれ以外の進路、子どもの人生を豊かにする選択」について深掘りします】










![「卒園おめでとう」を伝える絵本3選! 門出を祝うプレゼントにぴったりな名作[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/879/large/fe3c9db7-2339-4abc-a2cd-c276cc46fa59.jpg?1772501924)





































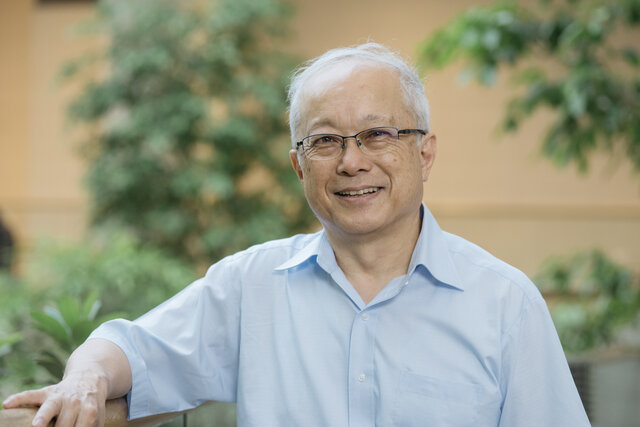


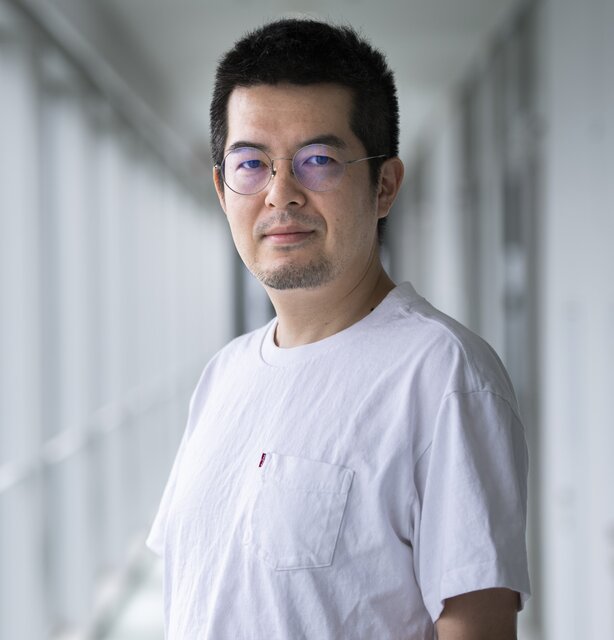





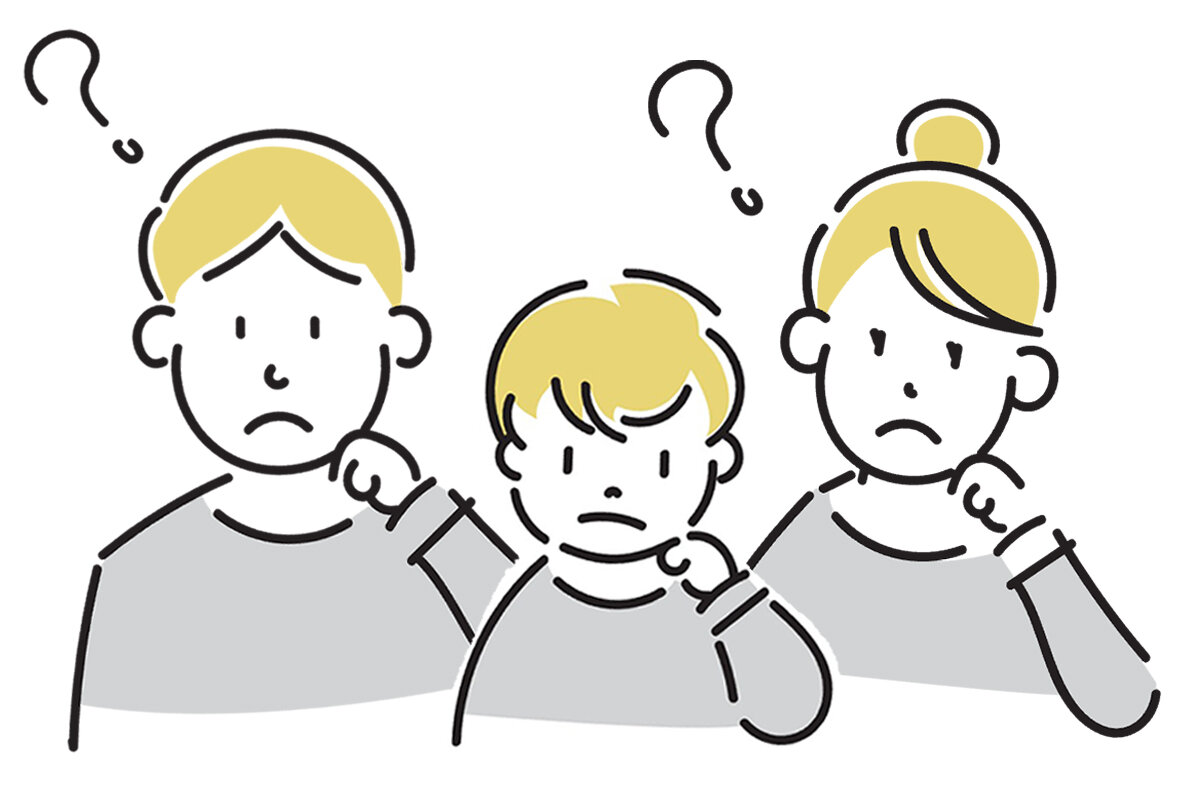




















































小林 美希
1975年茨城県生まれ。水戸第一高校、神戸大学法学部卒業後、株式新聞社、毎日新聞社『エコノミスト』編集部記者を経て、2007年よりフリーのジャーナリスト。就職氷河期の雇用、結婚、出産・育児と就業継続などの問題を中心に活躍。2013年、「「子供を産ませない社会」の構造とマタニティハラスメントに関する一連の報道」で貧困ジャーナリズム賞受賞。著書に『ルポ 正社員になりたい』(影書房、2007年、日本労働ペンクラブ賞受賞)、『ルポ 保育崩壊』『ルポ 看護の質』(岩波書店)、『ルポ 産ませない社会』(河出書房新社)、『ルポ 母子家庭』(筑摩書房)、『夫に死んでほしい妻たち』(朝日新聞出版)、『年収443万円 安すぎる国の絶望的な生活』(講談社)など多数。
1975年茨城県生まれ。水戸第一高校、神戸大学法学部卒業後、株式新聞社、毎日新聞社『エコノミスト』編集部記者を経て、2007年よりフリーのジャーナリスト。就職氷河期の雇用、結婚、出産・育児と就業継続などの問題を中心に活躍。2013年、「「子供を産ませない社会」の構造とマタニティハラスメントに関する一連の報道」で貧困ジャーナリズム賞受賞。著書に『ルポ 正社員になりたい』(影書房、2007年、日本労働ペンクラブ賞受賞)、『ルポ 保育崩壊』『ルポ 看護の質』(岩波書店)、『ルポ 産ませない社会』(河出書房新社)、『ルポ 母子家庭』(筑摩書房)、『夫に死んでほしい妻たち』(朝日新聞出版)、『年収443万円 安すぎる国の絶望的な生活』(講談社)など多数。