

日本社会の新しい課題として「体験格差」が話題になっています。「体験格差」とは「旅行やならいごと、休日に友達と一緒に遊ぶなど、学校外で行われる体験機会の格差」のことです。夏休みの海水浴やキャンプ、芸術鑑賞や自然体験などあらゆる「体験」の機会をさし、貧困や親自身の経験により格差が生じるともいわれており、たびたびメディアでも取り上げられている新しい社会問題です。今回のコクリコラボでは3回にわたり「体験格差」に対するリアルな声を特集します。
コクリコラボアンケート「AnyMaMa(エニママ)」登録者およびコクリコメルマガ会員を対象に 2024年3月26日~4月8日インターネット上で実施。有効回答数は122件。
※基本的にアンケート回答の原文をそのまま記載しています。ただし文字数の都合上、一部抜粋や主旨を損なわない範囲の要約・編集を行っている箇所があります。(明らかな誤字等は修正のうえ記載)
子どもに十分な体験をさせていると答えた親が過半数

まずは子育て中の親に「体験格差」の定義について説明した上で「我が子に十分な体験をさせられていると思うか」を聞きました。「そう思う」「ややそう思う」を合わせた約6割の親が「体験させてあげられている」と考えていることがわかりました。
それでは、子どもの体験のためにふどんなことをしているのでしょう?











![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)





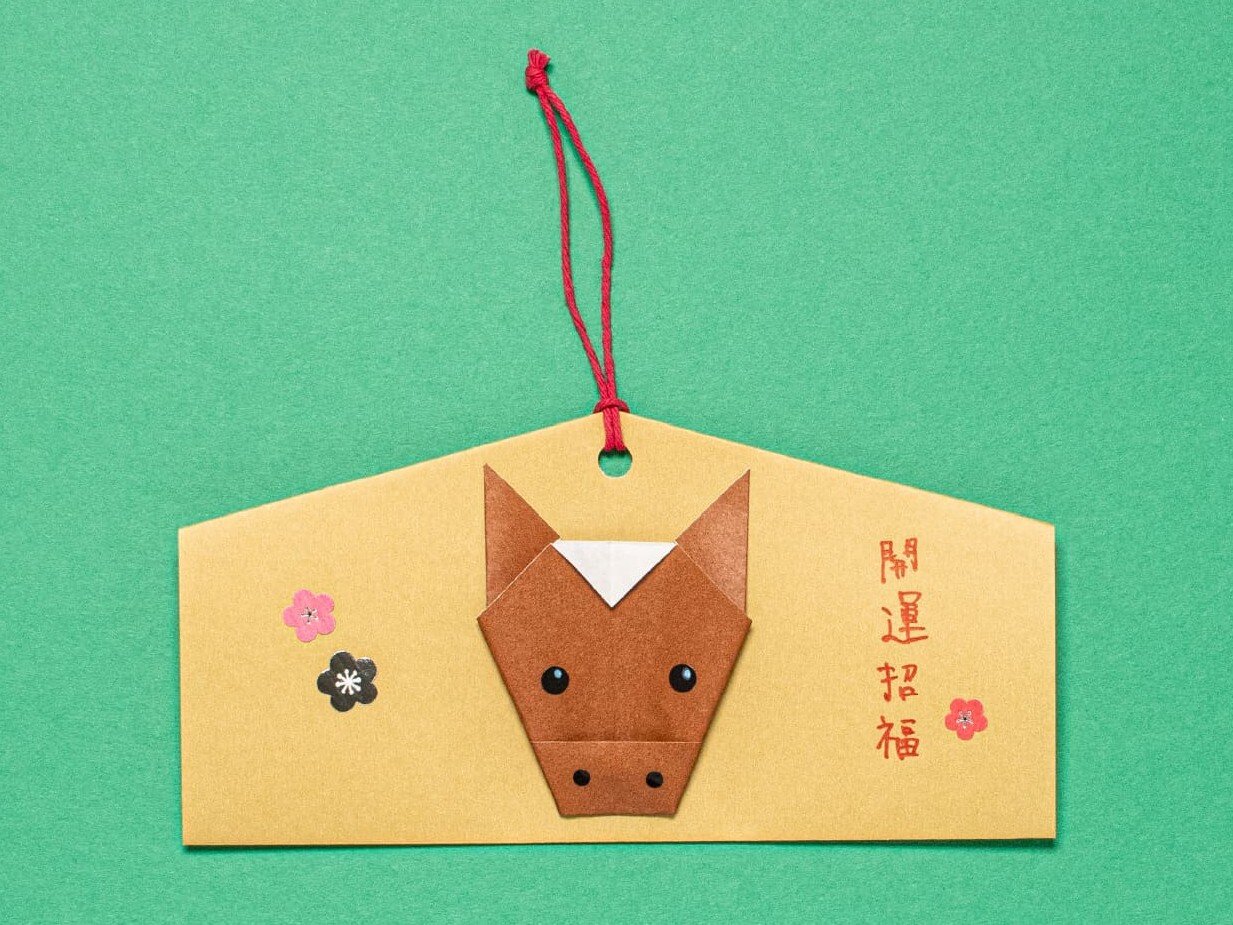



![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)




















































































