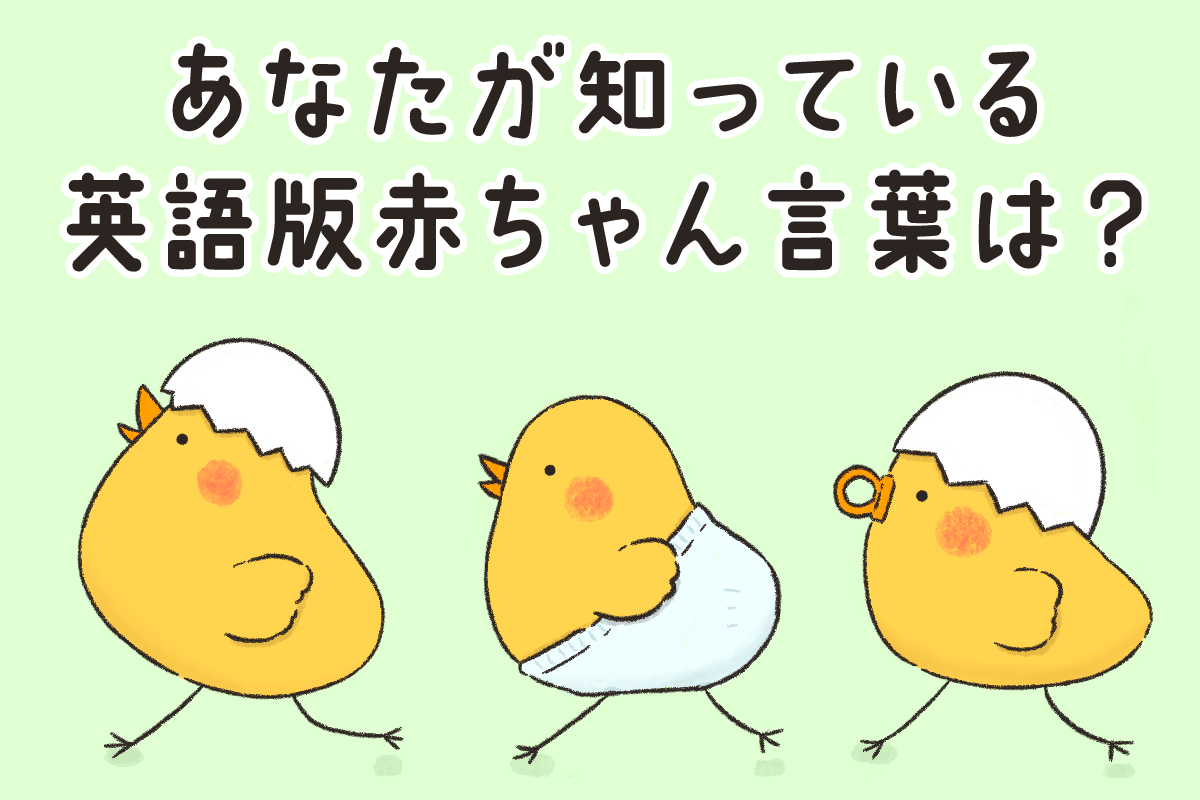発達障害の特性のある子の“きょうだい児”への支援【後編 保護者や周りができること】〔言語聴覚士/社会福祉士〕が解説
#17 発達障害の特性のある子どもの「きょうだい児」の支援─後編~周りの見守りとサポート~ (3/4) 1ページ目に戻る
2025.09.08
言語聴覚士・社会福祉士:原 哲也
(3)周囲の「眼差し」からくるストレスに対処したい
きょうだい児は保育園や学校等で、発達障害の特性のある兄弟姉妹がいることで変な目で見られたりからかわれることがあります。
この問題に対処するには、保育園や学校等の関係者の適切なサポートが欠かせません。そのために保育園や学校等の関係者は発達障害について正しい知識を持ち、そのうえで集団における上記のような状況からきょうだい児を守ってほしいのです。
関係者に適切にサポートしてもらうために養育者ができることとして、関係者に養育者から見た「発達障害の特性のある子のよいところを具体的に伝える」ことがあります。例えば、赤ちゃんの世話を誰よりもしてくれる、ケーキを作るとき材料を1グラムも違わずキッチリ計るなど、養育者の目からみた「よいところ」を伝えましょう。
養育者の心からのことばを聞くことで、関係者自身が発達障害の特性のある子の存在をポジティブに受け止められること、また「この子にはこういういいところがある」と具体的なことが頭に入っているのは、「からかい」などに関係者が対処するとき、非常に有効だと思います。
(4)ストレスを発散したい
きょうだい児は発達障害の特性のある兄弟姉妹との生活の中で、過剰適応状態になり、ストレスをため込むことが多くあります。
このようなきょうだい児にとっては、一定時間、家族から離れること、そこで家族以外の人とつながりを持つことがとても大事です。
趣味、クラブ活動、地域のつながりなど、きょうだい児が望むように家庭外での時間や家庭外の人とのつながりを保証してあげたいです。
(5)将来への不安に対処したい
きょうだい児は、自分自身の恋愛や結婚、そして、親なき後のことなど、多くの不安を抱えています。無理もないことです。
きょうだい児の成長につれて、発達障害の特性のある兄弟姉妹の特性や将来の支援体制についてきちんと話をすることはとても大切です。
ただ、現在の生活に精いっぱいで、養育者自体、将来のことについては情報不足であることも多いと思います。きょうだい児の不安に応えるという意味からも、児童発達支援事業所や児童発達支援センターの専門職、自治体の福祉担当課、通院している病院の医療ソーシャルワーカーや「親の会」などに相談することで情報を得て、将来のことを考えておくことは大事です。
また、養育者がそう思うのであれば、「きょうだい児自身の人生をしっかり歩んでほしい」と伝えることもきょうだい児の支えになると思います。