

「中絶」をめぐりアメリカが揺れている。2022年6月24日に米連邦最高裁判所が「ロー対ウェイド判決」を覆し、米国では女性の中絶権利が合衆国憲法で保障されなくなった。
(※女性の中絶の権利が州ごとに変わり、性的暴行などが原因による妊娠でも中絶できない州が存在することになった)
一方、日本はどうなのか。服用することで妊娠を中断できる「経口中絶薬」の承認審査が進んでいるが、5月の国会で厚生労働省が「配偶者同意が必要」と見解を示し、批判が相次いだ。
「女性の自己決定権」を望む声が上がるなか、6月27日には、助産師や研究者らのグループが中絶の「配偶者同意」撤廃を求め、約8万2000人の署名を厚労省に提出した。
日本は、2016年に国連の女性差別撤廃委員会から「配偶者同意」撤廃の勧告を受けているが、これまで議論が進んでこなかった状況だ。「中絶」をタブー視する社会の意識もまだ根強く、意図しない妊娠を背景とした事件も絶えない。
この記事では、中絶の当事者研究をしている杵淵恵美子教授(駒沢女子大学)に、子育て環境に詳しいライターの髙崎順子氏が取材。実態と統計から「日本の中絶の今」を探る。
語られてこなかった「中絶」というタブー
中絶をめぐるニュースを、多く見聞きするようになった2022年。日本ではいまだタブー色が強い話題で、当事者にとってはつらい記憶が残るデリケートな体験であることから、これまで日常会話やメディアでも多く語られてきませんでした。
読者の方々にも、保健体育の授業で教わり言葉の意味は知っていても、実際にはどんなものなのかをはっきり「知っている」と言えない人は、多いのではないでしょうか。
中絶というと、「避妊をしないで妊娠をした、若い未婚女性が行うこと」とイメージされがちです。
ですが実際には、避妊ができない・していても失敗した結果だったり、既婚者やすでに子どものいる女性が「仕事や家族を考えて、今は産めない」「これ以上は育てられない」と決断することも多いのです。
法律や制度が十分ではない状況
語られ、知られる機会が少ないけれど、国内で年間14万件を超える中絶手術の事情や背景は、本当にさまざまです。
子育て中の方々にも、他人事ではありません。そして日本ではこの手術をめぐる法律や制度が十分ではなく、新生児遺棄などのいたましい事件に繫がっているとの指摘があります。
今の日本社会における中絶とは、どんな形をして、どんな特徴や課題があるのでしょう。
もし読者の方々が「妊娠を継続しない」との選択をすることになったら、どんな制度や方法があるのでしょうか。一緒に知っていくために、この先を読んでいただけたら幸いです。
「妊娠を中断する」手術ができるのは「母体保護法指定医」のいる施設のみ
中絶とは、医学的な処置で妊娠を中断することです。その方法や可能な期間は国によって違い、各国の法律で定められています。(参考:日本産婦人科医会の公式ウェブサイト「女性の健康Q&A」)
日本の場合は、『妊娠22週未満まで』と決められています。
方法は時期によって変わり、妊娠初期(12週未満)では器械的に子宮の内容を除去する外科的手術を、日帰りで行います。12週以降は少なくとも数日の入院期間があり、人工的に流産を起こす処置で妊娠を中断し、役所に死産届を提出します。
これらの手術は国内の産婦人科医院であればどこででも行えるものではなく、都道府県の医師会が指定する「母体保護法指定医」のいる施設でしかできません。
また、12週以降は入院が必要になるため、行える施設の数がより少なくなります。どちらの手術も健康保険の対象ではなく、費用は自己負担で、10万円程度から数十万円と幅広く異なります。
「配偶者同意」が求められる
結婚している人・事実婚関係にある人は、手術にあたって「配偶者同意」という、妊娠相手の同意書を求められます。
配偶者がいない・相手が分からない・性的暴行を受けた・DVがあった・相手が死亡もしくは失踪した……などの場合は、同意書なしで手術が受けられると、厚労省と医師会が確認しています。
ですが医療施設によっては、同意書なしには手術をしないところも。そのため手術できる施設が見つかるまで、女性たちが数件のクリニックをめぐるという事態も起きています。
そうこうするうちに、手術の可能な週数を過ぎてしまい、孤立出産や新生児遺棄に至るケースもあります。
薬での中絶、日本では承認待ち
手術は心身の負担が大きいため、初期の妊娠中断(9週まで)は「経口中絶薬」という薬のみで行う国もあります。妊娠が続くためのホルモンを抑える薬と、子宮の内容を体外に出すための薬の計2種類を飲む方法です。
この方法は多量出血のリスクがあるため、承認されている国には、医療者の目の前で服用・事後診断を条件にするところもあります。そのほか、医療機関から希望者の自宅に郵送し電話相談でフォローをするなどの運用もあります。
日本の厚労省も、個人入手で摂取する危険を注意喚起しています(厚労省 注意喚起ページ)。
日本では経口中絶薬を求める声が年々高まっており、2021年の年末、製造元のラインファーマ株式会社が、日本国内での製造・販売を厚労省に申請しました。
稽留流産や不育症などの理由で妊娠が中断した場合も、中絶手術と同じ処置が必要となるため、この薬の承認が望まれています。
年間14万件の手術を7200人の医師で行っている
日本の中絶手術は、医療機関から医師会を通し、国への報告が義務付けられています。その実態は、毎年国から「衛生行政報告例」という報告書の一部で公表されています。(※衛生行政報告例「6母体保護関係」)
最新のデータは2020年度、年間14万1433件の手術がありました。
最も手術が多い年齢層は20歳~24歳で、約3万5000件です。それ以降は25歳~29歳で約2万6500件、30歳~34歳で約2万6000件。35歳~44歳の年齢層では、合計3万9000件となっています。大半は、12週未満の妊娠初期での手術です。
ここ数年は毎年、手術件数が減っており、2016年から2020年の5年間で、手術数は約2万7000件少なくなりました。
コクリコ編集部が厚労省に問い合わせたところ、中絶を行える「母体保護法指定医」は、最新の2018年のデータで7213人。同じ年の常勤産婦人科医は1万1556人(日本産婦人科医会)なので、中絶手術を行える医師は「常勤産婦人科医の6割ほど」と考えられます。
中絶の背景にあるさまざまな理由
この手術を受ける女性たちには、どのような事情や理由があるのでしょう。中絶の当事者研究をしている、駒沢女子大学の杵淵恵美子(きねふち・えみこ)先生にお話を伺いました。
先生によると、中絶手術の背景は、一人一人さまざまに異なっています。暴行や無理強いで避妊できなかった、避妊に失敗した妊娠の他、子どもは欲しくとも経済・仕事・学業などの理由で今は子育てできない人、母体に危険があって妊娠が続けられないケース……など、多様です。
妊娠初期で手術を受けた女性たちの中では、「今、相手と結婚できない。一人では産んで育てられない」という理由も多く聞かれました。
まさか自分が妊娠するとは…
「日本は婚姻関係の外で生まれる『非嫡出子』の数が、とても少ない国です。一人で女性が子を産んで育てるのが難しい社会で、女性自身にもその認識があることが、この理由に表れていると思います」(杵淵先生)
先生がヒアリングをする中で多かった発言に、「まさか自分が妊娠すると思わなかった」というものがありました。
セックスをしたら妊娠する、と頭では知っていても、それが自分の体に起こることと、本当の意味で納得できていなかった。だから女性自身で避妊ができていなかった、と。
「日本は、女性が自分で主体的に使える避妊法が少なすぎます。そして、避妊法について情報を得られる機会も、女性がそれについて話し情報交換をする機会も少ないのです。そのため避妊が必要な場面では、男性のコンドーム使用や、科学的ではない方法に頼ることになってしまう。
女性たちが妊娠と避妊を自分ごとと思えない意識と、そこから継続できない妊娠に至る経緯には、このような背景があります」
「避妊」の話がしにくい社会
避妊の話をしにくい状況は、若い未婚女性だけではなく、既婚の女性たちにも共通しています。たとえばこの記事の担当編集者は40代で、子どもがいる既婚者ですが、友人たちと生理痛や不妊治療の話はしても、お互いの避妊法に触れることはないと言います。
なぜそうなってしまうのか。避妊について話すことで「自分には避妊が必要だ、つまりセックスをしている人間だ」と示してしまうことに、ためらいがあるのではないかと、杵淵先生は言います。
「結婚しているご夫婦であっても、それを認めるのに気後れしてしまう空気が、日本社会にはあります。その空気から、中学や高校の保健体育で学ぶ内容も、学校や教師により差が出てしまう。
そして性的な活動が活発になる20代以降や、出産した後にも、避妊について女性自身が考える姿勢を、取りにくくなっているのではないでしょうか」
避妊について話すことに戸惑いを覚えてしまう、社会の空気。それが意図しない妊娠と、中絶手術の背景にある──女性の健康問題として、もっと避妊の話をするべきだと、杵淵先生は言います。
そのような空気がある日本の社会で、中絶をめぐる制度や法律の仕組みはどうなっているのでしょうか。それは続く、後編の記事で見ていきましょう。
もし今、意図しない妊娠の最中にいる人、妊娠を続けるかどうかを迷っている人、子を産んで育てられないと分かっているがどうしていいか分からない人は、以下のリンクを見てみてください。全国の思いがけない妊娠の相談窓口を掲載しています。
一般社団法人 全国妊娠SOSネットワーク
https://zenninnet-sos.org/contact-list
杵淵恵美子(きねふち・えみこ)産婦人科臨床等で約10年間助産師として勤務後、北里大学看護学部で教育・研究の仕事に就く。その後、石川県立看護大学、神奈川県立保健福祉大学、武蔵野大学看護学部に勤務し、2018年より駒沢女子大学看護学部に勤務している。研究テーマは「女性の意思決定」「妊娠継続を希望しない女性のケア」。
髙崎順子(たかさき・じゅんこ)ライター。1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)などがある。得意分野は子育て環境。















































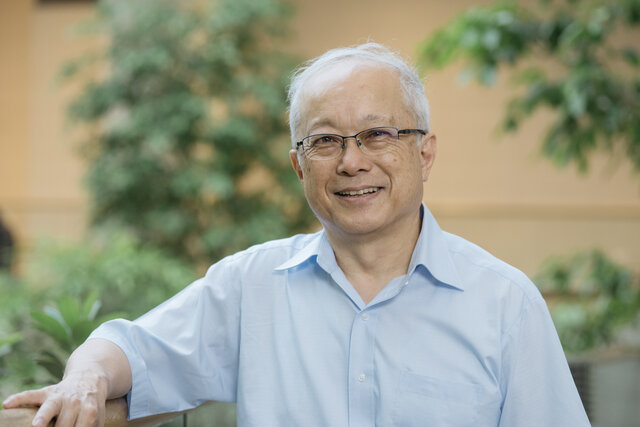


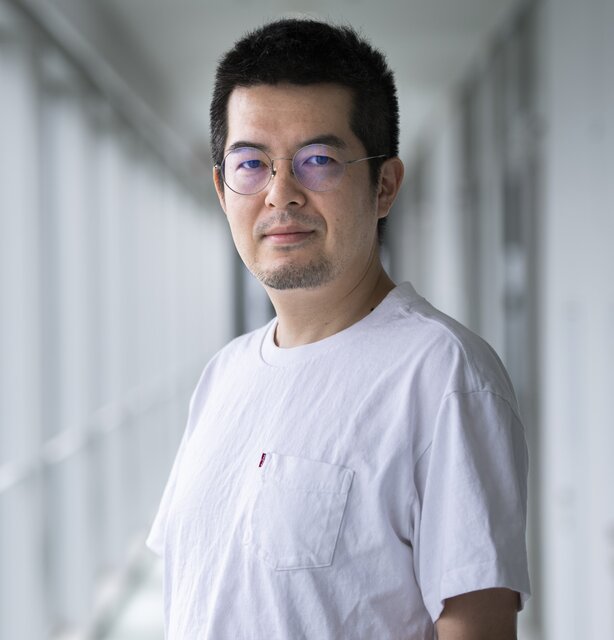



























































髙崎 順子
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)などがある。得意分野は子育て環境。
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)などがある。得意分野は子育て環境。