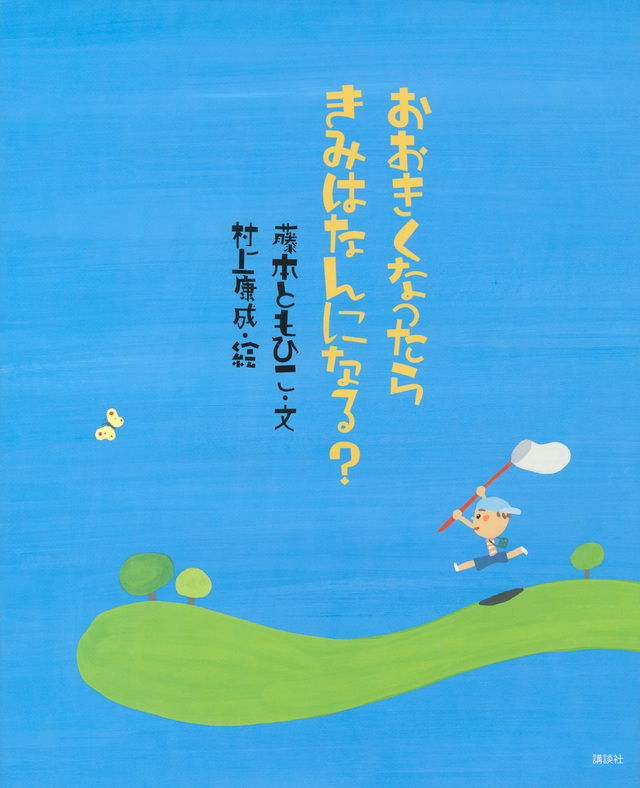【就学相談】子どもの「発達」気になる保護者のために 「支援級と普通級どう決まる?」「今すぐできる準備と段取り」 専門家がわかりやすく解説
2025.05.27
就学相談では、通常の学級(以下、通常級)、特別支援学級(以下、支援級)、特別支援学校など、就学先となりうる複数の選択肢を比較・検討します。
小学校入学を控えた年長児の保護者が参加するケースが多いですが、実際にはどの年齢の子どもや保護者も対象になります。診断の有無も関係ありません。
就学相談の基本的な流れ
就学相談の流れは、自治体や子どもの年齢によってさまざま。ここでは一般的な例を紹介します。

保護者による申し込み後、就学相談がスタート。多くの保護者は園や行政からの声かけがきっかけで参加を考え始めるのだそうです。
就学相談を担当する就学支援委員会は多くの場合、教育委員会の担当者や医師、公認心理師、大学教員などの専門職で構成されています。
就学後に転籍を検討する場合は、学校の担任が情報提供などで関わることもあります。

まず、保護者や子ども本人との面談・観察などが行われます。
就学支援委員会の担当者が子どもの在籍している園を訪問して集団生活の様子を見たり、子ども本人と関わったりしながら、特性や成長の度合い、必要な支援などを確認していきます。
併せて、保護者との面談を通して家庭での様子や保護者の希望などを聞き取ります。
「その子どもにとって最適な学びの場はどこか」を就学支援委員会内で検討した後、保護者と協議しながら考えのすり合わせを行い、最終的な就学先を決めていきます。
定員など、受け入れる学校側の状況が判断材料になる場合もあります。
就学相談に向けて、いますぐ準備できること

就学相談を受ける場合、家庭ではどのような準備が必要なのでしょうか。
「一連の流れを通じて大切にしたいのは、家庭内、特に夫婦間での継続的な話し合いです」と小関先生。
子どもに対する見方や将来の考え方が家族間で食い違う場合もありますが、実はそんなときこそ、一緒に就学相談の場に赴いてみることが有効。
専門家の意見がきっかけとなり、夫婦が同じ方向性で子育てできるようになることも、あるかもしれません。