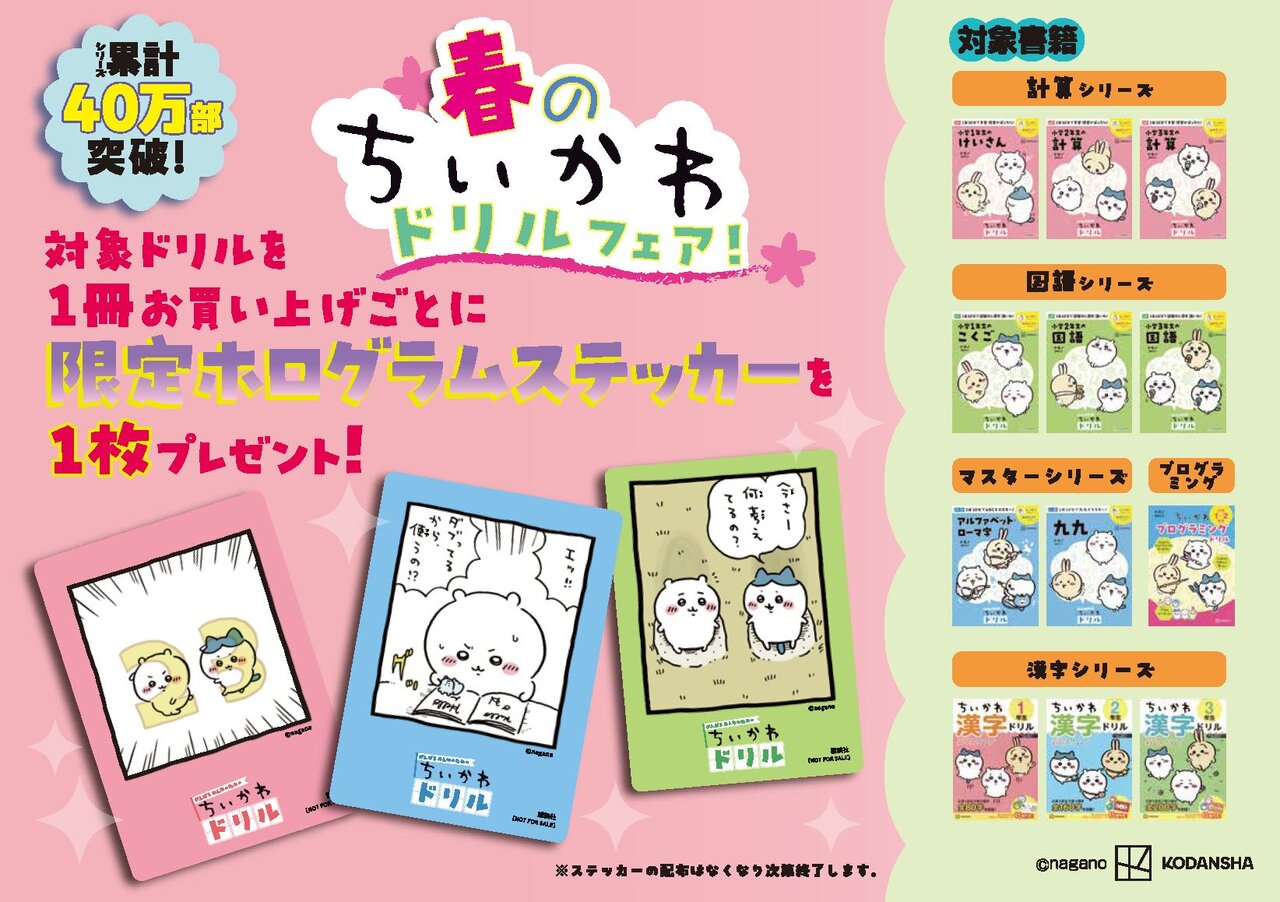生みの親と暮らせない子どもは約4万2000人 「養子縁組」の現在地 〔養子・里親の実態と仕組み〕
養子縁組の現在地 第1回~養子・里親の実態と仕組み~
2025.04.02
日本財団 公益事業部 子ども事業本部長:高橋 恵里子
日本財団が2013年に養子縁組・里親制度を支援するプロジェクトを発足させたのはメンバーの一人である高橋恵里子さんの素朴な疑問から。
「自分が子育てをしている中で、親に育ててもらえない子どもたちはどのような生活をしているのだろうと思ったことがきっかけで、そこから日本の養子縁組や里親制度について調べ始めました」
さらに、当時(2013年)、愛知県の児童相談所の元職員で、養子縁組支援に携わっていた児童福祉司・矢満田篤二(やまんた・とくじ)さんの講演会を聞いたことで、もっと養子縁組や里親制度への認知や理解を広げていかなければという強い思いにかられたそうです。
なかでも矢満田さんのこんな言葉が心にささったといいます。
「家庭を必要としている子どもはたくさんいる、一方で子どもを育てたいと思っている養親希望者も多くいる。
養子縁組が実現すれば、子どもにも養親にも、税金で子どもたちを養育している国や自治体にも良いことばかり。みんなハッピーになれるのに、なぜ今の日本では養子縁組がすすまないのか」
高橋さんは同年、プロジェクトを本格的にスタートさせました。
生みの親と暮らせない子どもは約4万2000人
現在、日本において何らかの理由で親と暮らすことができない社会的養護が必要な子どもの数は約4万2000人。その中で家庭養護を受けているのは約20%の8000人前後のみです(こども家庭庁調べ)。
※社会的養育の推進に向けて/こども家庭庁支援局家庭福祉課(P5) 令和7年1月
心身ともに幸せに育つために必要とされる家庭的な養護が受けられないまま、成人を迎える子どもが多くいるのが現実なのです。
「国連の子どもの代替養護に関する指針(※)では、政府はまず生みの親を支援して親子の分離を防ぐべき。しかし、それでも子どもが生みの親と暮らすことが難しい場合は養子縁組などで永続的に家庭を提供することを目標にするべきと掲げています。
家庭的養護のもとで育つのは子どもにとって重要なことであるのに、日本では生みの親が養育できない場合は乳児院や児童養護施設での養育が第一の選択肢となっているのです。その逆転現象をどうにか変えられないかと思い活動を続けてきました」
※国連総会採択決議 64/142. 児童の代替的養護に関する指針/2009年12月18日
日本は近隣国の香港 韓国より低い
アメリカやイギリスなど欧米諸国では、広く実施されている養子縁組・里親制度ですが、日本ではまだまだ少ないのが実情です。
2018年前後の厚生労働省調査(※)では、里親などに委託されている児童の割合は、オーストラリアが92.3%とトップで、ついでカナダ、アメリカが80%、イギリスでも70%を超えています。日本は調査対象国の10ヵ国中最下位で、24.3%に留まっています。

※社会的養育の推進に向けて/こども家庭庁支援局家庭福祉課(P71)令和7年1月
では、なぜ日本ではこのような低い割合となっているのでしょうか?
「日本では、実親の権利が強いことが影響していると思います。“子どもは親のもの”という考え方がまだ根強いので、『育てることはできないけれど親権は手放したくない』という親が多いのではないでしょうか。
しかし、親の権利があるように、子どもにも養育環境が整った家庭で幸せに安全に暮らす権利があります。当たり前である“子どもの権利”が長い間低く見られてきたという社会風潮があるのかもしれません。
それにともない、残念ながらどこか他人事であるという認識にもつながっているように思います」
受け入れ側の認識などの低さも改善すべき点だと高橋さんは続けます。