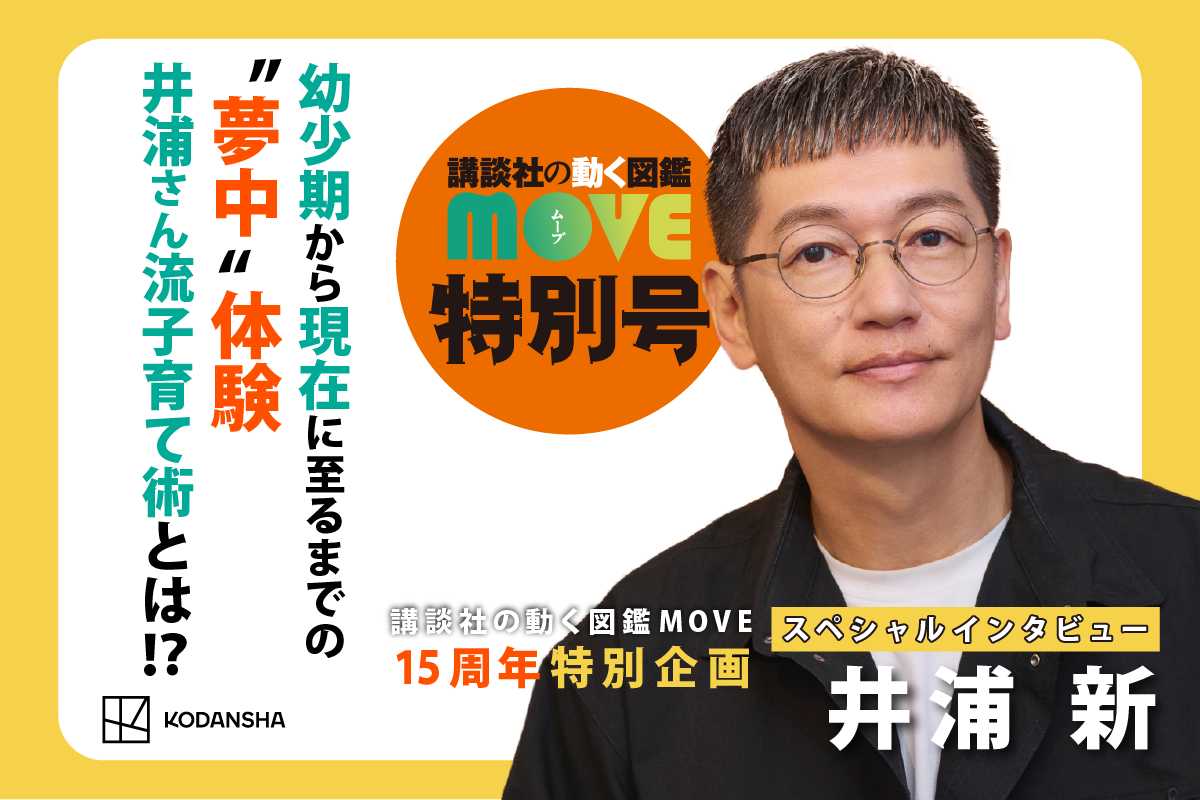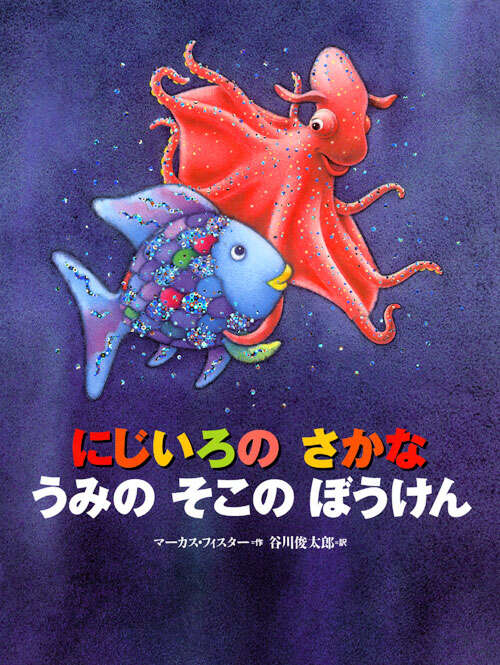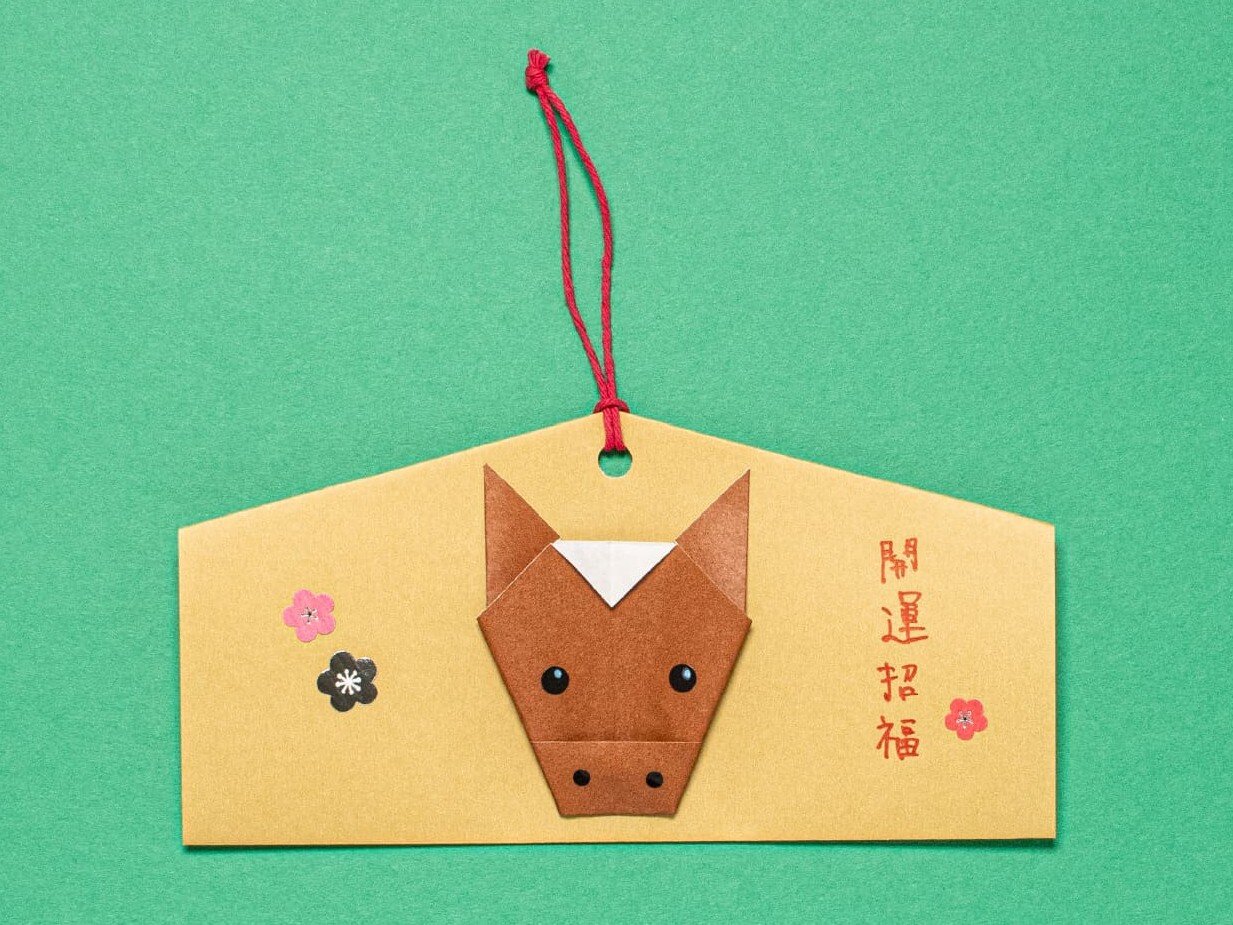さかなクンと一緒に考える【プラスチックごみ問題】深刻化する海洋ゴミの実態とは?
「プラギョミ漁」で“ギョギョギョッ!”な発見 『さかなクン探究隊』活動レポート第3弾 (4/4) 1ページ目に戻る
2024.11.21
マイクロプラスチックは2種類ある!

「プラギョミ漁」をしながら、海洋環境や海洋ごみの専門家である内田教授が、隊員たちにマイクロプラスチックについて解説してくださいました。
マイクロプラスチックとは、直径5ミリ以下の微細なプラスチックのことで、5ミリ以下のサイズになるまでの過程によって大きく2種類に分類されるそうです。生産された段階で5ミリ以下のプラスチック、つまり元々小さい状態で生産されたプラスチックのことを1次マイクロプラスチックと呼びます。例えば、歯磨き粉や洗顔料などのスクラブ剤やレジンペレット(プラスチック製品を製造するための原料として使われる微細なプラスチック粒。融解し、成型するとプラスチック製品となります)が挙げられます。
一方、2次マイクロプラスチックとは、ポリ袋やペットボトルなどのプラスチック製品が自然環境のなかで徐々に劣化、崩壊して小さなかけらとなったものを指します。そして、どちらのマイクロプラスチックも海へと流入することで、海洋環境や生物に深刻な悪影響をおよぼすことがわかっています。(参考:環境省「海洋ごみとマイクロプラスチックに 関する環境省の取り組み」)
プラギョミ漁を終えて
約1時間半の「プラギョミ漁」を終えた隊員たちに感想を聞いてみました。
「表面的にはきれいなビーチでも、少し砂を掘るとこんなにたくさんのマイクロプラスチックが埋もれているんだということに驚きました」
「わたしたちがくらす街から出たごみが、海の生態系に悪影響をおよぼしているから、海の生きものたちにごめんねっていう気持ちでごみを拾いました」
「ふだんからごみを少しでも減らす生活を意識したり、ちゃんと分別して適切な処理がされるように気をつけたいです」
「砂に埋もれていたり、海を漂っているマイクロプラスチックの回収はとてもじゃないけど無理! とってもとっても終わりがない。だから自然のなかに捨てられるのを防がないといけない。ポイ捨ては絶対禁止!」

体験型ワークショップ3回目の「プラギョミ漁」も、たくさんの刺激や視界の広がりを感じられる活動だったようです。次回の探究隊プログラムは11月中旬を予定。今回のビーチクリーン活動をふまえて、東京海洋大学の内田圭一教授の指導で、海洋ごみに関して学ぶ予定です。




















![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)