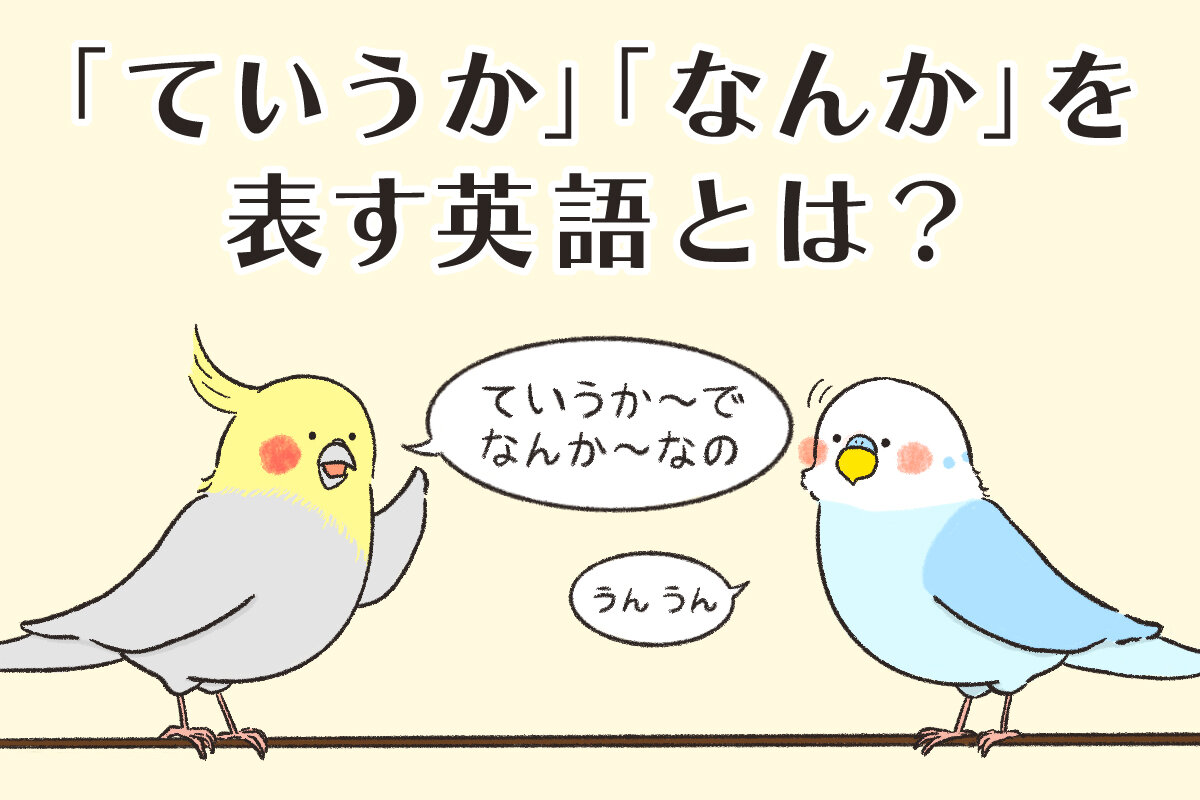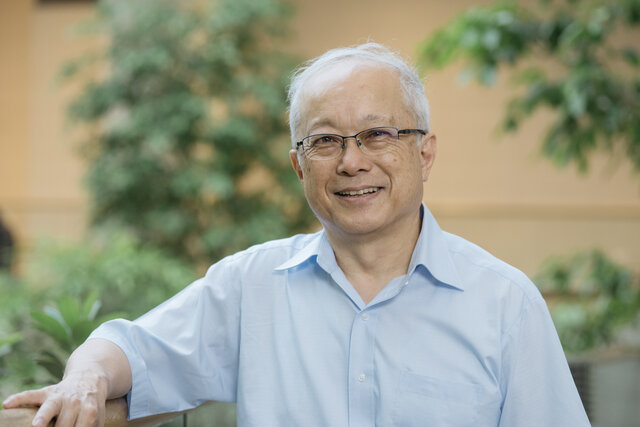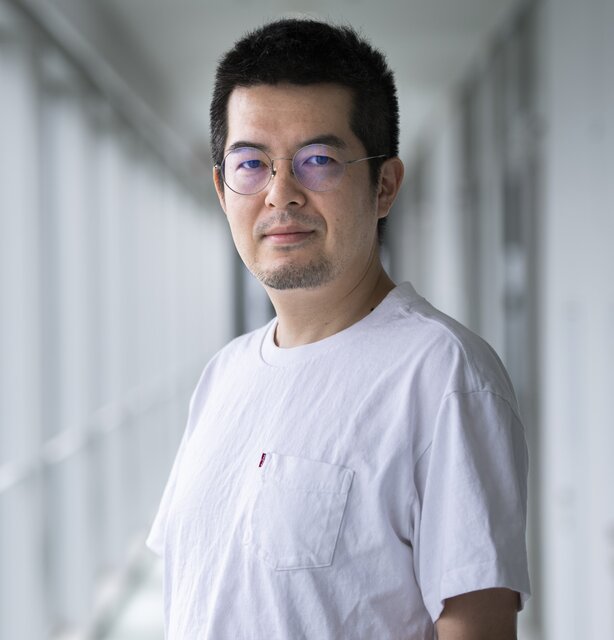![「卒園おめでとう」を伝える絵本3選! 門出を祝うプレゼントにぴったりな名作[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/879/large/fe3c9db7-2339-4abc-a2cd-c276cc46fa59.jpg?1772501924)

【働くママが脳出血に】リハビリに励む2児ママを襲った家族の死 悲しみの先に見えた希望
脳出血で緊急入院!【萩原はるな:ワンオペママの闘病記】#4 〜家族の逝去編〜
2022.05.19
ライター:萩原 はるな

ある日突然、脳出血で倒れてしまったフリーライターのママ(48歳)。パパと小学生の子ども2人を家に置いて、一人きりの入院生活がスタートしました。
ママの入院で、突如、ワンオペ育児に取り組むことになったパパの奮闘記(※1)はすでにお伝えしましたが、病に倒れたママ当人は、一体、どんな思いで過ごして来たのでしょうか。
※1=妻が脳出血!戦力外パパと2児の奮闘記(全6回)
社会復帰をめざしてリハビリに奮闘するママに、突然届いた訃報。激動の1日をレポートします。
訃報が届くも 身動きがとれないもどかしさ
病院の朝は早い。6時には電気がついてカーテンが開かれ、7時30分からの朝食に向けて、身支度を整えるのだ。
夜は9時に消灯になるものの、なかなかすんなりとは眠れない。入院患者の多くが何度も夜中に起きるようで、睡眠導入剤を飲んでいる人はけっこういた。
私も5時頃に一度目が覚めて、6時に起床を告げにくる看護師さんと朝の挨拶を交わし、7時になると夫のケータイにLINE電話。息子の笑顔を見てから支度を整え、7時半に朝食をとる。
すでに10月末、7月25日に倒れてから約3ヵ月が経ったころには、モーニングルーティンがすっかり確立していた。
そんなある朝、6時ころ目を覚めてスマホを見たところ、私の母からLINEが届いていた。
「早いな、なんだろう?」と開封してみたところ……。
「はるな、驚かないでね。父が、動脈瘤破裂で、急死しました。大好きなベッドの上で。救急車で自治医大に行き、でも、手をつくしてもらったよ。私が帰っていて、良かった」
えっ、何!? しばらく、目はメッセージを読んでいるものの頭では理解できず、固まってしまった。
「えっ、いつ? とても信じられない。お母さんは大丈夫?」と返したところ、「いい顔して、眠っている。幸せな人生だった証拠だね。救急車呼んだ時には、心肺停止していた。そばに居られて良かった」と返ってきた。
本当に、父は遠くに逝ってしまったのだ……!

病院の厚意で一時外出が決定!
7時半、いつものように朝食が運ばれてきたものの、まったく味がしない。すぐにでも実家にかけつけたいところだが、病院は完全にコロナシフトを組んでおり、かつては許されていたらしい一時帰宅や外泊はいっさい禁止になっていた。
父は以前も触れたとおり、脳卒中の大先輩。50代と60代の2度、脳梗塞で倒れている。父とは、リハビリ病院に転院してから、一度だけ電話で話していた。
「心配かけてごめん。手足はまだまだ思うように回復しないけれど、頭ははっきりしているよ」と言ったところ、「そうかそうか。それなら大丈夫だ。体はどんどん良くなるから」と、ほっとした様子だった。
いつも母を子どもたちの世話に駆り出してしまっていることを詫びたところ、「何を言ってるんだ、病気なんだから仕方がない。それよりも頑張れ」と励ましてくれたのだ。
私の入院中に79歳になった父。かつての「ザ・昭和の父」だった迫力はすっかりなくなり、母に頼りながらも楽しく暮らしている様子だった。
「年末には退院できるから、家族みんなで行くからね」、「おう、楽しみにしてるよ」というのが、父との最後の会話になってしまった。
ベッドで声を殺して号泣していたところ、「大丈夫?」と、同室の40代女性が声をかけてくれた。「ち、父が今朝、亡くなって」、「ええっ!? 早く看護師さんに言いなよ。なんとかしてもらえるかも!」。
その言葉に勇気をもらい、「父が亡くなって、お別れをしに行きたいんです」とダメもとで相談したところ、「難しいかもしれないけど、調整してみるからちょっと待ってくださいね」と看護師さん。泣き崩れる私の背中をさすりながら、「つらいね」と言ってくれ、余計に涙が止まらなくなってしまった。
しばらく待ったのちに、看護師長が部屋にやってきた。「自家用車で病院と実家のドアtoドア、屋内でもマスクは外さないこと」「病院に戻ったら、3日間個室で隔離」などを条件に、一時外出許可が降りたのだ!
「事情が事情だからということで、『特例』ということで」と看護師長。
翌朝9時に姉に迎えにきてもらい、夕方16時をめどに戻ってくることになった。

娘と息子に挟まれた長くて短い移動時間
翌朝、大きくて場所をとる車イスは置いて、杖で行くことにした。「車移動でどこにも行かないなら、大丈夫でしょう」と担当の理学療法士に言われたものの、3ヵ月ぶりの外の世界。正直ビビりながら、そろそろと姉の車に乗り込んだ。
「お母さ〜ん!」。病院の近くで待ち構えていた娘と息子が、後部席に乗り込んできた。
「あのね、この前野球でね」「お母さん大丈夫? 右手は動くようになった?」。右側に息子、左側に娘がピッタリくっついてきて、一斉に話しかけてくる。子どもたちに会うのも、3ヵ月ぶりなのだ。
病院から実家までの所要時間は、普段なら2時間弱。けれども新型コロナの感染状況が少し落ち着いてきた週末で、秋の行楽日和だったことから、高速道路は大渋滞していた。実家にたどり着いたときには、お昼前になっていた。
杖をつきながらゆっくりと玄関へ向かい、母に迎えられる。廊下を進んだ先に、父が眠る和室があった。
「すごく、いい顔してるでしょ」と母。髪を整え、一張羅のスーツを着て横たわった父は、本当に満足げだった。コロナで全然会えなかったけれど、どんどん認知症が進んでいたらしい父。
母は、「父が父でいられる、父として楽しく暮らせる、ギリギリのところに差しかかっていた気がする」と言う。母とその近くに住む姉は、近々介護が必要になると、覚悟していた。私とも折に触れ、「免許はいつ返納させようか」と、話していたのだ。
私が7月に倒れて以来、毎朝「はるなは大丈夫か」と母に聞き、「意識ははっきりして、リハビリをしてますよ」「そうか、それなら大丈夫だ」と同じやりとりを繰り返していたという。
誰の世話になることもなく、きれいに逝ってしまった父。
「最後まで、心配かけてごめんね」 私はしばらく、父のそばを離れることができなかった。