

日本では「経口中絶薬」の承認をめぐり議論が続いている。厚生労働省が5月17日の参院厚労委員会で「経口中絶薬に配偶者同意が必要」との見解を示したところ、「女性の自己決定権」をめぐって批判が相次いだ。
一方アメリカでは、6月24日に米連邦最高裁判所が「妊娠中絶は女性の権利」と認めた1973年の「ロー対ウェイド判決」を覆した。米大統領バイデン氏は「悲劇的な過ち」とコメントを発表。しかし早くもアメリカでは、一部の中絶クリニックの閉鎖が始まっている。
この問題は日本国内でも関心が高く、7月6日に日本産婦人科学会は「米国最高裁の「ロー対ウェイド」判決を覆す判断に抗議する」声明を発表した。
中絶は、女性の「性と生殖に関する健康と権利(SRHR:セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)」に大きく関わる問題だ。日本の中絶をめぐる状況について、前編に続き、中絶の当事者研究をしている杵淵恵美子教授(駒沢女子大学)に、子育て環境に詳しいライターの髙崎順子氏が取材した。
「配偶者同意」を求める日本
年間14万件行われている、日本の中絶手術。前編では、その当事者研究をしている駒沢女子大学・杵淵恵美子先生のお話から、女性が手術に至る事情や背景を述べました。
後編では、日本の中絶をめぐる法律や制度を紹介しながら、現状の特徴や問題点を見ていきます。
日本では、初期妊娠の中絶方法は手術のみで、都道府県医師会の指定する産婦人科施設で行うものであると、前編で触れました。そして手術の際には、妊娠した際の性行為の相手の同意を、書面で求められるのが原則です。
中絶手術は世界各国で行われていますが、この配偶者同意を求めるのは、実は世界203ヵ国のうち日本を含めた11ヵ国(※)しかありません。(出典:Center for repuroductive Right、生殖権利センター)
(※編集部注:11の国・地域は日本を含め、アラブ首長国連邦、イエメン、インドネシア、クウェート、サウジアラビア、シリア、赤道ギニア共和国、台湾、トルコ、モロッコ)
G7などの先進国のなかでは日本にしかなく、日本の生殖医療をめぐる一つの特徴と言われています。
なぜ、このような特徴があるのか。それは、中絶の仕組みを定める日本の法律のあり方を見るとわかると、杵淵先生は言います。
100年以上前の法律で決められている
「日本には刑法の『堕胎罪』(刑法第二十九章 堕胎の罪)があります。明治時代の、妊娠したら女性は出産しなければならないという考え方に基づいて、中絶そのものを罪とする法律です。
それでは女性の生命や健康が損なわれるということで、『国が定める理由があれば、中絶をしてもいい』としたのが、1948年の優生保護法と1996年の母体保護法(母体保護法)でした。
優生保護法には「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」という目的も含まれていましたが、その「優生」の考え方が削除され改正されて「母体保護法」になりました」
堕胎罪ができたのは明治40年(1907年)、今から115年前です。当時の妊娠出産の考え方に即して、中絶をした女性とそれを行った第三者(医療関係者を含む)を罰する内容で、妊娠の相手である男性への罰則を規定したものではありません。
母体保護法で配偶者の同意を求めるのは、この明治時代の法律の名残であると、杵淵先生は言います。
「明治時代の日本は家父長制で、男性が了解しないことを女性が行ってはいけない、という考え方で法律が作られていました。これは現代にはもう合わないので、国連からも是正が必要だと勧告されていますが、なかなか改正されません」
配偶者同意は必要なのか
この配偶者同意は、是非がたびたび議論され、ニュースにもなっています。杵淵先生のご意見は「不要と思います」と明快でした。
「女性が自分の体の中に起こっていることを、自分で決められなくてどうするのでしょう。
中絶手術に配偶者同意が必要だということは、自分の体のことを他人が決めるということ。それは、女性が一人の人間として、人格を認められていないのと同じではないでしょうか」
意図しない妊娠を背景とした痛ましい事件は、この配偶者同意も要因のひとつになっているのではないかと、先生は言います。
「結婚していない人は配偶者がいないので、本来は、同意は必要ないはずです。手術にあたり配偶者同意が必要ないケースは、厚労省も産婦人科医会も確認しています」
妊娠を中断できずに…
それでも「相手の同意書が手術には必要」とする医院は、残念ながら存在します。さまざまな事情で同意書を持参できない女性は途方に暮れたまま、中絶のできない時期まで妊娠が進んでしまう。
出産できない理由があるのに手術を受けられず、子が生まれてしまうケースは、後を絶ちません(※)。出産できないと知りながら、自分の体の中で妊娠が進んでしまうことは、どれだけ不安でしょう。
(※参考:「男性の同意」ないと中絶できない…相手からの連絡途絶えた未婚女性、公園のトイレで出産し遺棄(読売新聞))
「妊娠を継続できないと考える女性に対して、日本はとても冷たい社会と思います。もし誰かの中絶に反対する人がいるなら、出産でダメージを受ける女性と生まれた子の生育にも、責任をとることを考えてほしいです」
いまだ「中絶」は社会のタブー、知ることが困難な状況
日本の中絶は医療保険の対象外で、自己負担額が大きい、という課題もあります。前編で触れた経口中絶薬の承認と運用も、経済的・手続的に、手術より負担の少ない形で実現するかどうかはまだ、議論の最中です。
中絶をした女性の心理的なケアや、中絶後の避妊の情報提供など、改善すべき点はいくつもある。それでもこの件が、「以前より話題に出るようになったのは、良いこと」と、杵淵先生は感じています。
「以前は、中絶の研究をしているということも、言いにくい空気がありました。
私は助産師なのですが、助産師の仕事は妊娠して産む人に寄り添うことであり、中絶はそれと正反対の選択をする人、と見られていたからです。中絶のケアの教育も私の時代は皆無で、臨床で働きながら、先輩から実践で学ぶしかありませんでした」
今も、中絶の心理面のケアに関しては、国や学会のような公的機関による、明確で充実したガイドラインはありません。
中絶手術を担う「母体保護法指定医」の医療機関を検索できるような、国レベルの公式情報サイトもない。
(編集部注:世界保健機構WHOは2022年3月、中絶に関するケアをまとめた「アボーションケアガイドライン」の最新版を出している)
社会のタブー意識はまだ強く、さまざまな事情・背景を持つ女性たちが、不安を抱えて手探りで方法を探さねばならないのが現状です。国内でまだ製造販売が承認されていない経口中絶薬を、個人輸入しようとする人もいます。
必要な人がアクセスできるようになるために
みんなで話して、考えていくために。必要な人が必要な時に、中絶の医療と支援にアクセスできるようになるには、どうしたらいいでしょう。
杵淵先生は、「言葉に気をつけて、たくさん議論をすること」と考えています。
「中絶、という言葉自体には、否定的で強いイメージがあります。過去、中絶に反対する人々には、より強い『堕胎』という言葉をあえて使って、当事者を傷つけるやり方もありました。
女性の命と健康のためには大切なことですから、言葉の選び方から気をつけて、不要に苦しい思いをさせない配慮をしながら、話をしていきたいですね」
もし今、意図しない妊娠の最中にいる人、妊娠を続けるかどうかを迷っている人、子を産んで育てられないと分かっているがどうしていいか分からない人は、以下のリンクを見てみてください。全国の思いがけない妊娠の相談窓口を掲載しています。
一般社団法人 全国妊娠SOSネットワーク
https://zenninnet-sos.org/contact-list
杵淵恵美子(きねふち・えみこ)産婦人科臨床等で約10年間助産師として勤務後、北里大学看護学部で教育・研究の仕事に就く。その後、石川県立看護大学、神奈川県立保健福祉大学、武蔵野大学看護学部に勤務し、2018年より駒沢女子大学看護学部に勤務している。研究テーマは「女性の意思決定」「妊娠継続を希望しない女性のケア」。
髙崎順子(たかさき・じゅんこ)ライター。1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)などがある。得意分野は子育て環境。













































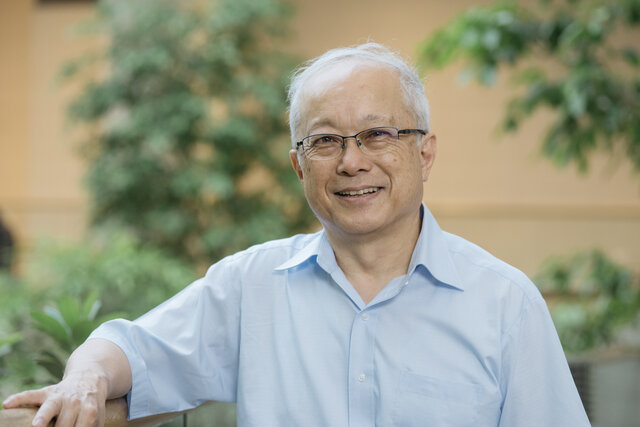


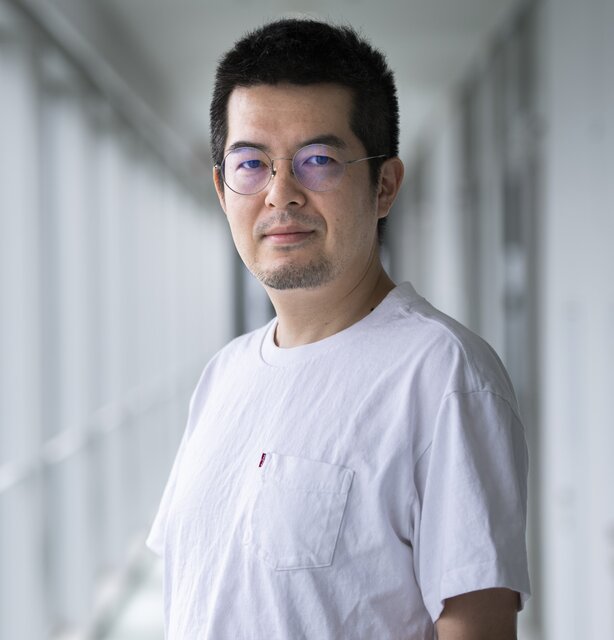
























































髙崎 順子
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)などがある。得意分野は子育て環境。
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)などがある。得意分野は子育て環境。