

発達障害・発達特性のある子の【トイレトレーニング】の方法を「療育の専門家」が解説
#7 トイレトレーニングはどうする?〔言語聴覚士/社会福祉士:原哲也先生からの回答〕
2024.06.19
一般社団法人WAKUWAKU PROJECT JAPAN代表・言語聴覚士・社会福祉士:原 哲也

発達障害や発達特性のあるお子さんの保護者の方からのご相談に、言語聴覚士・社会福祉士であり、発達障害のお子さんの療育とご家族の支援に長く携わってきた原哲也先生がお答えします。
お子さんとの生活が楽しくなり、保護者の方の負担が軽くなるような実践的なアドバイスをお伝えしていきます。第7回は、こちらのご相談です。
トイレに行くのを嫌がり、なかなかオムツが取れません。何かよい方法はないでしょうか?
【発達障害・発達特性のある子のお悩みに専門家が回答】これまでの回を読む
第1回 発達障害かどうか気になります
第2回 2歳ですが言葉が遅く心配
第3回 偏食がひどくて困っています
第4回 子どもが真夜中まで起きている
第5回 「こだわり行動」とは? 種類・原因・対応
第6回 医療機関を受診する目安
目次
今回はトイレトレーニングについてのご質問を取り上げます。
まず初めに一般的なトイレトレーニングについてお話しし、そのあとに発達障害の特性のある子のトイレトレーニングについて説明したいと思います。











![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)



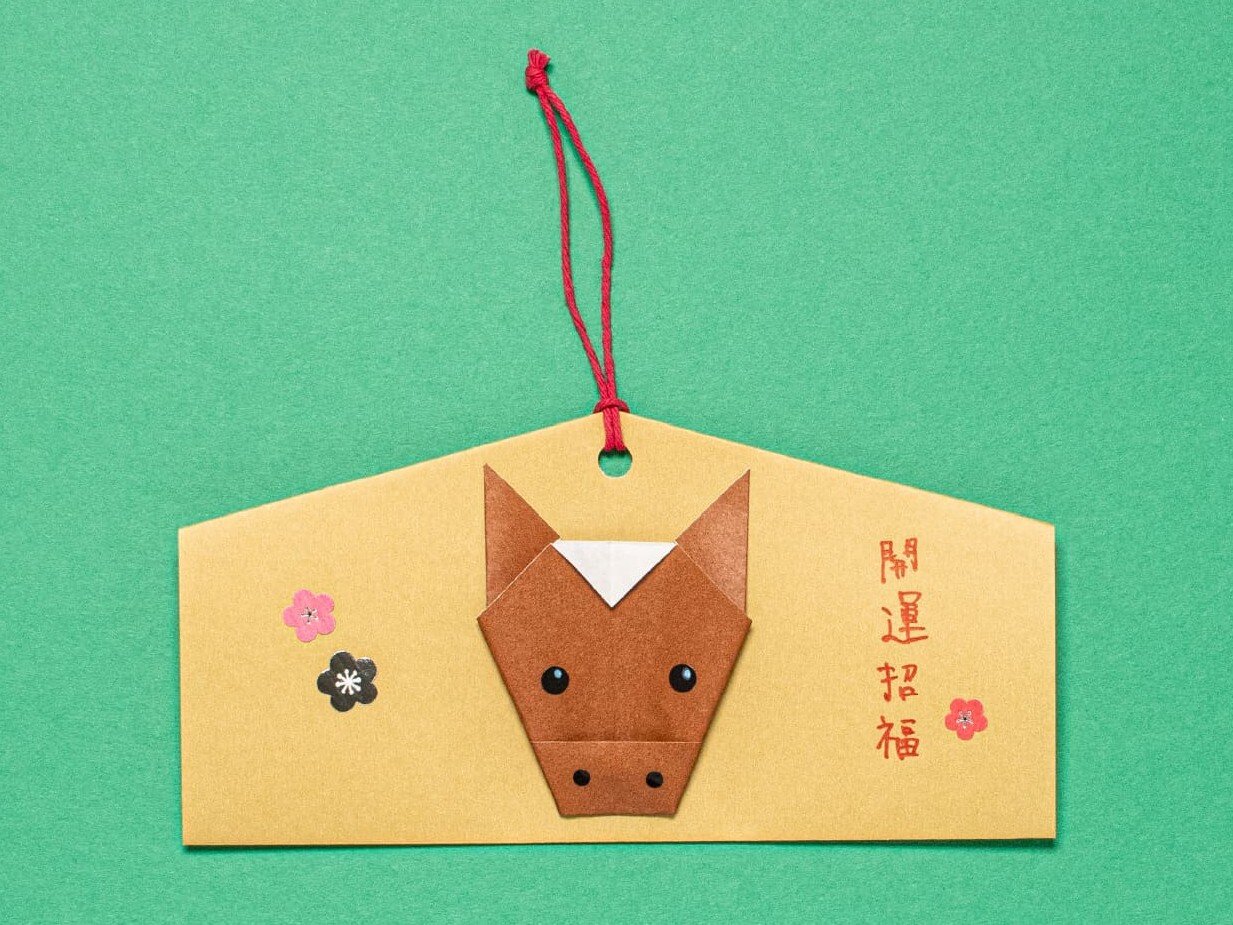





![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)




























































































