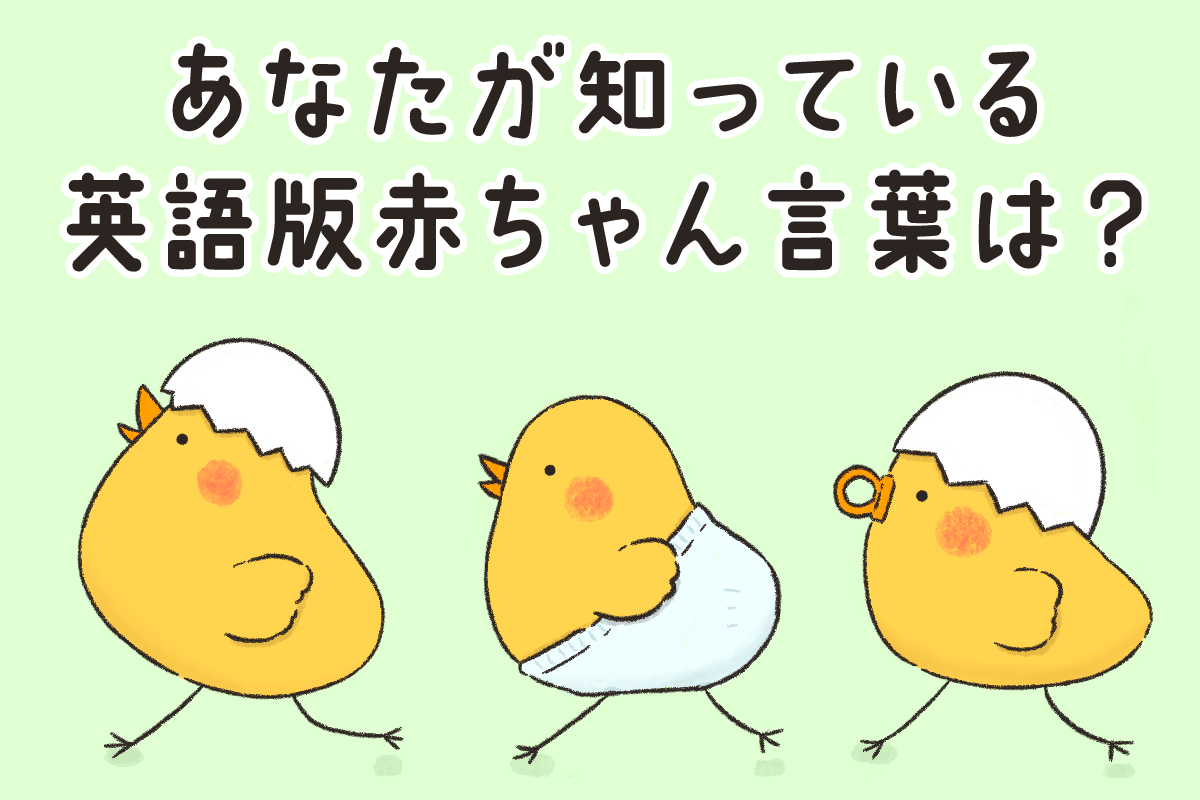部屋の中の安全対策
地震が来ても慌てずに済む家は、どう作ればいいのでしょう。
災害対策に詳しいNPO法人・かながわ311ネットワークの石田真実さんは、日常の安全対策と防災の両立が大切と指摘。
日常の収納を工夫することで、「地震後、散乱した破片などの片づけに追われる」という状況を避けられます。
石田さん
「乳幼児のいる家庭では、子どもの手が届かない高い場所に危険な物を置きがち。でも、地震のときには大きな揺れで落ちてくるリスクがあります」
ーーーーーーーーーーーー
室内での安全確保
ーーーーーーーーーーーー
●観音開きの棚
ストッパーをつけるか、引き戸式の収納に。中の物が飛び出しにくくなる
●包丁やまな板
使用中でも出しっぱなしにせず、シンクの中に置く習慣をつけるとよい
●割れやすい食器
シンクの下など低い場所にまとめて収納。引き出しには滑り止めシートなどを敷くと安全
ーーーーーーーーーーーー
非常食や備蓄品のコツ
「マンションの1階にスーパーやコンビニがあり、いつでも買い物できるから」と、家にあまりストックを置かない主義の人もいます。
しかし、防災の観点から言うとかなりリスキー。災害時にはすぐに品薄になる可能性があります。
在宅避難が想定されるマンションでの生活。エレベーターが止まると水や物資を運ぶのも困難になるため、食料や水の備蓄はマストなのです。
非常食というと、専用のものを用意し、賞味期限ギリギリまで保管しておく家庭が多いかもしれません。しかし、食べ慣れていない食品は、いざという時に子どもが口にしない可能性があります。
非常食には長期保存のためにさまざまな添加物が含まれており、味の好みが分かれることも。また、塩分を多く含むため、食後に喉が渇きがちです。

NPO法人・かながわ311ネットワークの伊藤朋子さんは、普段使いの食材や日用品を多めに備え、使ったら補充する「ローリングストック」を勧めています。
ある家庭では、子どもと一緒にさまざまなレトルトカレーを試食し「おいしく食べられるか」を基準に選定。「少し高くても、味を重視して備えている」といいます。
石田さん
「子どもや親自身がホッとできるような甘いものを準備しておくのも大切なこと。気分が落ち込みがちな災害時こそ、ちょっといいものを口にできるようにしておきましょう」
伊藤さん
「高価な防災専用の備蓄品ですべて揃える必要はないのです。普段から災害が起きたらどうなるかを具体的にイメージし、シミュレーションしておくことが、いざという時のパニックを防ぎます」
ーーーーーーーーーーーー
食料品・日用品の備蓄
ーーーーーーーーーーーー
●水(飲料用&調理用):
3L×人数×最低3日分を備蓄
●無洗米やパスタ
長期保存が可能で、カセットコンロと水があればあたたかい食事がとれる。パスタを少量の水に漬け、柔らかくしてから加熱するなど、水を節約する工夫も大切
●備蓄用非常食:
長期保存用できる一方、保存料が多く含まれ、味に好みが分かれる傾向が
●レトルト食品や缶詰など:
家族で試食し選定を。少し高くても美味しいものを選んで
●お菓子など:
災害時の気分転換や安心感を得る助けに
●ミルク:
粉ミルクは賞味期限が長く、ホットケーキなどの料理にも利用できる。一方、缶ミルクは衛生状態が万全でないときにもおすすめ
●衛生用品:
消費量の多いおむつは普段から多めにストックを
おしりふきは「ぬれタオル」の代用でさまざまな用途に使えて便利
ーーーーーーーーーーーー
子どもが寝る場所の安全確保
就寝中に地震が発生したら、真っ暗な中、子どもを連れて避難する可能性もあります。足元が十分に見えなくても、子どもを抱きかかえていても、階段を降りられるような備えが必要です。
ーーーーーーーーーーーー
就寝時の地震発生にそなえて
ーーーーーーーーーーーー
●足元を守る履物:
ガラスの破片などから足を守る。枕元に用意を
●停電時用の明かり:
ヘッドランプのように両手が空くタイプが理想的
●寝室やベッド周り:
地震で倒れてくる可能性のある家具や物がないかを再確認し、安全な部屋作りを
ーーーーーーーーーーーー
石田さんは、災害時の体験談として寄せられた声で、こんなエピソードを教えてくれました。
体験談
「東日本大震災発生時、子どもはお昼寝中。建付けが悪く普段は動きにくい窓が『スーッ』と開いたことを覚えています。お昼寝スペースに何も置いていない畳の一角を確保していて良かった」
石田さん
「最近は子どもが寝る部屋を別室にし、見守りカメラを設置している方も。でも、いざ地震が起きるとドアが歪んで開かなくなり、子どものそばに駆け付けられなくなるケースも起こり得ます。ドアが完全にロックされないような対策も必要です」
近所づきあいも防災につながる
「ご近所づきあいが煩わしいから」とマンション住まいを選んでいる人もいるかもしれません。
しかし、友人や親戚に限らず、困った時に「助けてほしい」と言える相手が近くにいることは、心強い備えとなるのです。
石田さんは、「マンションの管理組合や自治会の活動に顔を出したり、挨拶を習慣にしたりすると、いざという時の助け合いに繋がりやすくなる」と言います。
体験談
「東日本大震災当時、マンションに住んでいました。夫が帰宅できず、子ども3人を抱えて不安を感じていたら、それまで挨拶程度の仲だった同じ階の方が『困っていること、ない?』と声をかけてくれました。そのお宅も母子で過ごしていたのです。結局、お互いの夫が帰ってくるまでの数日間、助け合って一緒に過ごしました。大人が2人いるのはとても心強かったです」
伊藤さん
「『お子さん、かわいいわね』などと声をかけてくれる人は、いざというときに頼れる人かもしれません。一言二言交わすだけでも『◯◯号室には小さいお子さんがいる』と知ってもらえ、何かあった時に助け合いがしやすくなります」
マンション防災は、日常の延長上にある
子どもを守れるのは、日々の備え。「何かあったら」ではなく、起こる前提で考えることがマンション防災の第一歩となります。
かながわ311ネットワークでは、親子向け防災教室を開催。子どもの年齢や時間、目的に応じて、親子で参加できる多彩な防災教育プログラムを提供しています。(親子向け防災教室リンク)
日常の生活の中にこそ「防災」を。親子で楽しむ視点ももちながら、日々の暮らしの中にさまざまな備えを組み込んでいきましょう。
















![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)
![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)