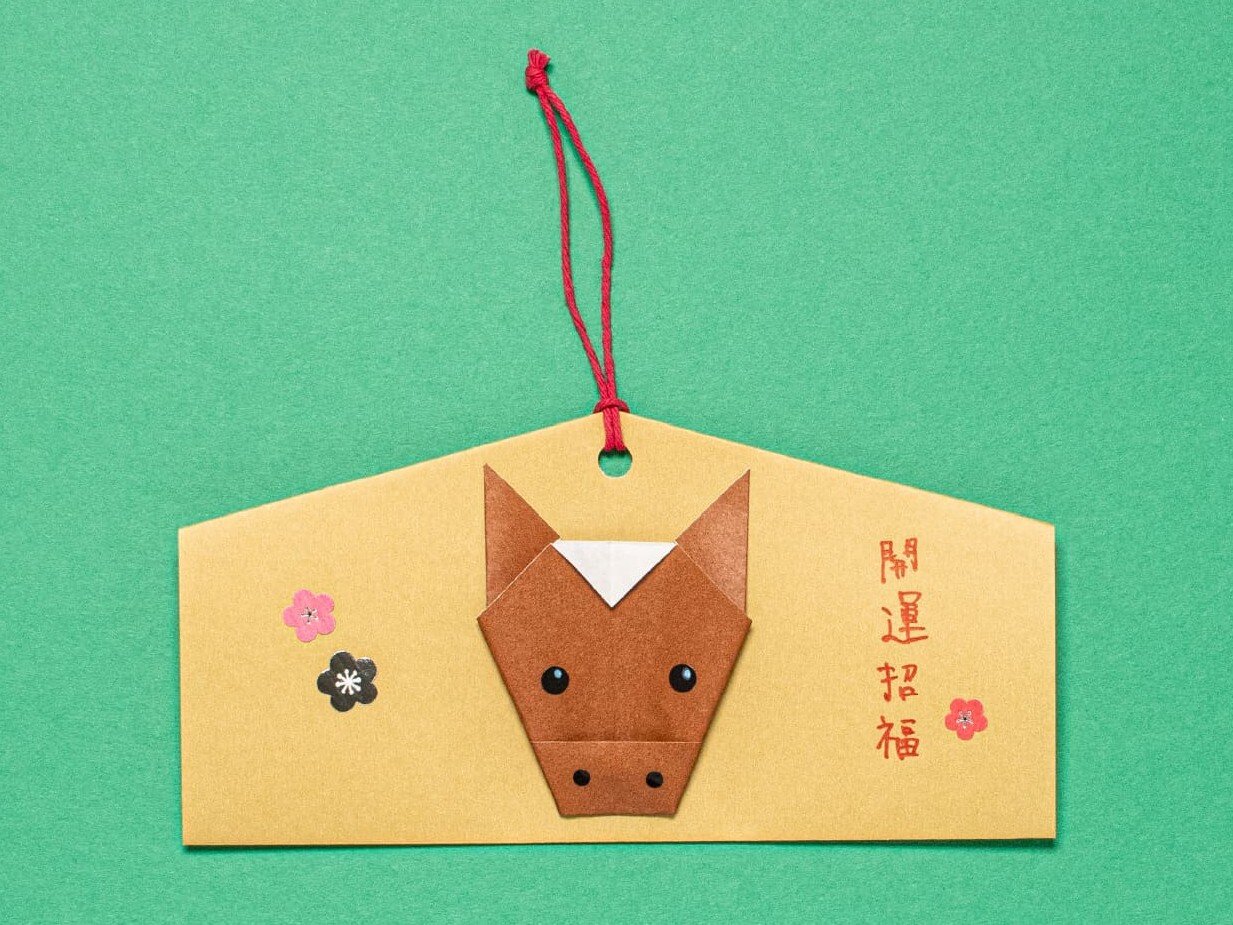前頭葉の発達ピークは10代! 脳科学的に子どもの「ならいごと」を検証
発達のピークは部分で違う! 「幼児期の脳」基礎知識〔細田千尋先生インタビュー 第1回〕
2021.06.10
医学博士・認知科学者・脳科学者:細田 千尋
ピアノや水泳、体操に幼児教室など。多くのならいごとがあるなかで「うちの子に合っているならいごとは一体どれ?」「いつからなにを始めたらいいの?」と悩んでしまいますよね。
そこで、脳科学の分野で教育や学習法についての研究を行う細田千尋先生に、科学的な視点からならいごとについて解説していただきました。
第1回は、乳幼児期の脳の発達とならいごとの関係についてのお話です。





















![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)