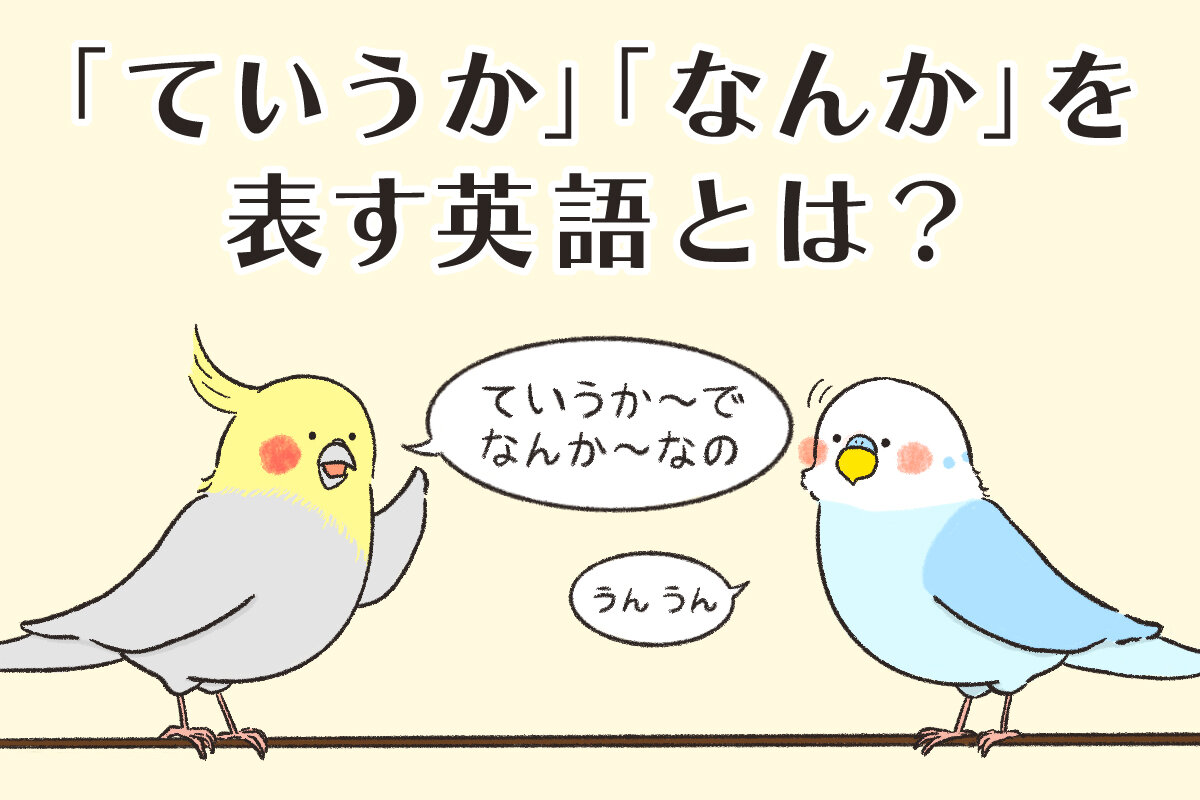

ポケモンやプリキュアのキャラクター名分析や、日本語ラップの言語学的分析など、幅広い分野で柔軟な研究を行い、言語学内外から大きな注目を集めている、音声学・言語学者の川原繁人教授。ミュージシャンの北山陽一(ゴスペラーズ)さんとの共著『絵本 うたうからだのふしぎ』が人気となっています。
声はどうやって生まれるのか、身体の中で何が起こっているのかなど、知られざる声の秘密について教えていただきました。
「声」によるコミュニケーション、その驚きのシステム
声というものは、ほぼ毎日使うものですから、ついつい「あって当たり前」と思ってしまいがちです。しかし、声を使って話し相手にことばが伝わるというのは、実はすごいことなのです。この記事では、これがいかにすごいことか、そしてその「すごい」を支えている「人体のすごさ」について解説していきます。
まず、話者の発したことばを聴者が理解できることが、どれだけすごいことなのか、マジックに喩えて考えてみましょう。こんな状況を想像してみてください。あなたは口の中で赤・青・黄のあめ玉をなめていて、マジシャンが近くに立っています。ただし、そのマジシャンにはあなたは見えていません。
あなたが3つのあめ玉から好きなものを1つだけ飲み込むと、マジシャンはその色を当ててしまいます。1回だったら偶然当たることもあるでしょう。しかし、このマジシャンは、これを何千回・何万回と繰り返しても、何色のあめ玉を飲み込んだかを当て続けます。偶然とは思えない仕掛けがありそうです。
私たちの発した音声が聞き手に伝わったとき、同じことが起こっています。この喩えを理解するために、試しに「ぱぱぱ」と発音してみてください。両唇が閉じると思います。次に「たたた」と発音してみましょう。舌先が上下に動くのが感じられるのではないでしょうか? 最後に「かかか」と発音すると、舌の奥が動くと思います。

このように、「ぱ」「た」「か」は、どの器官が動くかが異なります。ここで、私たちが例えば「ぱ」と発したとき、聞き手は私たちの口の動きが見えていなくても、それが「両唇」を使って発せられた「ぱ」であることが理解できます。
私たちは口の中のいろいろな器官を使って、いろいろな音を発していますが、聞き手はその口の中を見なくても、どの器官を使って発せられた音なのか理解できる。この意味で、音声コミュニケーションでは、上で述べたマジックのようなことが起こっていると言えるのです。
日本語を例にして、もう少し具体的に考えていきましょう。数え方にもよりますが、日本語は15個ほどの子音と、5個の母音を持っています。ですから、拗音(「ゃ、ゅ、ょ」)を入れると「う」「た」「に」「な」「ろ」などの子音と母音の組み合わせは、だいたい約100個になるでしょうか(=50音+濁音+半濁音+拗音)。
つまり、上のマジックの喩えでいえば、話者の口には100個ほどのあめ玉がはいっていて、聞き手は、話者がどのあめ玉を飲み込んだか―どのように口を動かしたか―について約100個の選択肢の中から正解を選び続けることができる。すごいことだと思いませんか?
もちろん、マジックにはタネがあります。音声コミュニケーションの場合、そのタネは空気です。話者と聴者の間には空気が存在していて、話者が発した音は、口のまわりの空気を振動させ、その空気の振動が聴者の耳に届くのです。それぞれの音によって空気の震わせ方が異なるので、聴者は話者が発した音を理解できる、という仕組みです。
声を出すとき、体も動く
この仕組みを駆使してコミュニケーションをとるために、人間は多くの器官を使って音声を発しています。まずは、空気の振動を起こすためのメカニズムから考えていきましょう。
空気の振動を起こすためには、息を吐く必要があり、これを支えているのが肺です。人間は肺を大きくすることで息を吸い、その肺が収縮する過程で息を吐きます。ところが、肺は自分自身では動くことができないため、さまざまな筋肉が動くことで呼気を生み出しています。
まず、肺を大きくして息を吸うために大事な筋肉は、「横隔膜」と「外肋間筋」です。横隔膜は肺が入っている胸郭という空間を下にひっぱり、外肋間筋は胸郭を斜め上方向にあげることで肺を広げます。
肺というのは風船のようなもので、広がると自然にもとの大きさに戻る性質を持っています。ですから、肺が膨らんだあと何もしないと、空気は一気に外に流れてしまいます。しかし、外肋間筋が胸郭を引っ張り続けることで、ゆっくりと息を吐くことができます。つまり、長い時間声を出せるのは外肋間筋のおかげなのです。
肺がもとの大きさに戻ったあとも、息継ぎなしで声を出し続けたいときには、「腹直筋」などの腹筋群や「内肋間筋」、さらに背中の「広背筋」などが働いて、肺をさらに縮めることができます。我々が声を出せるのは、これらの筋肉が肺を動かしてくれているおかげなのです。

このように、肺は声の源となる呼気をつくりだします。また、声の大きさを調節するのも肺の大事な役割です。肺から勢いよく空気が流れれば大きな声がでますし、小さな声を出すためには、空気の流れを抑える必要があります。
声のもとになる「音」は声帯で生まれる
肺から送り出された息は、喉の奥にある「声帯」というヒダを振動させ、これが私たちの声のもとになる「音」を作りだします。声帯は、「喉頭」という器官の中に入っていて、喉頭の仕組みもまた肺に劣らず驚くべきものです。
声帯は左右に1枚ずつ存在するのですが、振動を起こすためには、この2枚が近づいてなければなりません。しかし、ひそひそ声で話すときや、はたまた「ぱ行」や「た行」の子音を発声するときには、声帯を振動させてはいけず、そのためには左右の声帯が開きます。
ですから、人間には、左右の声帯を閉じる筋肉(「外側輪状披劣筋」など)や開く筋肉(「後輪状披劣筋」など)が備わっていて、どんな音をだすか・どんな話し方をするかによって、これらの筋肉の働きが変わります。
また、声の高さを決めるのも声帯の仕事です。一般的に声帯は緊張度があがると、その振動数が高くなり、結果として声の高さが上がります。この調整にもさまざまな筋肉が使われることが分かっていて、例えば「輪状甲状筋」は、声帯の前方がくっついている甲状軟骨―体の外側からは喉仏として見えることもあります―を傾けることによって、声帯を引っ張り、声を高くします。

声を低くする仕組みは未解明な部分も多いのですが、声を下げるときには喉頭全体が下がることは分かっています。試しに、自分の喉仏に手をあてて、いろいろな声の高さで声を出してみると、喉仏が上下するのを感じられる人もいるでしょう。喉頭を下げるためには胸骨舌骨筋などが使われます。声帯や喉頭の動きにも、さまざまな筋肉が関わっているのですね。
また、発話の全体的な声色を調整するのも声帯の仕事です。声帯は、三層構造になっていて、その厚みなどを変えることによって、声色が変わります。
さらに、一般人が日常生活で意識的に操る必要はないのですが、声帯の上には「仮声帯」というもう一対のヒダがあり、これを操ることで声色を変えることもできます。例えば、ダミ声は仮声帯を締めて発声します。また、喉頭の上には、肺に食べものが入らないように蓋をする「喉頭蓋」という器官が存在し、その喉頭蓋の傾き加減によっても、声色は変わります。声優さんのようにいろいろな声色を操れる人は、声帯・仮声帯・喉頭蓋などを駆使して、声色を変えていると考えられます。

肺に関しても喉頭に関しても、この記事で紹介した筋肉は一部に過ぎません。それだけ発声の仕組みは複雑なのです。
口腔で作る音の複雑さに舌を巻く!
さて、肺が作りだした呼気は、声帯を震わせることによって音になるのでした。次に重要なのは、「口腔」で起こる「共鳴」です。声帯でつくり出された「音」は、共鳴することにより「音声」になるのです。日本語にはさまざまな音がありますが、それぞれの音によって口腔の形と空気の流れ方が異なるため、独自の共鳴の仕方をします。
それでは、代表的な子音の特徴を紹介していきましょう。例えば、「ま行」や「な行」の子音。試しに、鼻をつまんで「あかさたなはまやらわ」と発音してみると、「な」と「ま」の部分で発音しづらく感じられるのではないでしょうか。これは、「な」や「ま」を発音するときには、口蓋帆という鼻への弁が下がることにより、鼻から空気が流れて、鼻の中でも音が響くからです。
では、「な」と「ま」は何が違うのでしょう。これも実際に発音すると感じられると思いますが、「な」では舌先で口腔が閉じ、「ま」では両唇で口腔が閉じます。音の響き方は、その響く空間の大きさによって異なります。バイオリンとコントラバスの響きが異なるのと同じです。「ま」と「な」では口の閉じの背後の空間の大きさが異なるので音色も異なる、というわけです。

では「さ行」はどうでしょう。「さ」の子音部分を発音するときには、舌先が上の歯の根元部分である歯茎に近づきます。ですから、舌の動きの観点からは「な」と「さ」は非常に似ています。ただ、「な」では舌先で口腔が完全に閉じるのに対して、「さ」では口腔は狭められるだけです。
このように非常に狭められた道を空気が通ると、空気の乱流(=摩擦)が起こります。これは、ホースから水を流している時に、ホースの先を潰した状況にとても似ています。さらに、「さ」の場合、舌先で作りだされた乱流は上の歯の裏に当たることで、音の大きさが増幅されます。
次に「ぱ」「た」「か」をどのように発音するか考えてみましょう。口蓋帆は閉じていて、鼻から空気は流れません。「ぱ」「た」「か」それぞれ、両唇・舌先・舌の胴体で口腔が完全に閉じます。さらに、左右の声帯は開いていて、呼気がどんどん口腔に溜まっていきます。空気がたまると口腔内の気圧が高まり、その結果として閉じの開放とともに破裂が起きます。
このように私たちは、口のどこで発音するか・空気をどのように流すか・声帯を開くか閉じるか、などを調整してたくさんの種類の子音を作り上げています。
最後に、母音について考えてみます。まずは、「あ」「い」「あ」「い」「あ」「い」と大袈裟に発音してみましょう。「あ」では顎と舌が大きく下がり、口腔が広く開きます。逆に「い」では顎と舌が上がり、口腔は狭くなります。「う」も「い」と同様に口腔が狭くなります。「え・お」は、「あ」と「い・う」の中間あたりと言っていいでしょう。

さらに、「い」「う」「い」「う」「い」「う」と繰り返して発音してみると、「い」では舌が前に出て、唇は後ろに引っ張られ、「う」では逆に舌が後ろにさがり、唇は丸まります。つまり我々は母音の音色を操るために、舌・顎・唇を駆使しているわけです。
まとめると、人間は体のさまざまな器官を調整することによって、実に多数の音色の音を紡ぐことができるのです。こう考えると、人間の身体というのは、それそのものが楽器であると考えてもいいでしょう。さらに、楽器それぞれに特徴があるように、人間の体もそれぞれ個性を持っています。声帯の長さや口腔の形などは個人によって違うので、自然と声の高さや共鳴の仕方も人によって異なります。
耳のしくみもかなり精巧
これまで、話し手のすごさを強調してきましたが、聞き手としての人体のメカニズムも同様に驚くべき仕組みを持っています。
まずは、一般的に「耳」として知られている「耳介」は、そのでこぼこによって入ってくる音を乱反射させ、これにより人間はどの方向から音が来たかを感知できます。イヤフォンを使って音を聞くと、耳介を通さないため、どの方向から音が聞こえてくるか感じることができません。
耳介から鼓膜に至るまでの道である「外耳道」では、話し手が発した音の種類を区別するのに重要な周波数帯の音が共鳴します。そうして鼓膜に到達した空気の振動は、耳小骨という骨々が「てこ」として働いて、大きさがなんと20倍以上に増幅されます。その増幅された音は「蝸牛」という器官に伝わり、蝸牛にはその音にどのような周波数成分が含まれているかを解析する仕組みが備わっています。この仕組みは、18~19世紀に活躍したジョゼフ・フーリエという数学者が提唱し、現在我々の生活の至る所で利用されている「フーリエ変換」という数学的解析法です。

まとめると、我々の耳は、音がどの方向から聞こえてくるかを感知し、話し手の音声の特徴を増幅させ、音自体を大きくし、その音がどんな周波数成分を持っているかを自動的に解析する仕組みを備えている、というわけです。
この記事の最初に、「私たちが発したことばが相手に伝わることは奇跡である」ということを述べました。肺から空気が流れ、それが声帯振動に変わり、口腔や鼻腔で共鳴し、空気の振動として聴者に伝わり、聴者はそれを理解する。私はこの一連のプロセスについて研究すればするほど、人間の体についての驚嘆が深まっていきます。

身体に取り込まれた空気が声になるまでの冒険を、わかりやすく表現した絵本です。川原先生のくわしい解説もあって、子どもからおとなまでたのしめます。











![「卒園おめでとう」を伝える絵本3選! 門出を祝うプレゼントにぴったりな名作[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/879/large/fe3c9db7-2339-4abc-a2cd-c276cc46fa59.jpg?1772501924)





































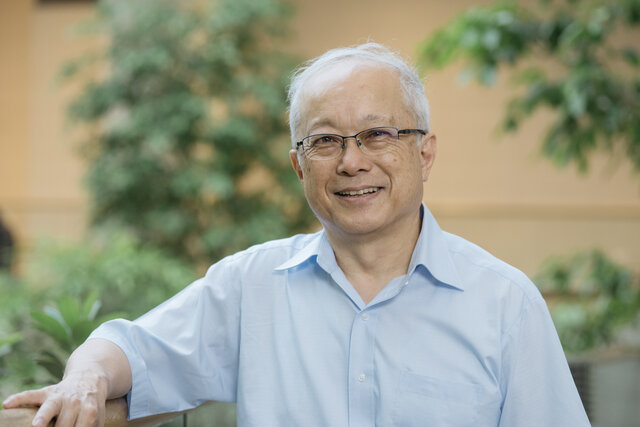


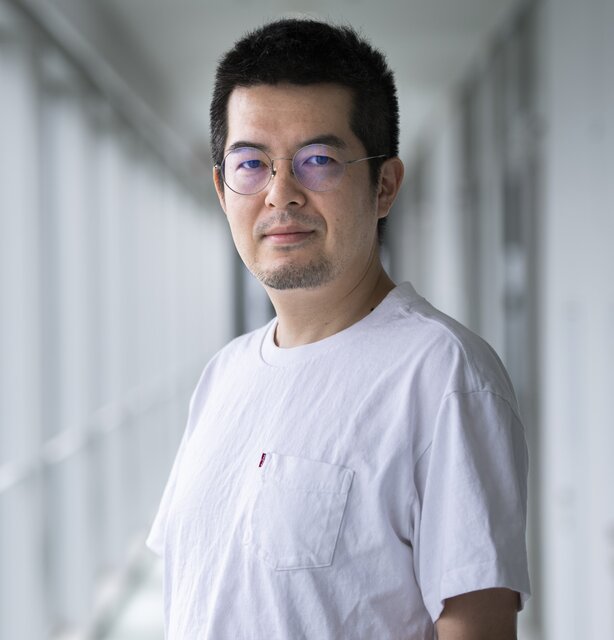





























































川原 繁人
慶應義塾大学言語文化研究所教授。2007年マサチューセッツ大学より博士号(言語学)。ジョージア大学、ラトガーズ大学にて教鞭を執った後、現職。専門は言語学、音声学。「ことばを話せることって、とってもすごいこと!」という想いを伝えるため、幅広い読者に向けて本を執筆している。 代表的な著書として『音とことばのふしぎな世界』(岩波科学ライブラリー)、『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』(朝日出版社)、『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか?言語学者、小学生の質問に本気で答える』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『言語学的ラップの世界』(東京書籍)がある。義塾賞(2022)、日本音声学会学術研究奨励賞(2016、2023)を受賞。
慶應義塾大学言語文化研究所教授。2007年マサチューセッツ大学より博士号(言語学)。ジョージア大学、ラトガーズ大学にて教鞭を執った後、現職。専門は言語学、音声学。「ことばを話せることって、とってもすごいこと!」という想いを伝えるため、幅広い読者に向けて本を執筆している。 代表的な著書として『音とことばのふしぎな世界』(岩波科学ライブラリー)、『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』(朝日出版社)、『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか?言語学者、小学生の質問に本気で答える』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『言語学的ラップの世界』(東京書籍)がある。義塾賞(2022)、日本音声学会学術研究奨励賞(2016、2023)を受賞。