

令和の「不登校問題」 現役教師が明かす学校側のリアルな声!
フリーランスティーチャー・田中光夫先生に聞く、子どもが不登校になったときどうしたらいい? #1 令和時代の不登校の認識と学校側の視点 (2/2) 1ページ目に戻る
2023.06.05
フリーランスティーチャー:田中 光夫
コロナ禍を経て「登校拒否」から「不登校」へ
田中光夫先生(以下、田中先生):20年以上前、私が初めて勤めた小学校では、子どもが学校を長期で休んでいる状態を「登校拒否」と呼んでいました。当時は学校側も親も、「なんとしても子どもを学校に行かせよう」という風潮でした。
しかし、学校に行けない理由は人それぞれあり、単に登校を拒否しているとは限りません。そのため、現在文科省では、年度間に連続、または断続して30日以上学校を欠席している場合「不登校」という状態であると定義しています。また、私の新任時と比べて、多様性が認められるようになり、不登校の子どもに寄り添う対応も増えてきたという印象ですね。
──文部科学省の発表によれば、全国の国公私立小中学校の不登校の児童・生徒は、2021年度で24万4940人となり、過去最高数だと言われています。そのような実感はありますか?
田中先生:私自身、直近5年間は小学校低学年の担任になることが多かったのですが、私のクラスで不登校になる子はいませんでした。そのため「急激に不登校が増えているな」という実感はないのが正直なところです。
しかし、コロナ禍を経て、少しの体調不良でも親は無理して子どもを登校させなくなりました。以前よりも、親も子も「学校に行く」、「行かない」が選択しやすくなったのは事実です。そうした背景が、不登校の児童が急激に増えている理由のひとつかと思いますね。
ちなみに、ぽつりぽつりと休みが続き、連続欠席が4日以上を超えると、元の生活に戻すことが難しくなるといいます。
私はこれまで不登校になる理由は、メンタルの問題だとばかり思っていましたが、令和時代はメンタルではなく身体が拒否している状態の子が多くいます。そうしたときに、周りから「どうして学校行かないの?」、「いつから学校に行くの?」など聞いてしまうこと自体が子どもにとってつらいですよね。
例えば、バンジージャンプを想像してください。足がすくんで一歩も踏み出せない状態でいるときに、無理に背中を押されたらどうなるでしょうか。「裏切られた。もう、二度と挑戦しない」という気持ちになってしまうことも往々にしてあると思うんです。
それと同じで、学校に行きたくても身体が動かない、具合が悪くなってしまう。そういった子どもに対して、教員としてしっかり気持ちを配慮してあげたいなと強く思いますね。
──子どもを追い詰めるような言葉がけをしていないか、大人は見直す必要がありますね。
田中先生:そうですね。また文科省の令和2年度の調査によると、最初に学校に行きづらいと感じ始めたきっかけとして、「学校の先生」(小学生30%、中学生28%)があり、不登校の原因として上位に挙げられています(引用元:文部化科学省 令和2年度不登校児童生徒の実態調査結果)。
例えば、先生に怒られて学校に行きたがらなくなってしまうケースですね。
先生が原因で不登校になっているのだとすれば、それは学校側が「子どもは学校に来るのが当たり前」という視点で考えているからでしょう。つまり、マイノリティ側の視点に立っていないということ。そのため大勢のクラスの中で悩んでいる子がいても、何に悩んでいるか気づかずに取りこぼしてしまうんです。
教員は「みんなできているから、できない子は甘えているんだ」と考えるのではなく、できない子に対して「何がこの子の壁になっているんだろう」、「どうすれば悩みが解消されるんだろう」と、マイノリティ側の視点に寄り添って考えることが大事だと思います。
忙しすぎる先生たちが抱えるジレンマ
──現実問題として、クラスで悩んでいる子どもがいた場合、先生は自ら気づいて適切なサポートをしてあげることは難しいのでしょうか?
田中先生:もちろんきちんと向き合ってサポートされている先生はたくさんいると思います。しかし、正直にお話をすると、今、学校側はすごく忙しいのが事実です。
昨今の働き方改革に加えて、ICT教育、GIGAスクール、英語教育など、やらなければならないことが足し算式に増えていて……。私たちが子どもだった30年前の学校とは余裕がまったく違うんですよね。そのためクラスで悩んでいる子どもがいても気づいてあげられない場合が正直出てきてしまっているのだと思います。
本来、「子どもたちに学校や学びの楽しさを伝えたい」、「子どもたちの成長をサポートしたい」と思って教員になったはずが、それができない現実にジレンマを抱えている教員も多くいます。
実際に保護者の方から子どもの様子を伝えていただいて、そこで初めて教員が気づくこともあります。
──保護者の方からもっと先生に相談してもいいんですね。
田中先生:例えば、子どもが家で「テストを受けたくないから学校を休みたい」と言っているとしましょう。保護者の方は「うちの子だけ、テストを受けさせないでください」と学校側に伝えたい。
けれど、それを学校に伝えると担任から「この親は自分の子どものことしか考えていない」、「わがままな親だと思われるかもしれない」と悩むわけです。
でも、親が自分の子どもを一番に考えるのは当たり前のこと。私はそれでいいと思っています。いろんな理由があって子どもが学校に行けない、行きたくないというのであれば、その気持ちを学校側がまず受け入れてあげればいいだけです。
子どもが「宿題がつらい」と言えば、学校側は「宿題はなくしましょう」と。子どもが「ドッジボールが嫌だから学校休みたい」と言えば、学校側は「ドッジボールは見学でいいですよ」と。
そうやってハードルとなっている壁を、学校側がどんどん取り除いていければいいなと思いますね。
特に小学校1年生の担任は、児童に学校は楽しい、学校に行くのが好きと思ってもらえる場を作ることが大切です。
つい、よかれと思って教員が取り組んでいることも、クラスの中にはしんどさを感じている子どももいます。私自身も保護者からの声を聞いて、初めて気づかされることも多々ありました。
そのように、保護者から声をあげていただくことは、教員にとってとてもありがたいことなんです。
もちろん、教員も人間ですから、教員の中には保護者から「あなたのせいで、うちの子は学校に行きたくないと言っているんだ」とストレートなパンチを受けて、心を痛めてしまうケースもあります。そこは難しいバランスではあるのですが……。
──学校側も保護者も子どものために、何ができるのかを一緒に考えていく姿勢が大事なんですね。
田中先生:そうですね。本来、教育というのは「学校の責任」、「家庭の責任」として捉えるのではなく、子どもが将来にわたって幸せになっていく力を一緒に考えていくことが大事です。
不登校に関しても大人が子どもの視点に立って、学校側は保護者とともに一緒にサポートしていく。理想論のように聞こえるかもしれませんが、これからの時代、もっと子どもに合わせて学校側は変わっていかなければならないと思いますね。
───◆─────◆───
子どもが不登校になる理由は、本人ですら分からないケースが多いといいます。そういった子どもたちに対して、大人が追い詰めるような言葉がけになっていないかの注意が必要です。
また、現在の教育現場では、働き方改革やICT教育などで先生方にゆとりがなく、悩んでいる子どもがいても、気づいてあげられていないケースもあり、このような状況に先生自身もジレンマを抱えていることが分かりました。
2回目では、不登校になったときの過ごし方について、引き続き田中先生にお話を伺います。
取材・文/山田優子
フリーランスティーチャー・田中光夫先生の記事は全3回。
2回目を読む。
3回目を読む。
(2回目は2023年6月6日、3回目は2023年6月7日公開日予定。公開日までURLリンク無効)


山田 優子
フリーライター。神奈川出身。1980年生まれ。新卒で百貨店内の旅行会社に就職。その後、拠点を大阪に移し、さまざまな業界を経て、2018年にフリーランスへ転向。 現在は、ビジネス系の取材記事制作を中心に活動中。1児の母。
フリーライター。神奈川出身。1980年生まれ。新卒で百貨店内の旅行会社に就職。その後、拠点を大阪に移し、さまざまな業界を経て、2018年にフリーランスへ転向。 現在は、ビジネス系の取材記事制作を中心に活動中。1児の母。













































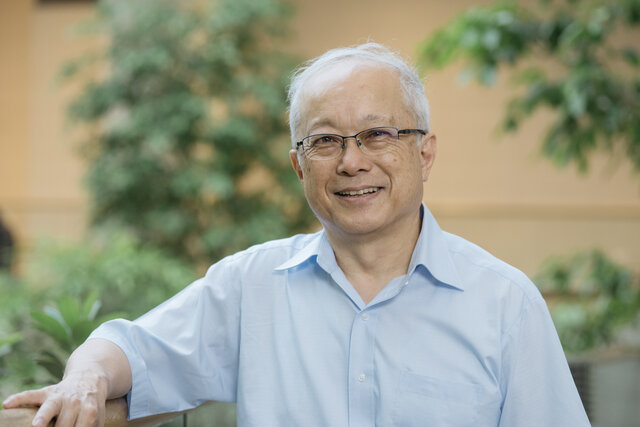


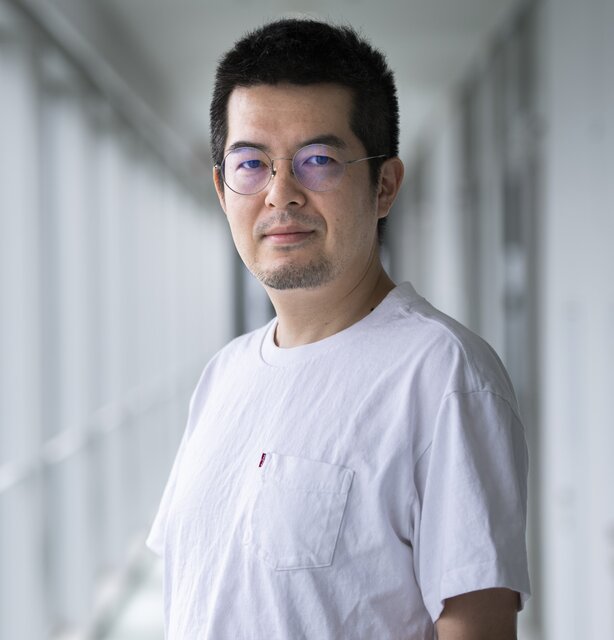























































田中 光夫
14年間の公立小学校勤務を経て、2016年4月より休業に入る先生の代わりに学校担任をする「フリーランスティーチャー」に。現在(令和5年6月)までにトータル12の小学校で代替え教師を務める。また、教員向けの実践ワークショップを定期開催している。 主な著書「マンガでわかる! 小学校の学級経営クラスにわくわくがあふれるアイデア60」。 Twitter @kariageshokudou
14年間の公立小学校勤務を経て、2016年4月より休業に入る先生の代わりに学校担任をする「フリーランスティーチャー」に。現在(令和5年6月)までにトータル12の小学校で代替え教師を務める。また、教員向けの実践ワークショップを定期開催している。 主な著書「マンガでわかる! 小学校の学級経営クラスにわくわくがあふれるアイデア60」。 Twitter @kariageshokudou