

自分のお子さんをよく見ながら、自分でできることが少しずつ増えていくように声掛けしながら手伝ってあげましょう。

「身じたくは子どもの発達に合わせて教える、といわれるが、よくわからない」(3歳・男の子)

子どもの成長に見合う小さなステップをたくさん用意してあげることです
着替えを例にとると、最初は「服の前側はこっちよ」「袖に手を入れて」などと声をかけ、意識を着替えに向けさせていく段階です。
少し成長したら、さりげなく手伝いながら、できそうな部分だけをやらせて「自分でできた満足感」を味わわせていく段階。
次はもう少しレベルアップするというように、支援しながら徐々に子どもができることを増やしていくのが「発達に合わせる」ということなのです。
「最近、おもちゃなどを投げます。危険だということをどう教えたらいい?」(2歳・女の子)

投げなかったときにほめるようにします
「痛い痛いよ」「こわれるよ」「大事よ」などといって、目を見てしっかりと教えることを繰り返しましょう。
また、意外と効果があるのが、やらなかったときにほめる方法。
機嫌が悪いときに投げなかった、投げる前に「ダメよ」といったらやめた、ものの扱いが乱暴な子がそっと置いたときなどに、「投げなくて、えらかったね」といってほめてあげると学びにつながりやすいものです。
「ローテーブルなど高いところに登りたがるので、困ります」(2歳・男の子)

時期的なものなので、今は安全面に気を配って
こういう時期は「危ないから登っちゃダメよ」と、いくら教えても何度も繰り返す可能性が高いのです。
それだけに、教えていくことにあわせて安全面に配慮することが欠かせません。
不必要な台は除く、窓辺に台になるものを置かない、落ちても痛くないように床にマットを敷く、床にとがったものや、かたいものを置かないなど、危険を予測して事故を予防することが必要です。
また、絵本やDVDなどを活用して、「登るのはよくないこと」と教えていくとわかりやすいでしょう。
文/宇野智子 写真/Adobe Stock

げんき編集部
幼児雑誌「げんき」「NHKのおかあさんといっしょ」「いないいないばあっ!」と、幼児向けの絵本を刊行している講談社げんき編集部のサイトです。1・2・3歳のお子さんがいるパパ・ママを中心に、おもしろくて役に立つ子育てや絵本の情報が満載! Instagram : genki_magazine Twitter : @kodanshagenki LINE : @genki
幼児雑誌「げんき」「NHKのおかあさんといっしょ」「いないいないばあっ!」と、幼児向けの絵本を刊行している講談社げんき編集部のサイトです。1・2・3歳のお子さんがいるパパ・ママを中心に、おもしろくて役に立つ子育てや絵本の情報が満載! Instagram : genki_magazine Twitter : @kodanshagenki LINE : @genki












































































































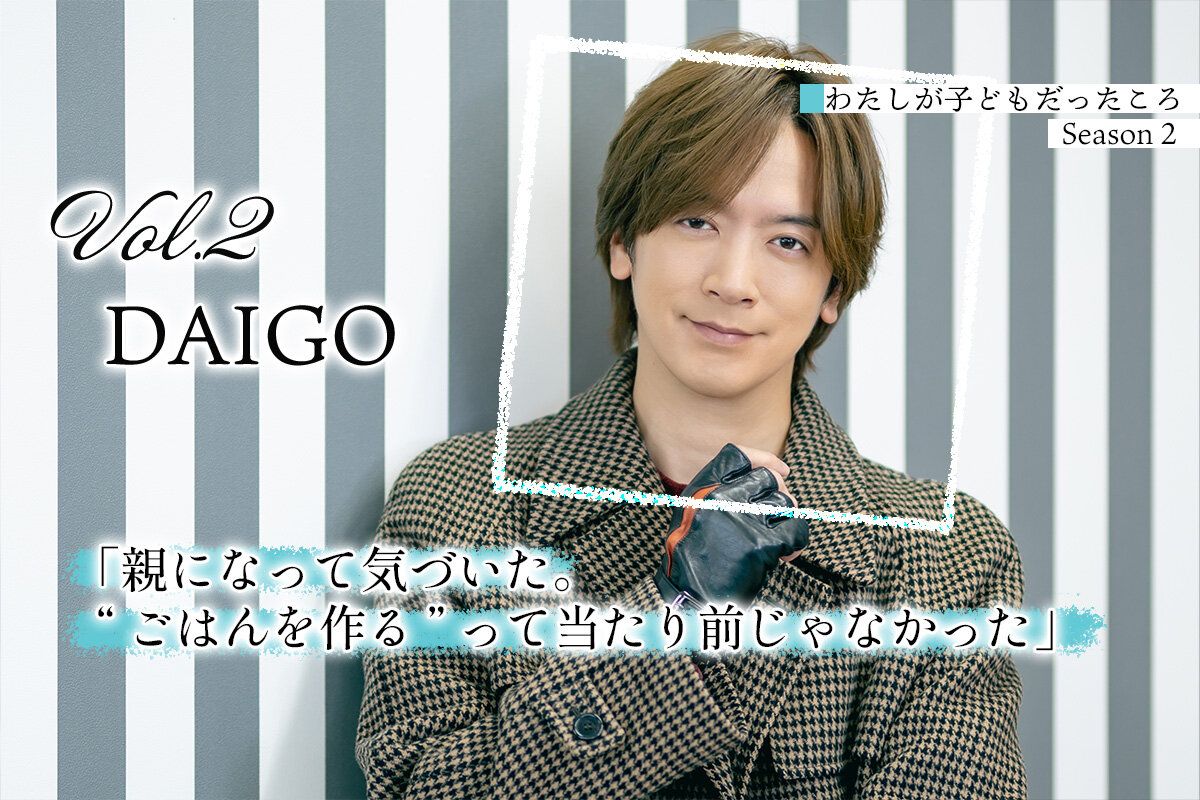










渡辺 弥生
大阪府生まれ。1983年筑波大学卒業。同大学大学院博士課程心理学研究科で学んだ後、筑波大学、静岡大学、途中ハーバード大学客員研究員を経て、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長兼務。教育学博士。専門は、発達心理学、発達臨床心理学。主な著書に『まんがでわかる発達心理学』、『11歳の身の上相談』(講談社)、『親子のためのソーシャルスキル』(サイエンス社)など。
大阪府生まれ。1983年筑波大学卒業。同大学大学院博士課程心理学研究科で学んだ後、筑波大学、静岡大学、途中ハーバード大学客員研究員を経て、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長兼務。教育学博士。専門は、発達心理学、発達臨床心理学。主な著書に『まんがでわかる発達心理学』、『11歳の身の上相談』(講談社)、『親子のためのソーシャルスキル』(サイエンス社)など。