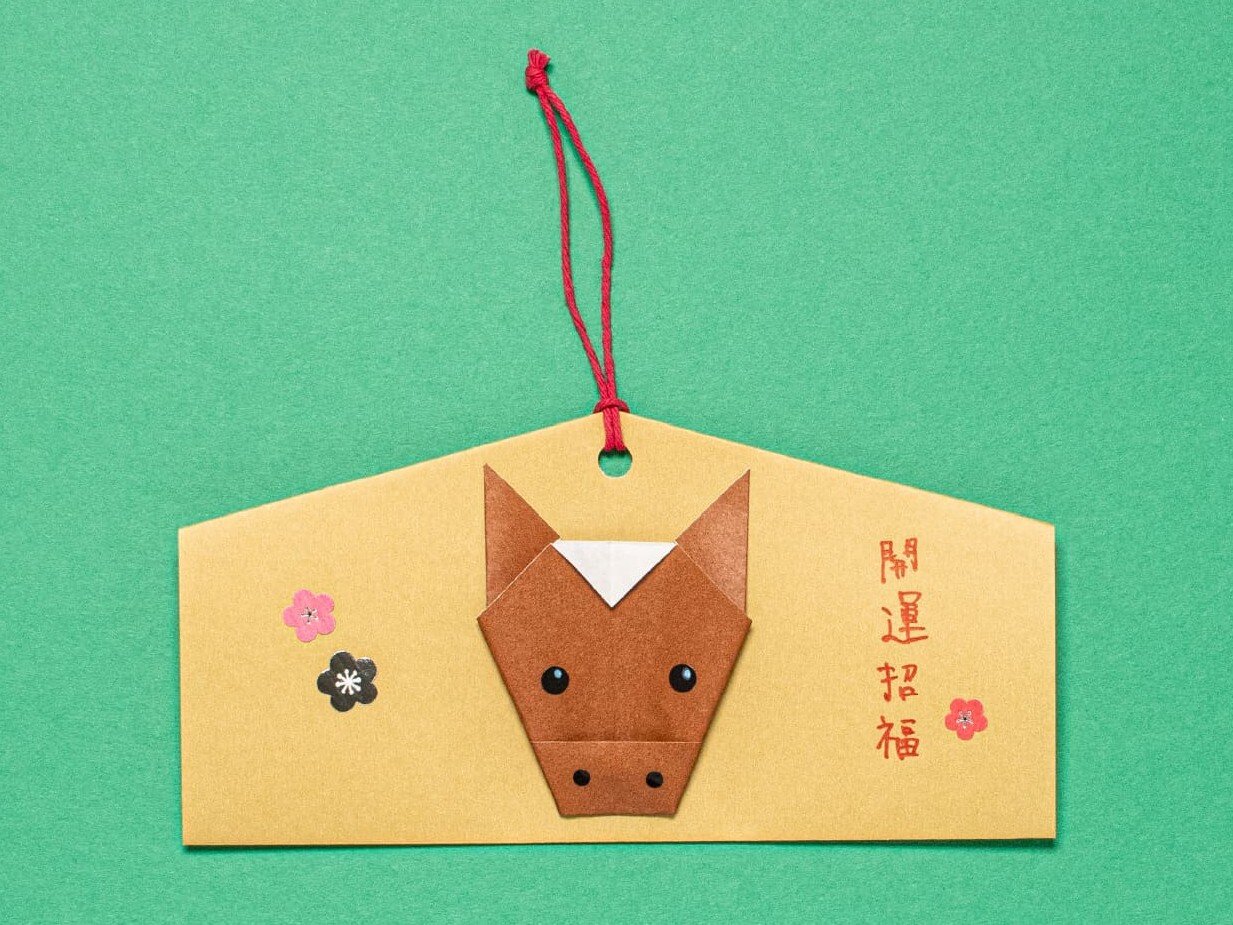【公民館がスゴいことになっていた!】“公園+パラソル“だけの屋台型「パーラー公民館」 超レアな「地域の拠点」に全国から視察も多数
シリーズ「地域をつなぐ みんなで育つ」#3‐4 「若狭公民館」【2/2】(沖縄県那覇市) (3/4) 1ページ目に戻る
2025.04.08
ライター:太田 美由紀
設置2年目には、パーラー公民館にこんな感想が寄せられています。(「パーラー公民館の2018年の評価・検証調査」より引用)
「子どもたちの遊び場が少ないので、毎週楽しみに参加している子どもたちが多くてよかった」
「公民館のない地域にも、公民館の雰囲気を味わうことができるのは素晴らしい」
「子どもたちが遊んでいるのを大人が見守る仕組みができていると感じました。また、定期的に公園に行くことができるので、公園の異変にも気づくようになったと思います」
「いろんな年代の方々と一つのものを作り上げる喜びがあり学びも多くありました」
「講座や場所ではなく『公民館』がほしい!」という熱い思い
「曙地域は若狭公民館の区域ですが、若狭公民館に来るには歩いて1時間以上かかります。近くに公民館がほしいと地域の方から要望をいただいたのですが、施設をつくるとなると予算的にもなかなか難しく、すぐにはできません。
そこで、公民館の『つどう・まなぶ・むすぶ』という機能を発揮できる場をどうすればつくれるかを考えました」
そう振り返るのは、若狭公民館の館長・宮城潤さん。若狭公民館はNPO法人地域サポートわかさが2010年度から業務委託、2015年度から指定管理者となって運営されていて、宮城さんはNPO法人の理事も務めています。
「最初、『出前講座ができますよ』とお伝えしたら、『そうじゃなくて、公民館がほしい』と言われたんです。では集まれる空間がほしいのかなと思ったのですが、すでに小学校に地域連携室というのがあった。
講座や場所じゃなくて、『公民館』がほしいと言うんです。正直、全国的に見ても公民館がこんなに熱望される地域って少ないと思うのですが(笑)、その言葉に隠された期待に、公民館の本質が隠されているんじゃないかと思いました」(宮城さん)
ニーズが言葉になるには時間もかかります。曙地域の人たちは、少し離れた若狭公民館で起こっていることをどこかうらやましく思っていたのかもしれません。その本質とは何なのでしょうか。
「いろんな世代が集まってつながって、地域の人たちで地域を作っていく。そのきっかけになる場や機会、そしてつなげる人がほしいということなんじゃないか。子どもの放課後の居場所がないのかもしれない。
月一回、その地域のまちづくり協議会に出席していたので、会議や会議の前後にいろんなおしゃべりをしながら、2年ほどの月日をかけて仮説を重ね、ようやくパーラー公民館をやってみることになりました」(宮城さん)
顔を合わせて対話を繰り返してもなかなかイメージは共有できない。じゃあとりあえずやってみるかとチャレンジしたと言います。
「普通なら、『よくわからないからやめよう』となりますが、曙地域では不思議と、『なんかわかんないけどまあやってみよう』となるんです。
曙小学校校長(当時)の真喜志昇(まきし・のぼる)先生やまちづくり協議会のみなさんがおもしろがってくださった。また、毎朝ラジオ体操を行っている『曙願寿会』会長で地域のキーパーソン、社会教育指導員の経験もある上原美智子さんが館長を引き受けてくださったことも大きかったと思います」(宮城さん)






















![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)