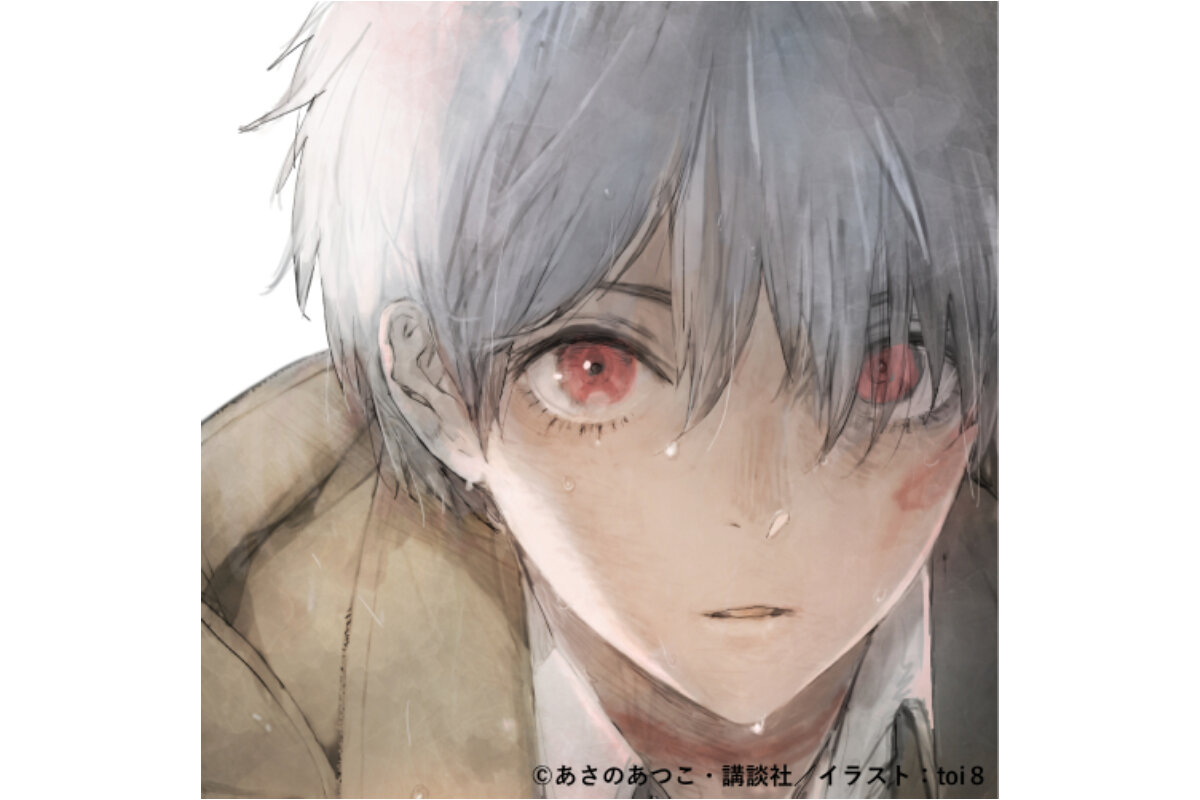子どもが「色覚異常」と診断されたら… 「色覚異常は“進化型“だ」作家・川端裕人が説く「色覚と進化のひみつ」に超ナットク
『いろ・いろ 色覚と進化のひみつ』著者 川端裕人さんインタビュー (2/3) 1ページ目に戻る
2025.08.09
色覚異常」の困りごとは「優劣」の問題ではない

──「色覚異常」の抱える問題について教えてください。
川端:進化型の色覚の人は、全体の中では少数派です。ヒトの歴史の中では、ほとんどの時代で、それが問題になることはなかったのですが、社会が近代化する中で、色覚の知識が十分ではないまま色を使った情報を伝えることがさかんになり、少数派の進化型には不利になってしまいました。
例えば、鉄道の信号などは、最初から知識があれば、だれもがわかりやすいものにすることができたはずなのです。しかし、実際には、進化型の人にはわかりにくいものが選ばれています。そうやって、多数派とは違うことを「異常」とされる素地ができてしまったんです。
実際は、少数派の進化型の人も、それぞれの見え方があります。多数派の見え方と、得意・不得意の違いはあっても、生きていくことについて過不足ないものです。でも、多数派が見ている色を前提にして、それに合わせなければならないことが多く、そのときに不利になってしまうのだと、まずは理解していただければと思います。これは、どちらがどちらに合わせるかという問題で、優劣の問題ではないんですよ。
最近では、色のユニバーサルデザインで環境を整えたり、スマホなどのデバイスを使って個人レベルで工夫をする方法もいろいろありますので、将来的に困りごとを減らしていけるかもしれません。これまでは、「異常」と診断されると、「わきまえて生きるように」と指導されることが多かったのですが、今後は、診断された人を勇気づけ、もっと実際の役にたつ支援が必要ではないかと思います。
そういった支援の足を引っ張らないためにも、「色覚異常」が生物学的には「異常」ではないことも、常識としたいところです。眼科もそろそろ、科学的には否定されている「異常」という理解も含めて、再考すべきだという提案が科学者側から出ています。