
70年以上「配置基準」変わらず

保育の定員枠が不足し、出産後の母親の復職の妨げとなっていた待機児童問題。今この記事を読んでいる方々にも、保活で涙し苦労を重ねた人は少なくないでしょう。
政府と業界の対策により待機児童の数は減少していますが、現在、保育の現場では別の問題が注目されています。それは「保育士の労働問題」と、それに大きく影響されるであろう、子どもたちが受ける「保育の質」です。
(編集部注:児童を保育する施設として「保育所」「認定こども園」があるため、この記事では「保育」で表記を統一しています)
日々成長する乳幼児たちを保育するには「責任」が伴い、身体的にも心理的にも、保育士たちは大きな負担を感じながら仕事をしています。ですが今の日本では、保育士の労働環境や処遇がその責任に見合わず、保育士たちが離職を選ぶ傾向が強くなっています。
資格を持ちながら保育士として働かない「潜在保育士」にその理由を尋ねたアンケートでは、「責任の大きさ・事故への不安」が16項目中第3位に上がりました。(厚生労働省※)
その要因として指摘されているのが、保育士の「配置基準」。
「保育士1人が何歳の子どもを何人まで保育できるか」を決めた、国の規定です。日本では他の先進国に比べ、この配置基準が低く、「保育士が1人で見なければならない子どもの数が多すぎる」と言われています。
4~5歳の配置基準、先進国で最低
「特に4~5歳は『子ども30人につき保育士1人』と先進国最低で、1948年に定められてから変わっていません。0~3歳は見直しがありましたが、それでも十分ではないと現場からは言われています。配置基準は保育士の待遇を左右しますし、保育の質に影響を及ぼすとの研究結果もあります。今の日本で、早急に改善すべき課題です」
そう語るのは、京都大学教授の柴田悠先生。保育をはじめとした子育て支援のより良いあり方を社会学的に研究し、その成果を論文や著書、国会などの場で発信しています。

先進国最低という日本の「保育士配置基準」は、どのようなものなのか。その配置基準はどのように作られ、どう現場で運用され、今日まで70年以上、変えられずに続いてきたのでしょう。柴田先生に伺います。
明確な科学的根拠のない配置基準
日本の保育士配置基準は、厚生労働省(以下、厚労省)の「児童福祉施設最低基準」の中で決められています。基準は、保育に通う子どもたちの年齢によって区切られており、年齢が高くなるほど、保育士1人が見る子どもの数が増えていきます。

保育士の配置基準そのものは、1948年に作られました。
第二次世界大戦後の社会混乱の中で子どもたちを保護する必要から、児童養護施設や乳児院が作られ、保育もその一環で、国としての基準が設けられました。
国は保育に運営補助金を交付しています。そのうち、「保育士の人件費」は、この配置基準をもとに計算されています。配置基準が低いほど、運営補助金で雇える保育士の数は少なくなる、という仕組みです。
それほど重要でありながら、この基準には、制定時から今までも、はっきりした論拠や裏付けは示されていません。その理由を、柴田先生は次のように指摘します。
「何人の児童に対して、何人の保育士を配置するのが望ましいか、に関する研究がそもそも少ないのです。それを科学的に測るための調査自体も、充分にされてきませんでした」
保育をめぐる社会の変化
明確な根拠なく決められた、日本の配置基準。しかもその見直しはなかなか行われず、0歳は1998年(25年前)、1~2歳は1967年(56年前)、3歳は1969年(54年前)、4~5歳は1948年(75年前)から変わっていません。親子の生きる日本社会や、保育利用者の状況は、明らかに変化しているにもかかわらず、です。
厚労省の統計によると、保育に通う子どもの数は、1956年から2022年で4倍以上になりました。
子ども全体の中での割合的にも増えていて、現在では1歳から5歳までの子どもたちの半分以上が、保育に通っています。

「1969年では、5歳児の7割が幼稚園もしくは保育を利用していましたが、保育児はそのうち2割弱でした。当時は両親ともフルタイムの共働きが少なく、通園時間の短い幼稚園を利用できる世帯が多かったのです。共働きが増えた現在、4~5歳では、幼稚園と保育に通う子どもたちの割合は、ほぼ半々になっています」(柴田先生)
そして、保育を利用する世帯には、数以外にも変化が起きています。
「1969年当時、保育利用世帯の7割は非課税世帯でした。ですが2014年には、その割合は2割ほどまで下がっています」
社会の中での保育の役割が、低所得世帯の保育の必要を補う福祉施設から、より多くの子どもたちの生活と成長の拠点へと、変わっているのです。
なぜ配置基準は変わらなかったのか
このような社会の変化に即して、保育士の配置の仕方は、いくつかの改善もありました。
たとえば、2012年には全国基準に加え、地域事情に合わせた最低基準を、都道府県が制定できるように。また2015年には、3歳児保育を対象に「児童15人につき保育士1人」を配置できるよう、国からの運営補助金が加算されています。
それでも根幹の配置基準は、頑として、不動のまま。ですが、保育現場や保護者たちからは、改善の声が上げられ続けてきたのです。なぜその声は、制度改正に繫がらなかったのでしょう?
柴田先生はその要因の一つに、「保育の利用世帯は、長いあいだ、社会のマイノリティだったこと」を挙げます。
「保育を利用する家庭は数が少なかったことに加え、生活に追われる人が多く、声を上げる余裕がありませんでした。また保育業界も『福祉施設』として、目の前の子どもたちに向き合う中、業界団体としての力をつけることができなかった。そのため、保育にゆかりの深い議員をあまり輩出できず、改善を求める声を上げ続けても、それを響かせることが難しかったと考えられます」
そして今、政治の世界にいる議員は、保育ではなく、幼稚園利用世帯の出身者が多いとも考えられます。その発言がどこか他人事のようだったり、保育児が少数派だった時代から認識が変わっていないと思わせるさまが、残念ながら見られます。
日本社会が大きく変わっても、動かない保育士の配置基準。その時代遅れの基準が及ぼす影響は、望ましくない形で、保育現場に表れています。それはどんなものなのか、改善策はあるのか。続く第2回「11人の人件費で15人が働く保育士たち 上がらない「配置基準」が生む負のループの記事で見ていきましょう。
引用・参考・出典
※保育人材確保のための『魅力ある職場づくり』に向けて(平成29年4月 厚生労働省)
厚生労働統計
保育所等関連状況取りまとめ(令和4年4月1日)
プロフィール
【柴田悠(しばた・はるか)京都大学大学院人間・環境学研究科教授。1978年、東京都生まれ。京都大学総合人間学部卒業、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。専門は社会学、社会保障論、幸福研究。同志社大学准教授、立命館大学准教授、京都大学准教授を経て、2023年度より現職。著書に『子育て支援と経済成長』(朝日新書、2017年)、『子育て支援が日本を救う──政策効果の統計分析』(勁草書房、2016年、社会政策学会学会賞受賞)、分担執筆書に『Labor Markets, Gender and Social Stratification in East Asia』(Brill、2015年)など。】
【髙崎 順子(たかさき・じゅんこ)ライター 1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)などがある。2023年5月に『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)を刊行予定。得意分野は子育て環境。】

髙崎 順子
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)などがある。得意分野は子育て環境。
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)などがある。得意分野は子育て環境。














































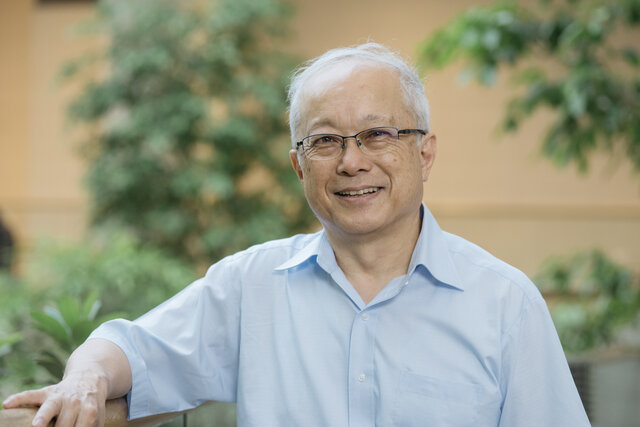


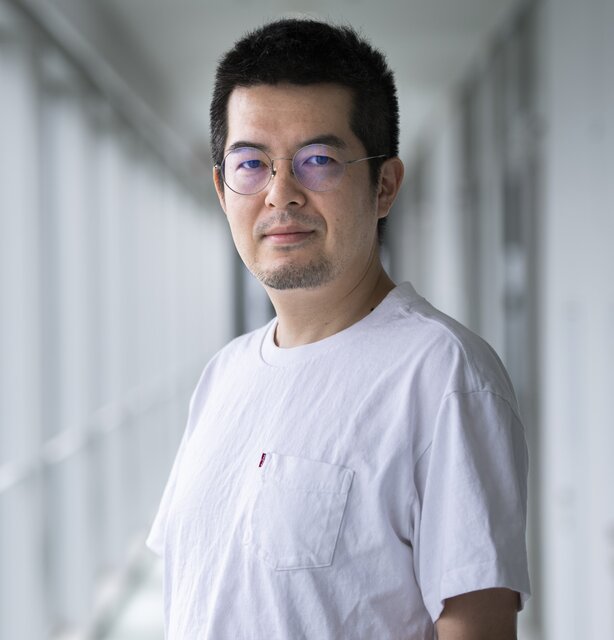


























































柴田 悠
京都大学大学院 人間・環境学研究科教授。1978年、東京都生まれ。京都大学総合人間学部卒業、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。専門は社会学、社会保障論、幸福研究。同志社大学准教授、立命館大学准教授、京都大学准教授を経て、2023年度より現職。著書に『子育て支援と経済成長』(朝日新書、2017年)、『子育て支援が日本を救う──政策効果の統計分析』(勁草書房、2016年、社会政策学会学会賞受賞)、分担執筆書に『Labor Markets, Gender and Social Stratification in East Asia』(Brill、2015年)など。
京都大学大学院 人間・環境学研究科教授。1978年、東京都生まれ。京都大学総合人間学部卒業、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。専門は社会学、社会保障論、幸福研究。同志社大学准教授、立命館大学准教授、京都大学准教授を経て、2023年度より現職。著書に『子育て支援と経済成長』(朝日新書、2017年)、『子育て支援が日本を救う──政策効果の統計分析』(勁草書房、2016年、社会政策学会学会賞受賞)、分担執筆書に『Labor Markets, Gender and Social Stratification in East Asia』(Brill、2015年)など。