

早期教育はいつからはじめたらいい? 効果はある? 発達心理学者が回答
こんなときどうする?子育てQ&A#36「早期教育って、いつからはじめたらいい?効果はあるの?」
2022.04.01
教育学博士:渡辺 弥生

1~3歳では「興味があるし、経験の一つとしてやらせてみようかな」というくらいの気持ちではじめて、ようすを見ながら進めるのがベストでしょう。

「早期教育って、いつからはじめたらいい? 効果はあるの?」(3歳・男の子)

二つの考え方とデメリット
一つは、教え方を工夫すれば、たとえば、小さな子も俳句が詠めるようになるし、3歳でバック転だってできるようになるという発想です。
そして、もう一つは、たとえば、ハサミづかい一つとっても、指を動かす機能が伸びているときに教えたほうが効果的。
つまり、発達が進む時期は興味も出てくるので、その段階ではじめるほうが能力の獲得が早いという考えです。
どちらも一理ありますね。
ただ、デメリットを知っておくことも必要です。期待をかけすぎたり、ほかの子と比べたり、嫌がるのに無理に習わせ続けたりすると、練習を嫌いにさせる可能性があるという点です。

習い事をはじめるときのポイント
スポーツ、外国語、音楽などで才能を輝かせる子、最近では中学生のプロ棋士も話題ですね。
彼らを見るたびに、早くから教えなくちゃと思うこともあるでしょう。
また、そこまでは望まなくても、人よりは少しは先をいかせたい、人より秀でなくてもいいから落ちこぼれないようにさせたいなどと考えるママもいると思います。
習い事は、子どもの経験を増やしてあげるという点で悪いことではありません。
ただ、先にお話ししたようにデメリットもあります。
1~3歳は、興味が「ある・ない」がはっきりしています。
そこで効果的な習い事の選択法としては、
①やりたがるものを選ぶ
子どもがやりたがるか、やっていて楽しそうにしているかを選択基準にしましょう。
②遊びの一部として楽しませる
子どもの能力は、自由な時間のなかで自発的に活動しながら伸びていきます。
それだけに、習い事に比重がかかって自由な遊び時間が減るのはマイナスです。
遊びの一部と考えて楽しませてあげたいものです。
③嫌がるときは休止する選択も
子どもが嫌がるときは、その習い事を本当に嫌いになる前にいったんやめるという選択も必要です。

早期教育の効果は? そして、大事なことは?
ただ、すべての子がそうではありません。
もし、「失うものはあっても才能を育てたい」などという強い気持ちがあれば別ですが、発達の旬をとらえて子どもの意欲にあわせてはじめたほうが上達はしやすいのは事実です。
1~3歳では、子どものようすを見ながら「経験の一つとしてやらせてみよう」という気持ちで進めていくと良いですね。
文/宇野智子 写真/Adobe Stock

げんき編集部
幼児雑誌「げんき」「NHKのおかあさんといっしょ」「いないいないばあっ!」と、幼児向けの絵本を刊行している講談社げんき編集部のサイトです。1・2・3歳のお子さんがいるパパ・ママを中心に、おもしろくて役に立つ子育てや絵本の情報が満載! Instagram : genki_magazine Twitter : @kodanshagenki LINE : @genki
幼児雑誌「げんき」「NHKのおかあさんといっしょ」「いないいないばあっ!」と、幼児向けの絵本を刊行している講談社げんき編集部のサイトです。1・2・3歳のお子さんがいるパパ・ママを中心に、おもしろくて役に立つ子育てや絵本の情報が満載! Instagram : genki_magazine Twitter : @kodanshagenki LINE : @genki












































































































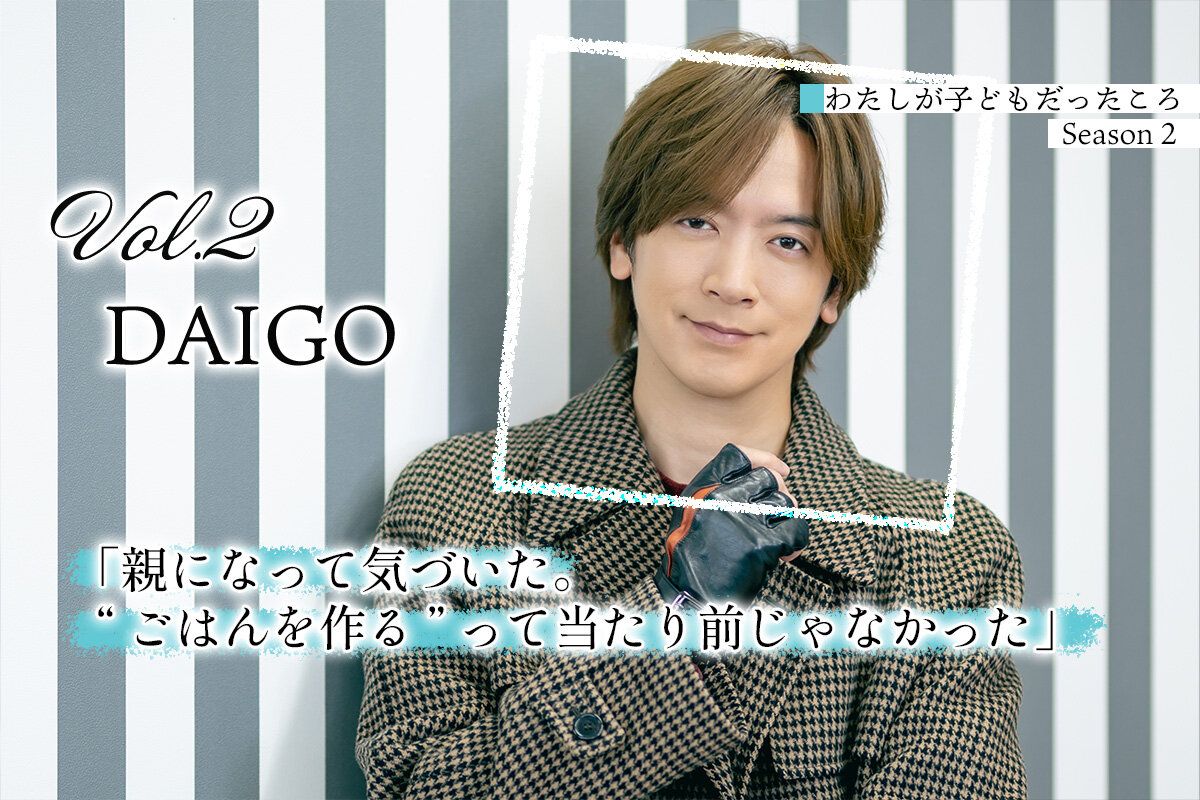









渡辺 弥生
大阪府生まれ。1983年筑波大学卒業。同大学大学院博士課程心理学研究科で学んだ後、筑波大学、静岡大学、途中ハーバード大学客員研究員を経て、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長兼務。教育学博士。専門は、発達心理学、発達臨床心理学。主な著書に『まんがでわかる発達心理学』、『11歳の身の上相談』(講談社)、『親子のためのソーシャルスキル』(サイエンス社)など。
大阪府生まれ。1983年筑波大学卒業。同大学大学院博士課程心理学研究科で学んだ後、筑波大学、静岡大学、途中ハーバード大学客員研究員を経て、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長兼務。教育学博士。専門は、発達心理学、発達臨床心理学。主な著書に『まんがでわかる発達心理学』、『11歳の身の上相談』(講談社)、『親子のためのソーシャルスキル』(サイエンス社)など。