

おもちゃを取られても何もしない気が弱い子 どうすべき? 専門家が回答
こんなときどうする? 子育てQ&A#69「おもちゃを取られてもしゅんとするだけの子。これでいいの?」
2022.06.17
教育学博士:渡辺 弥生

あとは、言葉で自分の気持ちを伝えられるようにしていってあげればいいだけです。
みんなが楽しく遊べるように、成長を支援してあげるのが大人の役割です。

「おもちゃを取られてもしゅんとするだけの子。これでいいの?」(3歳・女の子)

そのあとの対応が大切です
A=わが子を情けないと感じて叱咤激励する。
B=わが子をかわいそうに思い、「我慢してえらかったね」と、ほめるだけで終わらせる。
Aの場合、「イヤならイヤといいなさい!」などと強い口調でいうのは避けたいもの。
これでは、ママパパに叱られたことのほうにショックを受けてしまいます。
また、「情けない子」「弱虫な子」などという言い方も問題です。
「自分は弱虫で情けない子」と、子どもに暗示をかけてしまいます。
Bの場合、子どもの気持ちに共感することは大切です。
でも、「我慢したことをほめる」だけで終わっては、子どもの不本意な気持ちを押さえつけることになってしまいます。
また、相手の子を「悪い子ね」などと白黒つけるのもやめましょう。
相手もまだ未熟な子どもです。
わが子を含めて子どもたちみんなが楽しく遊べるように、成長を支援していってあげるのが大人の役割です。

具体的にはどうしたらいいの?
1.自分の気持ちを伝える大切さを学べるようにしていく。
2.子どもたちが楽しく一緒に遊べるように工夫していく。
1~3歳の子どもは、まだ自分の気持ちをうまく言葉で伝えられませんが、今から教えていけば、次の成長の段階でその教えが生きてきます。
具体的には、
①まず、共感して一緒に考える
「悲しかったね。でも、どうしたらよかったのかな?」と、子どもにも考えさせる言い方をしてみましょう。
②答えはママパパがいってあげる
たとえば、「返して(ダメ、ヤメテなど)といったら返してくれるかもしれないよ」というふうに、言葉で「NO」を伝える大切さをアドバイスします。
実際には、そういったからといって返してくれないかもしれませんが、「言葉での意思表示が大事」なことを教える機会にしましょう。
③ママパパが代わりに相手の子に伝える
ママパパが相手の子に「まだ、それで遊びたいんだって。(違うおもちゃを出して)これと交換して、それは返してくれるかな」などと伝えてかまいません。
それでも返してくれないときは、「じゃあ、一緒に遊ぼう」と、二人を違う遊びに誘って、とりあえずそのおもちゃから二人の気持ちをそらしてしまいましょう。
公園は子どもの社会性を伸ばせる場所です。
大人が仲介役になって、必要なことを学ばせながら、子どもたちが楽しく遊べるように対応していってあげるのがベストなのです。
文/宇野智子 写真/Adobe Stock

げんき編集部
幼児雑誌「げんき」「NHKのおかあさんといっしょ」「いないいないばあっ!」と、幼児向けの絵本を刊行している講談社げんき編集部のサイトです。1・2・3歳のお子さんがいるパパ・ママを中心に、おもしろくて役に立つ子育てや絵本の情報が満載! Instagram : genki_magazine Twitter : @kodanshagenki LINE : @genki
幼児雑誌「げんき」「NHKのおかあさんといっしょ」「いないいないばあっ!」と、幼児向けの絵本を刊行している講談社げんき編集部のサイトです。1・2・3歳のお子さんがいるパパ・ママを中心に、おもしろくて役に立つ子育てや絵本の情報が満載! Instagram : genki_magazine Twitter : @kodanshagenki LINE : @genki










































































































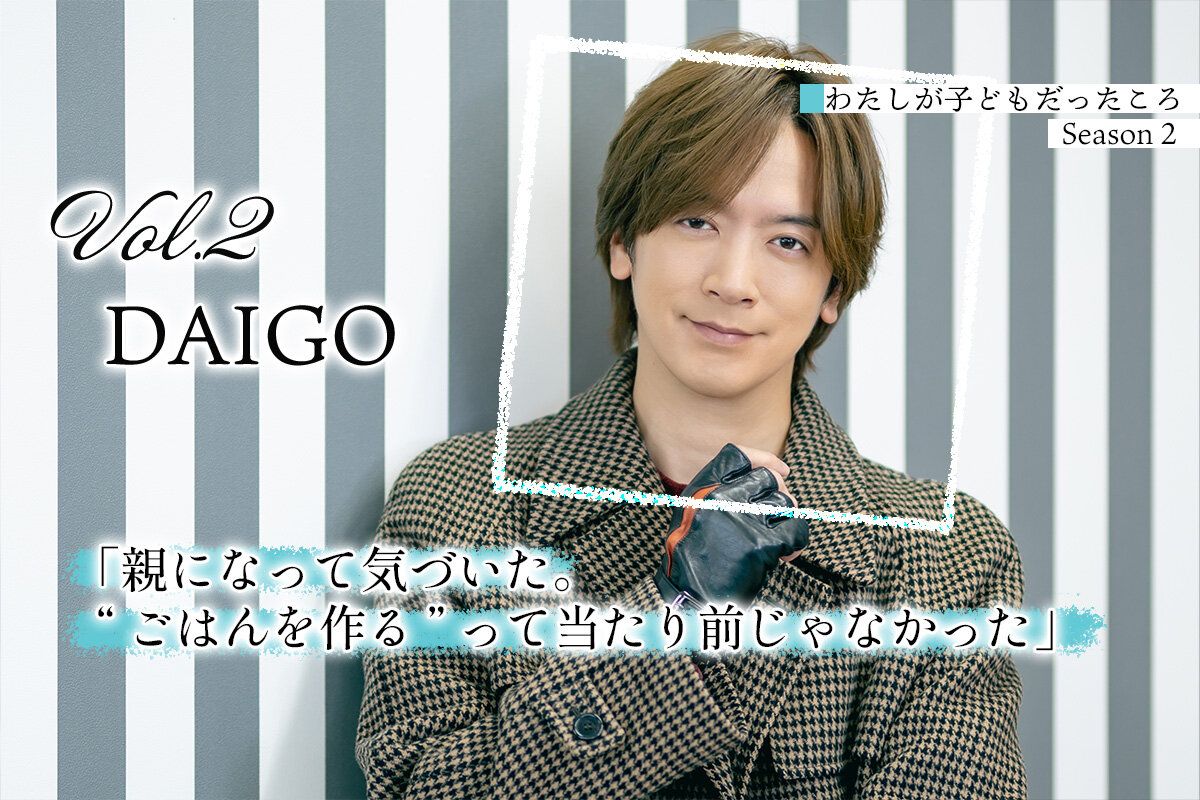









渡辺 弥生
大阪府生まれ。1983年筑波大学卒業。同大学大学院博士課程心理学研究科で学んだ後、筑波大学、静岡大学、途中ハーバード大学客員研究員を経て、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長兼務。教育学博士。専門は、発達心理学、発達臨床心理学。主な著書に『まんがでわかる発達心理学』、『11歳の身の上相談』(講談社)、『親子のためのソーシャルスキル』(サイエンス社)など。
大阪府生まれ。1983年筑波大学卒業。同大学大学院博士課程心理学研究科で学んだ後、筑波大学、静岡大学、途中ハーバード大学客員研究員を経て、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長兼務。教育学博士。専門は、発達心理学、発達臨床心理学。主な著書に『まんがでわかる発達心理学』、『11歳の身の上相談』(講談社)、『親子のためのソーシャルスキル』(サイエンス社)など。