

子どもが「友だち」で悩んだときに 親がそっと手渡したい「心が軽くなる本」の処方箋
出版ジャーナリスト・飯田一史が選ぶ、心の処方箋 第6回 「友だち付き合いに悩んだときに読む物語」 (3/3) 1ページ目に戻る
2025.11.04
ライター:飯田 一史
③『友だちがしんどいがなくなる本』

著:石田光規(講談社)
Amazonを見る↓
今の「友だち」関係とはどんなものになっているか、を知るのには、物語以外の本も有効です。社会学者の石田光規さんが中高生に向けて書いた『友だちがしんどいがなくなる本』は、物語と現実の友人関係がどう違うのかを理解する手がかりになります。
石田さんが本の中で直接そう表現しているわけではありませんが、この本で書かれているのは、「今の世の中では、友人関係も仕事で付き合うような人たちとの人間関係とあまり変わらなくなってきている」ということ。

石田さんは、スマホが発達する前は「友だち」か、そうでないかの境目ははっきりしていなかった、と指摘しています。学校や街中にある「たまり場」のような場所になんとなく集まる人たちが仲間、友だちという感じだった。
それが今では、特定のLINEグループに入っているかどうかによって「友だち」かどうか、また「どのくらい大事な友だち」なのか、「何についての友だち」なのかが線引きされ、目に見えてわかるように変化。「特定の趣味についてだけ話す友だち」などもいるわけです。
また、昔と違って学年や学級、あるいは部活動などで「全員参加の○○」のような「強制的な集まり」の機会が減っているがゆえに、積極的に自分から友だちを「つくる」ことをしないと人間関係ができづらくなっている、とも指摘しています。
いったん人間関係ができたあとも、放っておいてもしょっちゅう顔を会わせるようなものではなくなっているため、こちらから働きかけなければ自然と遠ざかりますし、相手からの誘いや連絡への態度次第では「あの子はレスが悪いから」といった理由で輪から外されてもいきます。
つまり、結構がんばらないと「ずっと続く友人関係」はない、ということです。
理想的には今も昔も「損得なしで付き合える」のが友情だと思われています。フィクションでもそういう美しいものとしてよく描かれています。けれど実際には仕事の付き合いと同じで、相手側にコミュニケーションを取るメリット、会う理由を提示できなければ、維持していくのはむずかしいのです。
マンガや小説で描かれるようなきれいな親友関係は現実にはとてもとても珍しく、その辺にゴロゴロ転がっているものではありません。でも、「そういうもの」なのだと知れば「マンガに出てくるような『親友』がいなくても普通のことなんだ。自分だけじゃないんだ」と安心できる部分もあるでしょう。
「なんでもわかりあえる親友」なんて幻想なのであって、現実には「学校で会う友だち」「塾で会う友だち」「SNSでつながっている知り合い」など特定の場やサービスと紐付いた人間関係があるだけ──。そう思えれば、学校で友だちがいないとか、不登校だから同年代の友だちがいないといったことも、そこまで深刻に感じる必要もなくなります。
どうせ学校での人間関係など何年も続くものではないのだから、我慢しすぎなくてもいい。気が合う人が見つかったら、積極的に働きかけて続けていけばいい。そう割り切れば、気はラクになります。
④『あらしのよるに』

著:木村裕一、絵:あべ弘士
Amazonを見る↓
「現実と物語は違うから、物語には意味がない」と言いたいわけではありません。
ここまで紹介してきた作品は、現実の人間関係にひきつけて(も)読める、素晴らしい物語です。また、必ずしもリアルな人間模様を描いた作品ではないけれど、友情をテーマにしたフィクションとして完成度が素晴らしい作品もあります。
今年、20年ぶりに新シリーズが始動した『あらしのよるに』シリーズは、後者の代表的なものだと思います。アニメ化もされたロングセラーですからご存じの方も多いでしょう。
オオカミのガブとヤギのメイ、捕食者と食べられる側の2匹があやうい関係のなかで、まわりから何かと干渉されながら、また、オオカミが本能に負けそうになりながらも、友情をはぐくんでいく感動的な物語です。
物語と現実の両方に触れることが、揺れる心を支える力になります。物語は、つらいときの心の避難場所となり、一方で現実を分析した本は「理想どおりでなくても大丈夫」と思わせてくれる、心のお守りになってくれるでしょう。
文/飯田一史
【好評連載】出版ジャーナリスト・飯田一史のこの本おススメ! 過去記事はこちら
【関連リンク】




















![【働くママの労働問題】「103万円の壁 結局どうなったの?」扶養内パートで働く場合・働かない場合の話[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/043/679/large/5e312970-2201-4f0f-9b80-fdf7e7a9560b.jpg?1759906116)



![【働くママの労働問題】「103万円の壁 結局どうなったの?」働いている人みんなに関係する話[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/043/678/large/b29b4c9e-58ce-47b6-8318-51f8f37e7e2c.jpg?1759906203)






















































































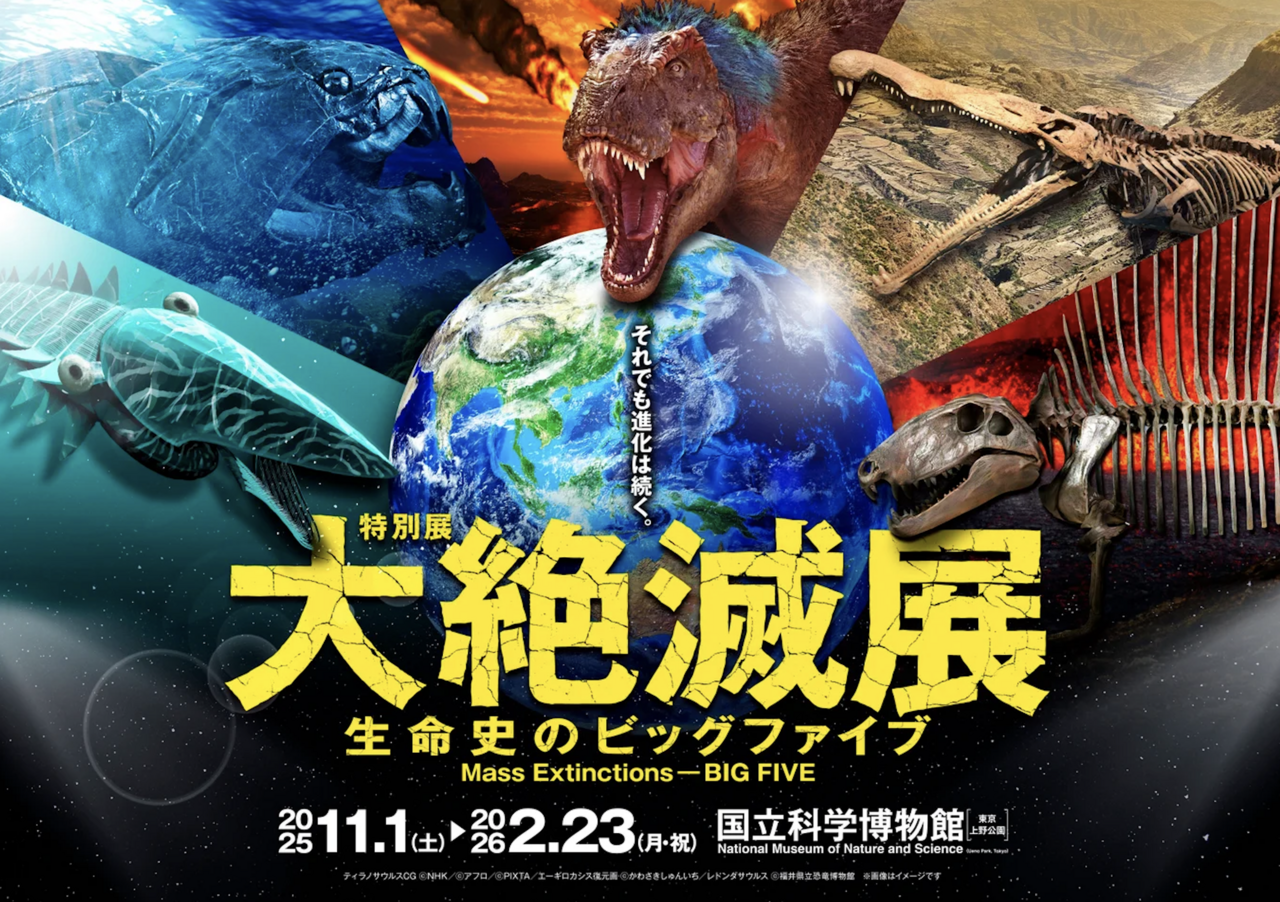


飯田 一史
青森県むつ市生まれ。中央大学法学部法律学科卒。グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了(MBA)。 出版社にてカルチャー誌や小説の編集に携わったのち、独立。国内外の出版産業、読書、子どもの本、マンガ、ウェブカルチャー等について取材、調査、執筆している。 JPIC読書アドバイザー養成講座講師。 電子出版制作・流通協議会 「電流協アワード」選考委員。インプレス総研『電子書籍ビジネス調査報告書』共著者。 主な著書に 『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』 『「若者の読書離れ」というウソ』 (平凡社)『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの?』(星海社)『ウェブ小説30年史』(講談社)ほか。 ichiiida.theletter.jp
青森県むつ市生まれ。中央大学法学部法律学科卒。グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了(MBA)。 出版社にてカルチャー誌や小説の編集に携わったのち、独立。国内外の出版産業、読書、子どもの本、マンガ、ウェブカルチャー等について取材、調査、執筆している。 JPIC読書アドバイザー養成講座講師。 電子出版制作・流通協議会 「電流協アワード」選考委員。インプレス総研『電子書籍ビジネス調査報告書』共著者。 主な著書に 『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』 『「若者の読書離れ」というウソ』 (平凡社)『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの?』(星海社)『ウェブ小説30年史』(講談社)ほか。 ichiiida.theletter.jp