

「山で死なない」2大鉄則 「自力で対処できなければすぐに救助要請・登山届と山岳保険」…山岳遭難防止アドバイザーが解説
公的な救助費用の自己負担は基本0円、遭難時のOK行動とは〈山での危険を防ぐ#3〉
2024.08.29

目次
山で事故に遭ったり遭難したりしたときに、真っ先に思い浮かぶのが「救助要請」。2024年も富士山をはじめ、日本各地の山で救助要請が頻発している。
救助や捜索を行うのは、基本的に警察と消防だが、救助を要請した場合「費用」は発生するのか。また、どんなタイミングで要請するのが良いのか。遭難した場合、どんな行動を取るのが適切か。また、救助されたときに「救助費用」は発生するのか。
長野県山岳遭難防止アドバイザーであり、女子高校生の遭難事故をテーマとした小説『6days 遭難者たち』(著:安田夏菜)の監修も手掛けた羽根田治さんに、山で死なないための救助要請2つの鉄則と、初心者や親子で楽しめる山を紹介してもらった。

【羽根田 治(はねだ・おさむ) 山岳遭難や登山技術に関する記事を発表する一方、沖縄、自然、人物などをテーマに執筆活動を続ける。主な著書に「ドキュメント遭難」シリーズ、『人を襲うクマ』『十大事故から読み解く山岳遭難の傷痕』『これで死ぬ』(すべて、山と溪谷社)など。2013年より長野県山岳遭難防止アドバイザーを務める。日本山岳会会員】
「自力で対処できないと判断したらすぐに救助要請」救助要請の鉄則1
──山で事故に遭ったり遭難したりした場合は、どんなタイミングで救助を要請するのがよいのでしょうか?
羽根田治さん(以下、羽根田):基本的に登山というものは、自分の足で登って、登山中に遭遇するトラブルやアクシデントに自分たちで対処し、解決して、自らの足で下りてくるというのが本来の姿であると思います。
しかし、自分たちだけでは対処できない事態になったとき、また自力で山を下りられないと判断した場合は、すぐに救助要請をしてほしいなと思います。
──実際にケガをして動けなくなった場合は、どんな手順で救助要請をすればよいでしょうか。
羽根田:ケガの程度や状態にもよりますが、救助要請をする前にまず「安全な場所に移動」しましょう。そこで気持ちを落ち着かせてから、携帯電話が使えるのであれば、「110」か「119」に電話をして救助を要請してください。電話が繫がった後は、警察や消防の指示に従って救助を待ちましょう。
※参考:山岳医療救助情報「救助要請の仕方」
https://sangakui.jp/medical-info/cata03/medical-info-349.html
──羽根田さんが監修をした『6days 遭難者たち』(著:安田夏菜)に、「救助を頼むとすごくお金がかかる」と救助要請を躊躇する描写が出てきます。実際に、救助費用を支払うことはありますか?
羽根田:日本国内の行政による山岳遭難救助に関しては、埼玉の一部エリア(※)を除いて、原則、当事者負担はありません。つまり、警察や消防が出動した場合、かかった費用は税金でカバーされるので、基本的には無料です。
【※埼玉県では、2018年に一部山岳エリアでの防災ヘリが出動を有料化。救助のために飛行した時間5分ごとに8000円の費用を、手数料として納付する条例がある(2024年4月1日に料金改定)】
──地域住民だけでなく地域外からの観光客、外国人観光客からの救助要請も、基本は無料で行っているということですね。
羽根田:ただし、例外があります。警察や消防では人手が足りなかったり、現場により早く到着できる民間救助隊員がいる場合は、警察や消防から、民間救助隊に協力を依頼するケースもあります。
そうなると、民間救助隊に当事者が実費を支払うことになります。
今は民間のヘリコプターが出動する機会はほとんどありませんから、救助費用に何百万もかかることは稀です。
ただし民間救助隊に支払う費用は、少なくて数万円、日数と人数によって数十万円くらいかかるケースがほとんどです。安くはない金額ですが、命に関わることですから、そこは致し方ないと思います。
──山に入る前に、救助についての知識も必要ですね。迷惑かけたくない、お金がかかると考えて救助要請を我慢するのではなく、無理だと思ったら迷わず救助要請するのが、鉄則だということですね。
羽根田:はい。ただし行方不明になった場合、警察や消防の捜索はだいたい3~4日、長くて1週間です。その期間内に見つからず、家族がどうしても諦められないという場合には、捜索に特化した民間捜索隊に依頼することになります。
しかし、調査期間が長引くほど費用もかかります。ですから、まずは命を第一に考えた行動をしてください。
「山岳保険に入り登山届を提出する」救助要請の鉄則2
──救助要請する事態になったときに備えて、登山前にやっておくとよいことはありますか?
羽根田:登山の計画を家族と共有し、登山届(登山計画書)を必ず提出することです。登山届の提出は原則的に義務ではありませんが(※)未提出のまま山に入り、遭難したり救助要請をしたりするケースがあとを絶ちません。
【※自治体によっては条例によって登山届の提出を義務づけているところもある】
登山届を作成して提出するメリットは2つあります。
1つ目は、計画を立てることで、事前にルートや装備などの再確認ができること。入念に下調べをしておけば、遭難事故やケガのリスクを減らすことができるでしょう。
2つ目は、登山計画を家族に知らせておけば、遭難した場合でも早めに救助要請をしてもらえる可能性が高いこと。
「下山予定時刻を過ぎても連絡がない」「帰宅しない」という家族の通報がきっかけで遭難したことが発覚し、救助活動が開始されるケースが非常に多くみられます。
逆に通報がない場合は、遭難したことさえわからずに、初動に大きな遅れが出てしまいます。特に単独で登山をする人は、必ず家族や知人に登山計画書を残しておきましょう。

羽根田:実はご家族が「どこの山に行ったのかもわからない」というケースも少なくありません。そうなると警察も捜しようがなく、発見されるまでに時間がかかり、助かる確率はかなり下がってしまいます。
──「単独登山」と聞くとかっこいい趣味のように感じますが、やはり家族や周囲の人に情報を知らせておくのも大事ということですね。
羽根田:もうひとつ大事なのは、万一のときの経済的負担を考えて、「山岳保険」に加入することです。
「山岳保険」は、1日単位で加入できるものから年単位契約のものまで、各社さまざまなプランがありますので、自分の登山スタイルに合ったものを選んで、加入しておくとよいでしょう。
初心者親子登山におすすめの長野県の山7選
──長野県山岳遭難防止アドバイザーを務めている羽根田さんがおすすめする、初心者親子登山にピッタリの山を教えてください。
羽根田:親子登山の場合は、子どもの体力に合わせた「行動時間が短く、危険箇所がない」山を選びましょう。
標高が高い山でも、ロープウェイなどの交通機関があるところもあります。そういった乗り物を利用して山に登り、駅の周辺を散策して、高い場所からの景色を眺めるだけでも、十分楽しめるのではと思います。
爽やかな高原状の広がりがある山もおすすめです。それらを満たした場所でおすすめは、志賀高原、北八ヶ岳、霧ヶ峰、美ヶ原高原など。それから北アルプスの山麓部にある栂池(つがいけ)高原や上高地。
標高は高いけれど、かなり上のほうまでバスで行ける乗鞍岳もよいでしょう。また、手軽に登れて展望がよい入笠山(にゅうかさやま)もおすすめです。
「子どもから目を離さない、見つけやすい服を着せる」親子登山の鉄則
──親子登山での注意点を教えてください。
羽根田:もっとも大事なのが「子どもから目を離さない」こと。
家族で登山をしていた11歳の男の子が「先に行く」とひとりで山頂に向かったまま行方不明になり、死亡した事故がありました。キャンプ場で子どもが行方不明になった事件も、親が目を離した隙に起きています。

(画像『子ども版 これで死ぬ 外遊びで子どもが危険にあわないための安全の話』より)
──はしゃいで走りだしてしまう子もいると思いますが、できる限り目を離さず、いっしょに行動するのがよいということですね。
羽根田:はい。登山の前に大人といっしょに行動することや、万が一はぐれてしまったときにどうするかなど、親子で約束しておくのも大切です。
また低山や初心者向きの山でも、登山道の谷側が崖になっているところもあります。特に小学校低学年ぐらいまでの子どもと歩く場合は、大人が谷側、子どもは山側を歩くと事故防止につながります。
──服装の注意点はありますか?
羽根田:天候や体温の変化に応じて着たり脱いだりできるように、夏でも長袖の上着を用意するなど、基本的な注意事項は大人も子どもも同じです。
あえて挙げるとしたら、自然にはない「蛍光色」、「赤」や「青」などの原色系の色だと、自分の子どもがどこにいるのか見つけやすくなると思います。逆に「黒」は目立たないし、ハチにも刺されやすくなりますので、避けましょう。
子どもを危険な目に遭わせないように気をつけるのは、保護者の責任でもあります。子どもといっしょに準備や計画をするのも、よいと思いますよ。
【羽根田治さんに「山での危険を防ぐ」アドバイスを伺う連載は全3回。第1回で「富士山」をテーマに死なない・遭難しないための鉄則を、第2回では「熊」をテーマに危険を防ぐアドバイスを解説していただいたのに続き、最後となるこの第3回では「遭難」した際にとるべき行動について教えていただきました。
自然豊かな山には、普段住んでいる町とは違う危険があります。自分の命を守ってくれるのは、しっかりとした準備と安全な登山計画。登山をする全員で知識を共有し、親子で安全な登山を楽しんでほしいですね】
(取材・文/中村美奈子)
山について深く知る 羽根田治さんの本
山での事故や危険について、より深く知ることができる、羽根田治さんの著書・監修書を紹介します。
羽根田治さん監修の本


羽根田治さん著作の本




中村 美奈子
絵本サイトの運営に関わり、絵本作家への取材も多数。また漫画、アニメ、映画、ゲーム、アイドルなど幅広いエンターテインメントジャンルで記事を執筆。漫画家や声優、役者、監督、クリエイターなど、これまでに200名以上へのインタビューを経験している。
絵本サイトの運営に関わり、絵本作家への取材も多数。また漫画、アニメ、映画、ゲーム、アイドルなど幅広いエンターテインメントジャンルで記事を執筆。漫画家や声優、役者、監督、クリエイターなど、これまでに200名以上へのインタビューを経験している。












![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)

![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)
















































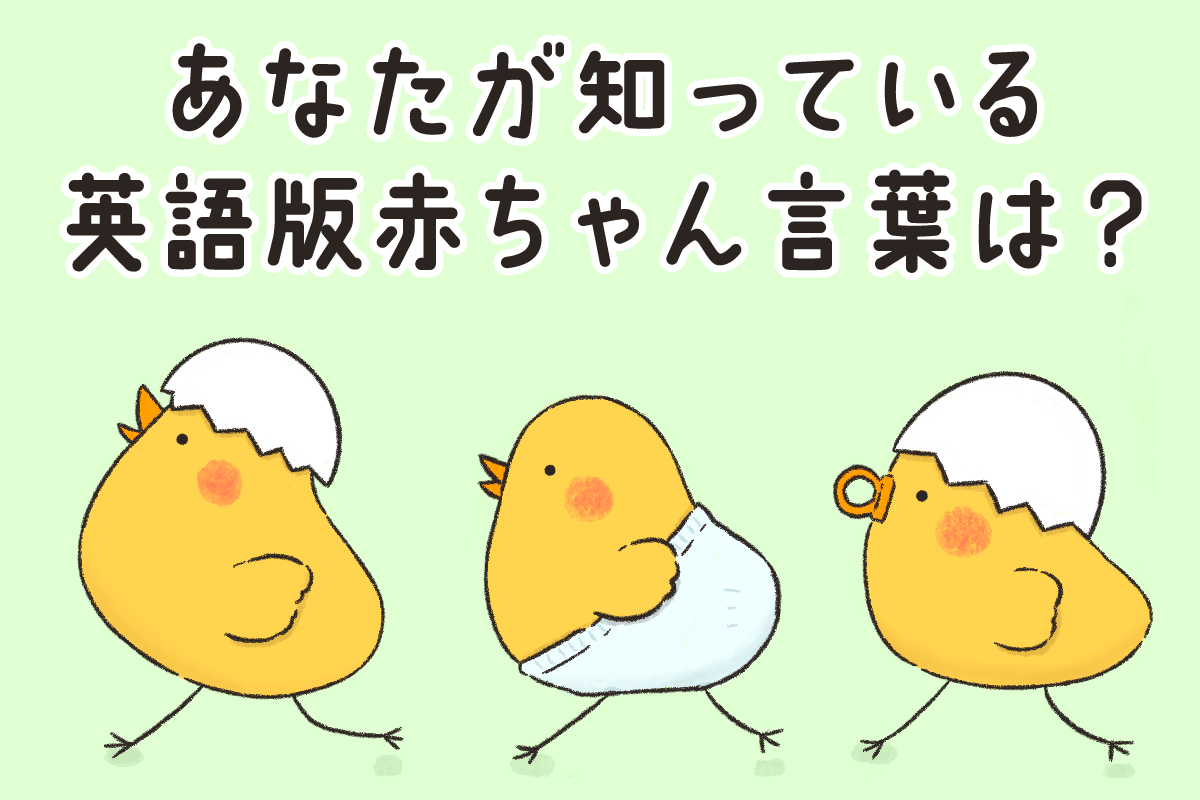

















































羽根田 治
1961年、さいたま市出身、那須塩原市在住。フリーライター。山岳遭難や登山技術に関する記事を山岳雑誌や書籍などで発表する一方、沖縄、自然、人物などをテーマに執筆活動を続ける。主な著書にドキュメント遭難シリーズ、『ロープワーク・ハンドブック』『野外毒本』『パイヌカジ』『トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか』(共著)『生死を分ける、山の遭難回避術』『人を襲うクマ』『十大事故から読み解く山岳遭難の傷痕』などがある。近著は『山はおそろしい』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)『これで死ぬ』(山と溪谷社)など。2013年より長野県山岳遭難防止アドバイザーを務め、講演活動も行なう。日本山岳会会員。
1961年、さいたま市出身、那須塩原市在住。フリーライター。山岳遭難や登山技術に関する記事を山岳雑誌や書籍などで発表する一方、沖縄、自然、人物などをテーマに執筆活動を続ける。主な著書にドキュメント遭難シリーズ、『ロープワーク・ハンドブック』『野外毒本』『パイヌカジ』『トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか』(共著)『生死を分ける、山の遭難回避術』『人を襲うクマ』『十大事故から読み解く山岳遭難の傷痕』などがある。近著は『山はおそろしい』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)『これで死ぬ』(山と溪谷社)など。2013年より長野県山岳遭難防止アドバイザーを務め、講演活動も行なう。日本山岳会会員。