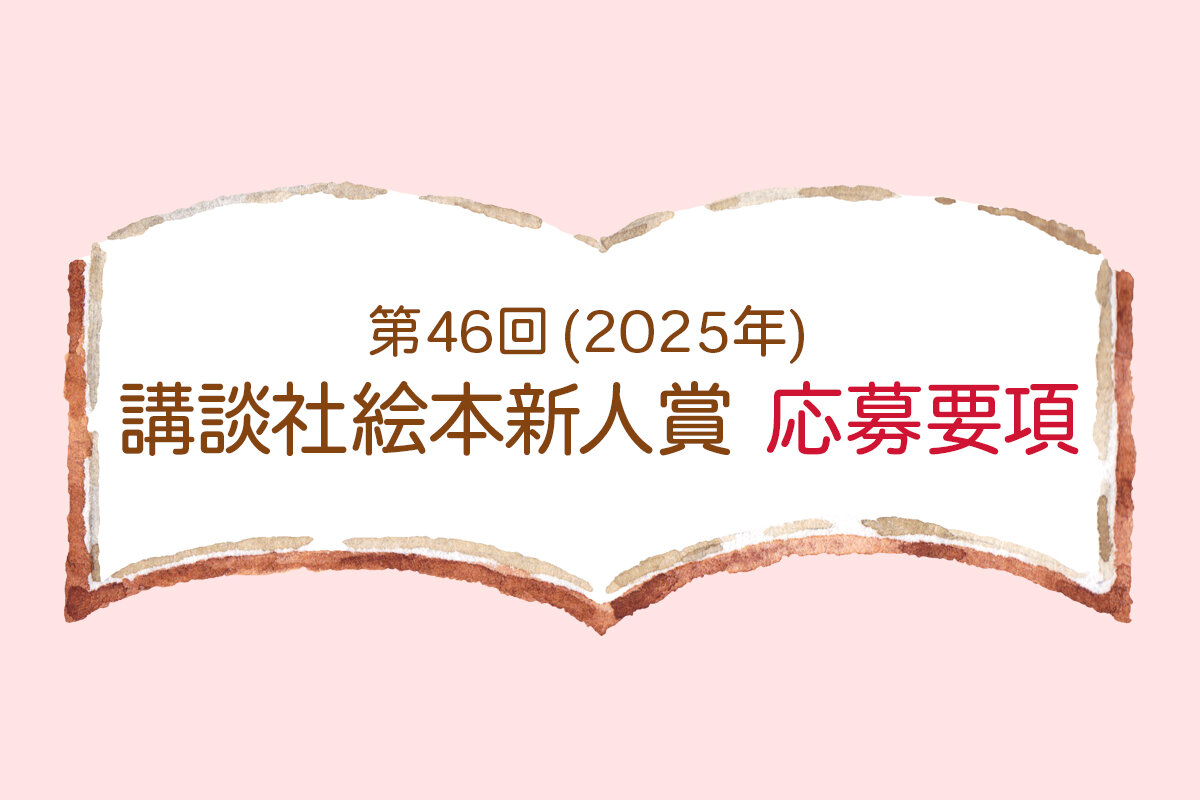


江戸のエコライフを絵本にしたい
私は札幌に住んでいまして、4年ほど前から小別沢というところで仲間と畑を借りて作物を作っているんですね。市民農園のように小さく区切られた畑をそれぞれで借りるのではなく、大きな畑で小麦や大豆、じゃがいもなどを作っていて。そこでは化学肥料には頼らず、動物の糞を肥料にしています。近くの「やぎや」というレストランで飼っているヤギの糞や、円山動物園のゾウの糞を堆肥として活用しているんです。


ある日、畑で農作業をしていてひと息ついて、手ぬぐいで汗を拭いていたら、畑にさあーっといい風が流れてきて。気持ちいいなぁと感じたのと同時に、ふと“江戸”を感じたんです。江戸ではリユースやリサイクルが当たり前でした。そのことを絵本にしたいなと。そのときそばにあったのが手ぬぐいだったので、手ぬぐいを主人公にしようと決めました。
落語が好きで、池波正太郎の時代小説なんかも好んで読むので、江戸文化については多少は知っているつもりでしたが、お話を作るにあたって改めて調べました。深川江戸資料館にも足を運んで調べていくと、まだまだ知らないことがたくさんあって。
手ぬぐいは、ぼろぼろになるまで使い込むのは当たり前で、燃えて灰になってもまだ活用できるんです。すべてが無駄なく生かされているのが素晴らしいなと感じて、お話の中に盛り込んでいきました。

豆絞りの模様を一点一点描く
そうなんです。大まかなストーリーは変わらないんですが、最初は“はっつぁん”という男の人の手ぬぐいを主人公にするつもりでした。でも、メインの登場人物が江戸時代のおじさんというのは、子どもが読むにはどうなんだろうと思って(笑)。それで、おじさんはやめて“たろう”という子どもにしようと考えたんですが、江戸時代の子どもってちょっと不思議な髪型をしてるんですよね。それをそのまま描くと、読む人がびっくりしてしまうかもしれないなと。
この絵本の企画がスタートしてから我が家で猫を飼い始めたこともあって、最終的に猫の子ども“ねこきち”の手ぬぐいを主人公にしました。我が家の猫・小太朗はハチワレではないんですが、色合い的にはねこきちと少し似ています。小太朗をモデルに子猫の様子を想像しながら、ねこきちを描いていきました。


物を主人公にする場合、顔をつければ絵本らしく引き立つと思うんですね。私もこれまでの絵本では、しゃもじや瀬戸物のかめ、消しゴムや鉛筆、のりなど、さまざまな物に顔を描いて、擬人化させてきました。
ただ今回は、手ぬぐいに顔を描くのはなんだか違うなぁと思っていて。顔は描かずに主人公として際立たせるにはどうすればいいだろうと考えた結果、手ぬぐいだけを布で表現しようと思い立ちました。
手ぬぐいは、さらしに自分で模様を描いています。
絵のサイズに合わせてそれぞれ作ったので、サイズはさまざまです。原画はほぼ原寸なので、本当に小さなものから半ページの大きなサイズまで。豆絞りの手ぬぐいは、さらしに筆でひたすら点々を描きました。老眼鏡が必需品でしたね(笑)。
ねこきちの豆絞りだけでなく父ちゃん母ちゃんの手ぬぐいも、原画の数だけ作る必要があって。やり直しも含めると、全部で何枚になったのか自分でも把握できないくらいたくさん作りました。

ねこきち一家は別の紙に描いて、手ぬぐいをひっかけるようにして、雲や小道具的なものも含めて背景の絵の上に貼り付けています。それを印刷所の水平移動するカメラで真上から撮影して、原画として取り込んでもらいました。よく見ると切り貼りした部分にはちょっと影もあって、立体的なのがわかるかと思います。
物干し竿に手ぬぐいが干してある場面です。深川江戸資料館では、江戸時代の町並みを実物大で見ることができるんですが、そこで長屋の裏手に物干しがある風景を見たんですね。それで、物干し越しに縁側の様子を描きたいなと思っていたんです。
物干しから縁側まで少し距離があるので、物干し部分は別の紙に描いているんですが、遠近感がうまく出せるかよくわからなくて、難しかったですね。最終的に上に置いて撮影することで、手前の物干し竿に手ぬぐいがかかっている雰囲気が出せたのでよかったです。

最後の凧あげの見開きです。ここは、「燃えて灰になったら、ねこきちにはもう会えない……」と沈んでいた手ぬぐいの気持ちが、「まだ役割はある。ねこきちのところへ戻れる」と切り替わるシーンでもあるんですよね。手ぬぐいの気持ちに合わせて、江戸の風景がぱあーっと広がるように描きました。浮世絵でも、凧あげをしているお正月の絵がいくつかあるので、そういったものを参考にしながら描いています。

毎日の暮らしの中で大事にしたいこと
古いもの、使い込まれたものの美しさには惹かれますね。あとさき塾で絵本作りを学ぶために東京で暮らし始めた頃は、アルバイトするなら古いお蕎麦屋さんがいいと思って、池波正太郎が愛した神田まつやでバイトしていました。ああいう江戸の風情みたいなものに魅力を感じます。
あと、今は本当に使い捨てが多いなと思っていて。物を大事に使うって、私も言うほどできていないんですが、そんな自分への自戒の念も込めて描いているようなところもありますね。
着物は、この絵本を描くにあたって着るようになりました。江戸の話を描くとなると、絶対着物が出てきますよね。でも着物のことがちゃんとわかっていないと、この動きのときに袖はどうなっているのかとか、そういうことがわからないんですよ。わからないと描けないので、着付けの先生に習いに行って、なんとか着られるようになったんです。この絵本の原画を描いていた間は、ほぼ毎日着物を着ていました。
着物を着ると動きが制限される分、所作も変わってくるんですよね。動きが違うと、きっと考え方も違ってくるんじゃないかなと思っていて。足下だって、靴ではなくて草履だと歩き方も変わってくるじゃないですか。せっかく江戸の話を描くので、そうやって見た目を変えることで、気分だけでも江戸に近づけるようにしていました。

リユースやリサイクル、SDGsを声高に推奨したいわけではなくて、江戸ではそういったエコライフがもっと自然に実践されていたということを知ってもらえたらと思っています。
便利さや企業利益を追い求めた結果が今の世の中で、使い捨てが当たり前だったり、使い捨てを減らそうと言いながらも何か買えばプラスチックがついてきたりと、日々の暮らしの中でいろんな矛盾を感じていますが、そんな中でも私たちにできることはあると思うんですよね。
物にはそれぞれ役割があって、使い終えてもまた次へと繫げて、循環させていくことができるはず。そういうことを根底で知っていると、自分のことももっと大事にできるような気がします。江戸時代のようにはいかないと思いますけど、まずは物を大事に使うという習慣を思い出すところから始められるといいですよね。
-------------------
物を大切にする心をはぐくむ絵本『ねこきちのてぬぐい』
手ぬぐいたちは、おしめにされ、ぞうきんになり、やがてぼろになって燃やされて……。でも、灰になってからも、さまざまに役に立つ、リサイクルの輪ができていた江戸時代のお話。手ぬぐいをきっかけに、物を無駄にしない心や、江戸の循環サイクルなどが自然に学べる絵本です。

かとうまふみさんの絵本はこちら!

かめじいさんからお月見の話をきいて、なまずのぽんたは興味しんしん。でも、池にはふしぎな言い伝えがあって……。さて、どうしたら無事にお月見ができるかな? 季節と行事のよみきかせ絵本シリーズ。

おーくんが、夜中に思いっきりおならをしたら、おならおばけがでてきたよ!おならって、きらわれもの? いえいえそうじゃないんでスゥ~。それはね……。これを読んだら堂々とおならがしたくなる、おなら・ファンタジー絵本。

「狂言えほん」シリーズは、狂言の筋書きをもとにした、小さな子どもも楽しく読むことができるシリーズです。『かずもう』は蚊の精とおとのさまが相撲をとるという、奇想天外ながらもユーモラスな物語展開で見どころの多い名作。古典に親しむきっかけとしてもおすすめです。





























































































かとう まふみ
1971年、福井県生まれ、北海道育ち。北海道教育大学卒業。ディスプレイデザインの仕事を経て、絵本作家に。絵本に『まんまるいけのおつきみ』『おならおばけ』『狂言えほん かずもう』(文・もとしたいづみ)『ねこきちのてぬぐい』(講談社)、『ぎょうざのひ』(偕成社)、『のりののりこさん』『けしゴムの ゴムタとゴムゾー』(BL出版)、『ひょろのっぽくん』(農山漁村文化協会)、『しゃもじいさん』『ぬかどこすけ!』『みそこちゃん』(あかね書房)、「どろろんびょういん」シリーズ(作・苅田澄子 金の星社)、『まあちゃんとりすのふゆじたく』(アリス館)、『かたつむりくん』(風濤社)、『おもちのかみさま』『よつばのおはなし』(佼成出版社)、『おとうさんのこわいはなし』(岩崎書店)、『セイロウさん』(WAVE出版)など、装画・挿絵に『にゃんともクラブ』(作・竹下文子 小峰書店)などがある。
1971年、福井県生まれ、北海道育ち。北海道教育大学卒業。ディスプレイデザインの仕事を経て、絵本作家に。絵本に『まんまるいけのおつきみ』『おならおばけ』『狂言えほん かずもう』(文・もとしたいづみ)『ねこきちのてぬぐい』(講談社)、『ぎょうざのひ』(偕成社)、『のりののりこさん』『けしゴムの ゴムタとゴムゾー』(BL出版)、『ひょろのっぽくん』(農山漁村文化協会)、『しゃもじいさん』『ぬかどこすけ!』『みそこちゃん』(あかね書房)、「どろろんびょういん」シリーズ(作・苅田澄子 金の星社)、『まあちゃんとりすのふゆじたく』(アリス館)、『かたつむりくん』(風濤社)、『おもちのかみさま』『よつばのおはなし』(佼成出版社)、『おとうさんのこわいはなし』(岩崎書店)、『セイロウさん』(WAVE出版)など、装画・挿絵に『にゃんともクラブ』(作・竹下文子 小峰書店)などがある。