

あいさつができる子にするための親の関わり方は? 発達心理学教授が回答
こんなときどうする? 子育てQ&A#83 あいさつがきちんとできる子に育てる方法は?
2022.07.20
教育学博士:渡辺 弥生

同時に、子どもがこれから社会のルールを身につけ、行動に移していくためにも大切なものです。

「あいさつがきちんとできる子に育てる方法は?」(3歳・女の子)

生体リズムを整えることと、あいさつの深い関係
そして、この体験があいさつをはじめとする社会のルールを覚えることと連動していると考えられているのです。
逆にいえば、幼児期に夜中に外出して食事をするような生体リズムをこわす生活をしていると、社会のルールを覚えることが難しくなってしまいます。
朝は「おはよう」、昼は「こんにちは」、夜は「こんばんは」と異なる言葉を使うのも、生体リズムと関係があるのかもしれません。
その意味でも、あいさつを教えていくというのは、「朝がきて『おはよう』と元気に言葉を交わしたら、みんながいい気分になるんだよ」という心と体にとって大切なことを伝えていく大人の役目でもあるのですね。

あいさつを教えるための具体的な方法は?
そう考えると、まず、
◆「おはよう」「こんにちは」「お帰りなさい」「ただいま」「ごめんなさい」「ありがとう」などの言葉を親が率先して使いましょう。
真似したい年齢なので、吸収するのも早いでしょう。
◆頭を下げるだけでも、小さな声でも、その子なりにあいさつができたときはほめてあげることも大切です。
ママパパとしては、家族以外の人にもあいさつをしてほしいと思うかもしれませんが、人みしりや恥ずかしがりやの子もいるので、無理は禁物です。
◆「ママと一緒にごあいさつしようね」などと誘うのはかまいませんが、できなくても責めないようにしましょう。
そこで叱ったりすれば、相手の方もいい気はしません。
「お互いをここちよくするあいさつ」なのですから、これでは本末転倒ですね。
そういうときは、
◆「次は、おはようっていえるといいね」などと話して聞かせたり、あいさつの楽しさや気持ちよさを描いた絵本を読んであげたりして伝えましょう。
今はできなくても、あるとき急にできるようになるのが子どもの特徴です。
あまりあせらずに、毎日の生活の中でゆっくり教えていってあげたいですね。
文/宇野智子 写真/Adobe Stock

げんき編集部
幼児雑誌「げんき」「NHKのおかあさんといっしょ」「いないいないばあっ!」と、幼児向けの絵本を刊行している講談社げんき編集部のサイトです。1・2・3歳のお子さんがいるパパ・ママを中心に、おもしろくて役に立つ子育てや絵本の情報が満載! Instagram : genki_magazine Twitter : @kodanshagenki LINE : @genki
幼児雑誌「げんき」「NHKのおかあさんといっしょ」「いないいないばあっ!」と、幼児向けの絵本を刊行している講談社げんき編集部のサイトです。1・2・3歳のお子さんがいるパパ・ママを中心に、おもしろくて役に立つ子育てや絵本の情報が満載! Instagram : genki_magazine Twitter : @kodanshagenki LINE : @genki











































































































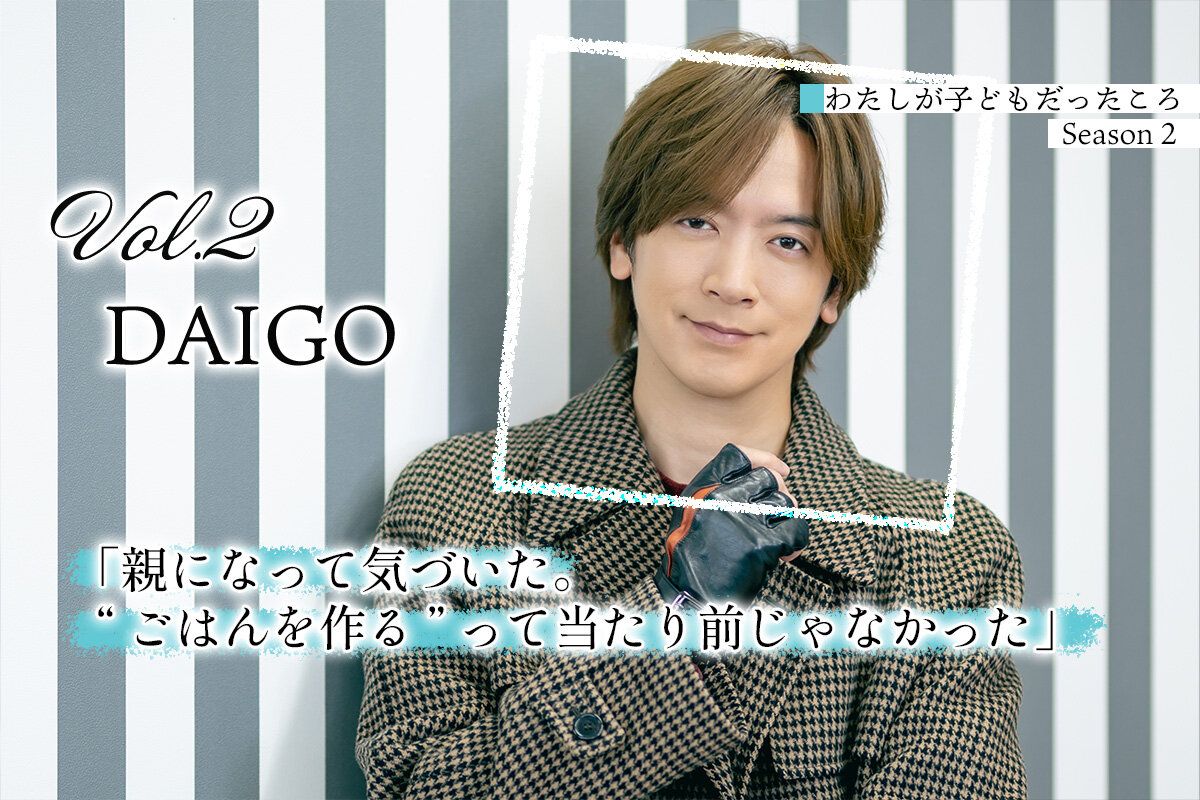









渡辺 弥生
大阪府生まれ。1983年筑波大学卒業。同大学大学院博士課程心理学研究科で学んだ後、筑波大学、静岡大学、途中ハーバード大学客員研究員を経て、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長兼務。教育学博士。専門は、発達心理学、発達臨床心理学。主な著書に『まんがでわかる発達心理学』、『11歳の身の上相談』(講談社)、『親子のためのソーシャルスキル』(サイエンス社)など。
大阪府生まれ。1983年筑波大学卒業。同大学大学院博士課程心理学研究科で学んだ後、筑波大学、静岡大学、途中ハーバード大学客員研究員を経て、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長兼務。教育学博士。専門は、発達心理学、発達臨床心理学。主な著書に『まんがでわかる発達心理学』、『11歳の身の上相談』(講談社)、『親子のためのソーシャルスキル』(サイエンス社)など。